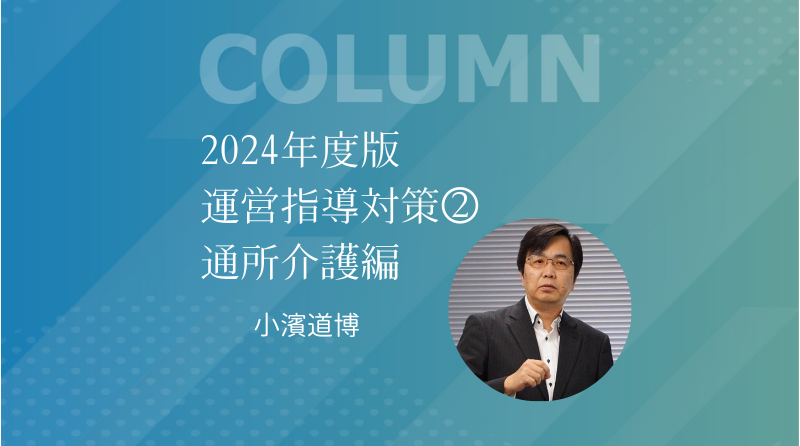通所介護は0.44%、地域密着型通所介護では0.38%の基本報酬がプラスされた2024年度介護報酬改定。
個別改定項目のうち多くの事業所に影響を与えたのは、入浴介助加算Ⅰの算定要件に入浴介助担当者に対し入浴技術研修を実施することが義務化されたことだ。この変更を知らずに従来通りのサービス提供を続けてしては、報酬返還となってしまうだろう。
一方で通所介護の個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)における機能訓練指導員要件が緩和されたことなどは、それまでの事業所の状況によっては増収につながる変更だ。
24年度改定における変更点を中心に、通所介護事業所が運営指導に向けて対策・点検すべきポイントを解説する。
*2024年度介護報酬改定後の運営指導対策〜全サービス・概要編はこちら
1,通所介護の「入浴介助加算」の算定が認められる場合と認められない場合
まず、入浴介助加算は通所介護計画上に入浴の提供が位置づけられていても、利用者側の事情で入浴を実施しなかった場合算定できない加算である。入浴にはさまざまな形があるが、本加算の対象となるのは全身浴と部分浴、全身シャワー、部分シャワーであり、清拭では算定できない。一方で身体的な介助を必要とせず、利用者がほとんど自力で入浴できるケースであっても、利用者が入浴するのを見守り、結果として、身体に直接接触する介助を行わない場合も加算の対象となる。
それまで9割の事業所が算定している入浴介助加算Ⅰでは、冒頭で触れた通り「入浴介助に関する研修」が必須の算定要件となっている。入浴介助に関する基礎的な知識や技術を習得する機会を設けるために実施し、研修を実施した事実がわかるように研修記録を作成して、事業所で保管する。
入浴介助に関する研修は、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴の一連の動作を対象に実施する。
研修内容の例としては、入浴介助担当職員に必要な入浴介助の技術や転倒・入浴事故防止のためのリスク管理の知識、安全管理といったテーマが考えられる。これらの研修は、内部・外部の受講を問わないが、継続的に研修の機会を確保しなければならない。近年は、オンラインの入浴介助講座も充実しているので、それらを活用することも選択肢の一つである。
また、入浴介助加算Ⅱは通所介護のほか、通所リハビリテーションでも医師等が利用者の居宅を訪問することが難しい場合、代わりに介護職員が訪問して、医師等の指示の下にビデオや写真、テレビ電話システムなどの情報通信機器を活用して浴室での利用者の動作や浴室の環境を記録し、これをふまえて医師等が評価・助言を行うことが認められるようになった。
つまり、介護職員がカメラマン的な立ち位置で居宅訪問することができるようになったのだ。
このとき、テレビ電話のシステム画面を通して同時進行で医師等が対応する必要はない。利用者の動作を映した動画や、浴室環境の写真を活用して、医師等が評価をすれば要件が満たせる。注意すべきは、介護職員に認められているのは、あくまでもカメラマン的な位置づけで訪問することであって、評価・助言を行うのは医師等であるということである。
2,通所介護の個別機能訓練加算算定に関する注意点
通所介護の「個別機能訓練加算」では区分(Ⅰ)ロの機能訓練指導員の配置要件が緩和され、報酬単位が減額された。
機能訓練指導員2名以上の配置を必要とする区分であるが、最低1名を常勤専従とする要件は廃止された。これで、機能訓練の時間帯に配置する指導員は2名とも非常勤でも認められるようになった。その分、加算単位は減額されている。
この変更によって、リハ職を手厚く配置してきたリハビリ(機能訓練)特化型デイサービス(通所介護)は減収となった。しかし、それ以上に、常勤専従規定が壁となってⅠ(ロ)の算定ができなかった事業所が、同加算を算定できるようになったメリットは大きい。新たにこの加算を算定した事業所は、20単位の増収となる。
たとえば、午後から非常勤の機能訓練指導員が勤務しているほか、常勤で看護職員を1名配置している通所介護事業所の場合、常勤職員を午前中は看護職員、午後は機能訓練指導員として扱うことで、午後の時間帯は機能訓練指導員2名体制となりⅠ(ロ)の算定ができるようになる。
個別機能訓練加算の各区分の違いや注意点は以下の通りだ。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
- 専従の機能訓練指導員として理学療法士等を1人以上配置する。
- 機能訓練指導員には「常勤」の算定要件がない。看護師を午前中は看護職員、午後から機能訓練指導員として配置した場合も算定可能である。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
- 加算(Ⅰ)イの要件である機能訓練指導員とは別に、専従の機能訓練指導員を1人配置した時間帯に訓練を受けた利用者は、加算(Ⅰ)ロが算定できる。
- 機能訓練指導員の2人以上の配置がなく、1人配置している時間は、加算(Ⅰ)であれば算定することができる。ただし、日々の機能訓練指導員の配置人数・時間を事前に利用者とケアマネジャーに通知している必要がある。
LIFEでデータ提出とその活用を要件とする加算(Ⅱ)は加算(Ⅰ)のいずれかに上乗せして算定する。
なお、(Ⅰ)のイとロいずれにおいても3カ月に1回以上の頻度で機能訓練指導員等(機能訓練指導員、看護職員、生活相談員、その他の職種のもの)が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活を確認した上で、利用者または家族に機能訓練の内容、評価や進捗状況を説明する必要がある。そして、訪問の内容を記録するとともに、機能訓練の見直しを行う。個別機能訓練計画を作成するために利用者の居宅を訪問している時間について、人員配置基準上で確保すべき勤務延時間数に含めるか否かの判断は、以下の通り、職種によって異なる。
①機能訓練指導員
個別機能訓練の実施に支障がない範囲であれば、配置されているとみなされ、勤務延時間数に含めることができる。
②生活相談員
利用者の居宅を訪問して在宅での生活状況を確認したり、利用者の家族も含めた相談・援助に対応したりしている場合は、勤務延時間数に含めることができる。
③介護職員
確保すべき勤務延時間数に含めることができない。
④看護職員
利用者の居宅を訪問する看護職員とは別に看護職員が確保されていない場合、利用者の居宅を訪問する看護職員は、その訪問している時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図る必要がある。
3,ADL維持等加算の変更点と利得の算出について
ADL維持等加算は区分Ⅱの算定要件である、ADL利得が2から3に引き上げられた。同時に利得の計算方法も簡素化された。特定施設や介護老人福祉施設の同加算も同じ変更が行われている。
改定後の各区分ではそれぞれ以下の水準のADL利得を得る必要がある。
①加算(Ⅰ) 調整済ADL利得の平均が1以上
②加算(Ⅱ) 調整済ADL利得の平均が3以上
この「調整済ADL利得の平均」の求め方については、次の通りである。
調整済ADL利得とは
「調整済ADL利得」とは、利用開始時のADL値や要介護認定の状況に応じた調整値を加えたADL利得のことをいう。
具体的には、「評価対象利用開始月の翌月から起算して6カ月目の月のADL値」から「評価対象利用開始月のADL値」を引いて、次の表の評価対象利用開始月に測定したADL 値(左欄)に応じて右欄の「調整値」を加えた値になる。
| 評価対象利用開始月に測定したADL値 | 調整値 |
| ADL値が0以上25以下 | 1 |
| ADL値が30以上50以下 | 1 |
| ADL値が55以上75 以下 | 2 |
| ADL値が80以上100以下 | 3 |
調整済ADL利得の平均の計算方法
加算の要件となる「調整済ADL利得の平均」は、利用者全員の平均ではなく、ADL利得の多い順に上位10%と下位10%を除いた利用者で計算する。つまり、「調整済ADL利得」の値の上位と下位のそれぞれ1割を除いた、8割の利用者で平均を計算する。
この加算は、通所介護を一定期間利用した人について、ADL(日常生活動作)の維持・改善の度合いが一定の水準を超えた場合に算定する。算定にあたっては、事業所を6カ月以上利用している利用者(評価対象者)の総数が10人以上必要である。
事業所の利用開始月と、利用開始月の翌月から起算して6カ月目にADL値を測定する。ADLの評価は一定の研修を受けた者が Barthel Index(BI)を用いて行い、その評価に基づく値(ADL 値)を測定する。
「研修」は、さまざまな主体が実施するBIの測定方法の研修のほか、厚労省が作成するBI のマニュアルや測定の動画等で測定方法を学習する。
ADL値の提出はLIFEを用いて行い、算定の可否もLIFEが通知する。
4,認知症加算における変更点と利用者の割合の算出について
認知症加算は算定要件である、認知症利用者の割合が「15%以上」に緩和された。
前年度または前3カ月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来す症状・行動があるため介護が必要な認知症の利用者の割合を計算する。算定の対象となるのは日常生活自立度Ⅲ以上の利用者のみである。
認知症利用者の割合を算出する際の考え方
「前3カ月」の直前の月は実績ではなく予測値で利用者を計算する。
「日常生活に支障を来す症状・行動があるため介護が必要な認知症の利用者」とは、日常生活自立度Ⅲ以上の認知症の利用者をいう。
「認知症の利用者の割合が15%以上」とは、具体的には、次の計算式のどちらかの値が0.15を超えていることが必要。いずれか有利な方を選択できる。
a 利用実人員数認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用実人員数
b 利用延人員数認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用延人員数
その他の代表的な注意事項は以下の通り。
認知症高齢者の日常生活自立度の判定は、最新の医師の判定結果又は主治医意見書によって判断して、通所介護計画書に記載する。
医師の判定がない場合は、認定調査員が記入した「認定調査票」の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いる。
認知症介護研修修了者が配置されていない日は、本加算は算定できない。逆に、利用者の中に本加算対象者がいない日であれば、配置は不要である。
5,通所介護におけるその他のチェックポイント
上記のほか、24年度改定の変更点としてはLIFE加算の算定要件も見直しがある。これまで加算によって異なっていたLIFEへの提出頻度が3カ月毎に統一され、算定要件も緩和された。
また、通所系サービスにおける送迎では共同送迎が認められていることも確認しておきたい。