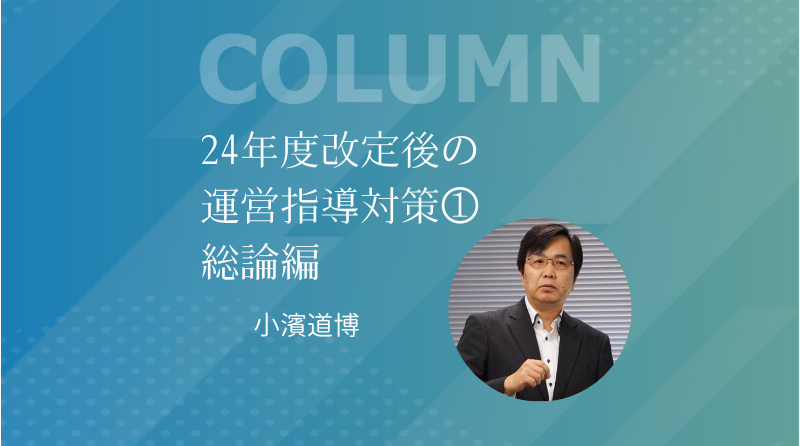2024年度に入り、コロナ禍の間に自粛傾向にあった介護施設・事業所への運営指導が一気に強化されている。BCP関連の対応や高齢者虐待防止措置など、多岐にわたる新要件に適切に対応することも必要だ。今回から、運営指導のトレンドを解説すると共に、事業所が対応すべき項目について点検していこう。
※通所介護編はこちら
1,急増する運営指導件数と増える報酬改定対応―運営指導を巡るトレンド概説
24年度の運営指導の実施件数は全国で10万事業所を超えると推測される。更に、24年3月で3年弱の間続いてきたコロナ禍特例も廃止となった。今後は、コロナ感染などを理由とした人員の欠員であっても、無条件で人員欠如減算となる。しかし、コロナ禍特例が採用されていた3年の間に介護業界に就労した職員は、それが普通と思い込んでいる場合がある。本来の基準について再確認と周知が急務である。
24年度の介護報酬改定を振り返ると、変更のあった項目数は過去最大規模である。人員基準や運営基準だけでなく、多くの既存加算の算定要件に変更があった。前回の2021年度改定辺りから、既存加算の算定要件が見直されることが増えている。
以前の報酬改定は基本報酬の増減と新加算の創設が主体であり、新加算を算定しない場合は、特に日常的な業務を見直す必要が無かった。それゆえに改定内容にアンテナを張ることも無く、従来通りの業務を繰り返すだけでも対応が足りた時代があった。
しかし、現在は、自らセミナーに参加するなどして最新情報を確認しなければならない時代となった。これを怠る事業所は、運営指導において返還指導などを受けることとなる。

(資料出典:令和5年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(総務課介護保険指導室))
2,標準確認項目と標準確認文書で運営指導の効率化・標準化を促進
運営指導は、基本的に「標準確認項目」及び「標準確認文書」に基づいて実施される。24年7月4日に発出された「介護保険施設等運営指導マニュアル」に関する通知で、最新版が公開された。
※介護保険施設等運営指導マニュアル掲載ページ(厚生労働省ウェブサイト)
「標準確認項目」は、いわば運営指導におけるチェックリストである。「標準確認文書」は、事業所がチェックリストにある各項目を満たしているかどうかという視点で確認すべき書類である。例えば、確認項目は、「専門職は必要な資格を持っているか」であれば、その確認文書は「資格者証」という関係である。これらを活用して、行政担当者は運営指導を行うことになる。
現在の運営指導は、2時間程度で終わる形式に移行している。従来のように1日掛けて実施していた“質の重視”から、ポイントを絞った“量の指導”に変わりつつある。この標準確認項目は、運営指導の標準化や効率化を図るために定められたものでこれによって一件当たりの所要時間を短縮し、一日に複数件の運営指導を実施することが想定されている。
今回、各サービス共通項目として新たな「標準確認項目」に組み込まれたのは、24年度から義務化されて、減算も創設されたBCPなどへの対応である。

(【画像】介護保険最新情報Vol.1288(「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)」の一部改正について 2024年7月4日厚生労働省老健局長通知)
3,業務継続計画(BCP)の義務化―減算適用は免れても運営基準違反となることに注意を
21年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業者を対象に業務継続に向けた計画等の策定を始めとする取組の強化が義務化された。計画等(BCP)の策定、研修の実施、訓練の実施等が必要である。研修や訓練に関しては、定期的な実施をして記録しなければならない(在宅サービスは年1回以上、施設サービスは年2回以上)。
24年度改定で設けられたBCP減算は、特例を受ける場合、適用されるのは25(令和7)年4月からである。しかし、減算の有無は介護報酬上の要件に過ぎない。24年4月から施設や事業所に対応が義務化されている事実は変わっていないため、運営指導を受ける際に計画が未策定であれば減算にはならないが運営基準違反で指導対象となる。研修や訓練が未実施である場合も同様である。
運営基準に定められているのは以下の通りである。
BCPに基づく研修と訓練の実施義務
解釈通知においては、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施において、定期的(在宅系サービスは年1回以上、施設サービスは年2回以上)な研修を開催して記録しなければならないとされた。訓練(シミュレーション)は、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(在宅サービスは年1回以上、施設サービスは年2回以上)に実施する。
4,高齢者虐待防止措置への対応
こちらも21年度報酬改定で全サービスでの対応が求められるようになった。具体的に必要なのは、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、専任の担当者を定めることである。24年3月まで経過措置期間であったが、4月から義務化されて、未実施の場合は運営基準違反として指導対象となる。同時に、減算も創設された。福祉用具貸与だけは特例として3年の経過措置があるが、その他のサービスで未実施の場合はこの4月から1%の減算が適用されている。
以下、必要な対応について個別に内容を確認しよう。
①虐待防止検討委員会の開催
虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加えて、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会である。管理者を含む幅広い職種で構成する。役割分担を明記した委員会名簿を作成して、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。
②指針の作成と研修の実施
虐待の防止のための指針を作成する。研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識、指針に基づいて虐待の防止の徹底を行う内容とする。 職員教育を組織的に徹底させていくために、指針に基づいた研修プログラムを作成して、年1回以上の定期的な研修を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要となった。また、研修記録は保存する。専任の担当者を置くことが必要で、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましいとされている。
5,感染症対策の義務化
21年度介護報酬改定に於いて、全サービスに感染症の発生及びまん延等に関する取組として、感染対策委員会の開催、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の策定、研修と訓練が義務化された。こちらも3年間の経過措置が設けられていたが、24年4月から運営指導において確認される。未実施の場合は、運営基準違反の指導や勧告を受ける。
①感染対策委員会の開催
感染対策委員会は、おおむね6カ月に1回以上の定期的開催ともに、感染症が流行する時期等に必要に応じて随時開催する必要がある。 外部を含めて感染対策の知識を有する者を含み、幅広い職種により構成することが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を記した委員会名簿を作成して、専任の感染対策担当者を決めておく必要がある。
②感染症の予防及びまん延の防止のための指針
指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。平常時の対策は、事業所内の衛生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等を記載する。また、発生時における事業所内の連絡体制や関係機関への連絡体制を整備して明記しておくことが必要である。
③感染対策の研修と訓練の実施
研修の内容は、感染対策の基礎的な内容等の知識、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う内容とする。年1回以上、定期的に開催するとともに、新規採用の際には感染対策研修を実施することが望ましい。終了後は研修記録を作成する。また、実際に感染症が発生した場合を想定して、発生時の対応についての訓練(シミュレーション)を年1回以上、定期的に行う必要がある。訓練は、感染症発生時に迅速に行動できるように、発生時の対応を定めた指針と研修内容に基づいて、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施する。訓練の実施は、机上のシミュレーションを含めて、実施手法は問わない。シミュレーションと実地訓練を組み合わせながら実施することが適切である。
なお、感染症対策の研修・訓練は業務継続計画(BCP)における研修、訓練と合わせて実施することが可能である。
6,認知症介護基礎研修の受講義務とその対応
介護職員として配置され、初任者研修修了者、介護福祉士、看護師等の医療福祉の資格を持たない職員は、配置した日から1年以内に、認知症介護基礎研修の受講が義務化となっている。
7,身体拘束の記録の義務化とその対応
訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援については、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束等を行ってはならない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、3原則を厳守した上で、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務づけられている。
ここまで、原則としてすべてのサービス事業所に対応が求められる項目について紹介した。
次回は、通所系サービスについて論じていこう。