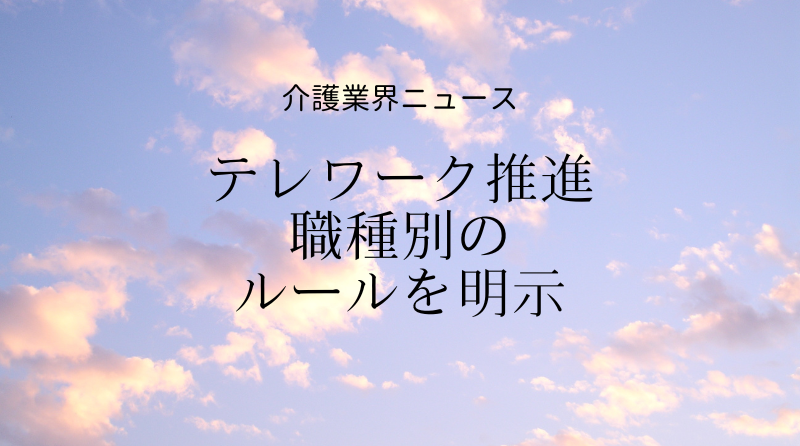2024年度介護報酬改定で重視されている施策の一つが、「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」です。
その具体的な施策にテレワークの推進があります。
3月29日発出の通知では、介護現場の従事者のうち、人員配置基準で必要数が定められている職種のテレワークが認められる範囲が示されました。
ポイントとしては、書類作成等の事務作業や事業所外の専門職といった業務は、日時を事前に決めておけば、テレワークの実施が認められます。
一方で、利用者らとの面談・相談やアセスメント等のための観察等については、詳細な注意事項も定められています。
「介護職員」や「生活相談員」、「機能訓練指導員」といった職種別の取り扱いも明らかになっていますのでご確認ください。
2024年度介護報酬改定で現場従事者も一定の範囲内でのテレワークが可能に
今回新たに考え方が示されたのは、介護保険法上の各サービスにおいて人員基準や運営基準で配置が義務付けられている現場従事者のテレワークについてです(特別養護老人ホームの職員、軽費老人ホーム、養護老人ホームの従業者もこの内容に準じた取扱いが可能)。
なお、事業所や施設などの管理者のテレワークは、「個人情報の適切な管理を前提に、介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において」可能であるとの考え方が23年9月時点で示されていました。今回の通知以降も基本的にこの方針が踏襲されます。
介護事業所等の現場従業者のテレワークに関する基本的なルール
介護事業所等の従業者によるテレワークについて、基本的なルールは以下のとおりです。
①人員配置基準等で定められた必要数以上の従業者は、基準を上回る部分について、個人情報の適切な管理を前提に、テレワークを実施しても差し支えない。
※例えば常勤換算3.0人が必要で実際の配置数が常勤換算 3.2 人の場合、常勤換算0.2人の部分で従業者がテレワークの実施が可能。
②基準上の必要数を上回らない部分については、利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲内であれば、テレワークを実施しても差し支えない。
※例えば常勤換算3.0人の配置が必要で、1人のがテレワークを実施し、サービス提供場所(事業所・施設等及び利用者の居宅等)で業務に従事する従業者数が3.0 人を下回る場合(例えば、常勤換算2.8 人となる場合)でも、 利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、テレワークを実施しても差し支えない。
③人員配置基準等で常勤換算職員数や常勤職員数等の具体的な必要数が定められていない職種については、 個人情報の適切な管理を前提に、当該職種の職責を果たすことができるのであれば、人員配置基準上は、業務の一部をテレワークにより実施しても差し支えない。
ただし、②の人員配置基準を下回る場合、原則としてテレワークが認められない職種があります。
「利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲」とは
前述の②の通り、テレワークを実施することで現場の人員配置基準が満たせなくなる場合、「利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲」に限定してテレワークが認められます。その具体的な範囲は以下の通りです。
| (1) 各職種の従業者がテレワークを行い、事業所等を不在とする場合でも、運営基準上定められた各職種の責務・業務に加え、テレワークを実施する従業者が実務上担っている役割を果たす上で、支障が生じないよう体制を整えておくこと。 ※テレワーク実施者本人、管理者及びテレワーク実施者以外の従業者に過度な業務負担が生じ、利用者の処遇に支障が生じることのないよう留意する。 ※事業所等に不在となる時間が一定以上生じることで、その職種としての責務の遂行に支障が生じる場合はテレワークの実施不可。 (2)テレワークを実施できる日数・時間数は、サービスの種類や事業所等の実態等に応じて、各事業者で個別に判断する。 ※終日単位で事業所等を不在にする場合、利用者の処遇に支障が生じないかを特に慎重に判断する。 (3)勤務時間中、事業所等の現場に出勤する従業者とテレワーク実施者の間で適切に連絡が取れる体制を確保する。 (4)テレワーク実施者の労働時間の管理等、適切な労務管理を行う。 (5)個別業務のうち、書類作成等の事務作業、事業所外の専門職との連絡等の業務については、予めテレワークを行う日時を決めておけば、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。 (6) 個別の業務のうち、利用者・入所者との面談・相談やアセスメント等のための観察等の業務については、相手方の表情や反応を直接確認する必要があり、自身と相手方の双方に相応な機器操作能力が求められることに加え、情報通信機器を通じた音声の聞き取りづらさ等、意思疎通の上で一定の制約がある。 そのため、情報通信機器を用いた遠隔での面談等の実施については、意思疎通が十分に図れる利用者について、利用者本人及び家族の理解を得 て行うなど、適切に対応すること。 ただし、家族との面談については、家族側でも操作環境が構築でき、家族の同意がある場合には、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。 |
テレワークの実施について職種ごとの考え方(人員配置基準を下回る場合)
今回の通知では人員配置基準を下回る場合のテレワークの実施について、職種ごとに詳細な留意事項が示されています。
主なものを以下に紹介します。
① 医師について(介護老人保健施設、介護医療院および介護老人福祉施設)
介護老人保健施設及び介護医療院の医師は、個別の入所者の状態によってはオンライン診療に準じた対応では十分ではない場合があることに留意する。
施設に不在となる時間がある場合、 緊急時の対応の体制を整え、利用者の処遇に支障が生じないようにしておく。その際、テレワークの実施及びそれに伴って生じる事態について、予め責任の所在を明確にしておく。
※介護医療院の I 型療養床で求めている医師の宿直は、テレワークでの実施は認められない。
介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 空床利用型短期入所生活介護を含む。)の配置医師は、人員基準上の具体的な必要数の定めはないが、入所者の状態を適切に把握することが困難な場合には入所者の処遇に支障が生じることに留意する。
② 薬剤師 (介護老人保健施設、介護医療院、居宅療養管理指導)
介護老人保健施設及び介護医療院の薬剤師は書類作成、薬剤の発注等の事務作業や職員からの薬剤に関する相談対応等、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
介護保険施設における服薬指導について、同一事業所内に他の薬剤師が存在しない場合は、施設の現場に出勤する看護職員と連絡が取れる体制を確保する。
調剤業務については、原則として、テレワークでの実施は認められない。
入所時の入所者の薬剤の確認及び評価、副作用の発現の確認は、原則として、入所者の状態等を直接確認する必要がある。
居宅療養管理指導を行う薬剤師は、利用者の同意及び個人情報の適切な管理を前提に、情報通信機器を用いた服薬指導を実施しても差し支えない。また、患者の異議がない場合は、薬剤師の自宅等から情報通信機器を用いた服薬指導を行うことも可能であるが、薬局で調剤に従事する薬剤師と相互に連絡を取れる 環境を確保するともに、情報通信機器を用いた服薬指導を開始した 後に、利用者から対面での服薬指導への移行の求めがあった場合には、テレワーク実施者本人又は他の薬剤師によって速やかに対応可能であることが必要。
③ 介護職員・看護職員について
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても利用者の処遇に支障がないと考えられるが、職員が事業所等に不在となることで利用者の処遇に支障が生じないよう十分留意する。
利用者を直接処遇する業務及び直接処遇に関わる周辺業務は、原則テレワークでの実施は認められない。
※夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務について、これまでの取扱いを変えるものではない。
④ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士について
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても利用者の処遇に支障がないと考えられる。
面談等の業務は、意思疎通が十分に図れる利用者について、本人・家族の理解を得て行うなど、適切に対応する。
リハビリテーションの実施等の利用者を直接処遇する業務は、原則として、テレワークでの実施は認められない。
テレワークの実施日時及び時間数を決める上では、施設・事業所全体で提供するリハビリテーションの時間が減少しないよう留意する。また、利用者の希望する訓練実施日に影響しないよう留意する。
⑤ 機能訓練指導員について
書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
面談等の業務は、意思疎通が十分に図れる利用者について、本人・家族の理解を得て行うなど適切に対応する。
機能訓練の実施等の利用者を直接処遇する業務は、原則として、テレワークでの実施は認められない。
※集団での機能訓練に際し、介護事業所内で他の機能訓練指導員等の従業者がサポートを行ったとしても、機能訓練の質の担保には懸念・課題があることから、原則として、テレワークでの実施は利用者の処遇に支障が生じると考えられる。
テレワークの実施日時及び時間数を決める上では、事業所全体で提供する機能訓練の時間が減少しないよう留意する。また、利用者の希望する訓練実施日に影響しないよう留意する。
⑥ 管理栄養士・栄養士について
利用者に対する食事提供の実務上の責任者として現場での対応が必要になることから、テレワークの実施は原則として認められない。
※ ただし、管理栄養士・栄養士の不在時における意思決定の流れ等を明確化しており、併設事業所も含めて管理栄養士・栄養士が複数名配置されている等、現場での急な対応を他の従業者で代替することができる場合に限り、計画的なテレワークの実施であれば、利用者の処遇に支障は生じないと考えられる。
※その際、書類作成・食材発注等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
上記の場合にテレワークを実施する場合であっても、ミールラウンド(食事の観察)については、利用者の食事・嚥下の状態を直接確認する必要があり、原 則として、テレワークでの実施は認められない。
⑦ 介護支援専門員について(居宅介護支援・介護予防支援)
書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
居宅サービス計画の作成等をテレワークで行うに当たっては、適切なアセスメントやモニタリングが行われた上で実施する必要があることに、留意する。
運営基準上義務付けられている少なくとも1カ月に1回(介護予防支援は3カ月に1回)利用者に面接することにより行うモニタリ ングについて、オンラインで行う場合は、利用者の同意を得るとと もに、利用者がテレビ電話装置等を用いた状態で十分に意思疎通を図ることができることを確認する。
サービス担当者会議をオンラインで行う場合は、家族含む関係者間で対象者の現状を共有できるよう、また利用者・家族との意思疎通が十分にとれるよう、留意する。
⑧ 介護支援専門員について(居宅介護支援・介護予防支援以外)
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
(地域密着型)施設サービス計画や(看護)小規模多機能型居宅介護計画の作成をテレワークで行うに当たっては、利用者の直接的な観察や対面でのやり取り、他の従業者からの聞き取り等が十分に行われた上で行う必要があることに留意する。
事業所等内で従事する従業者の業務負担が過重となったり、従業者間に必要なコミュニケーションが不十分なものとなったりすることがないよう留意する。
⑨ 計画作成担当者・計画作成責任者について
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
認知症対応型共同生活介護計画・特定施設サービス計画・定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護計画の作成をテレワークで行うに当たっては、利用者の直接的な観察や対面でのやり取り、他の従業者からの聞き取り等が十分に行われた上で行う必要があることに、留意が必要する。
事業所等内で従事する従業者の業務負担が過重となったり、従業者間に必要なコミュニケーションが不十分なものとなったりすることがないよう、留意する。
⑩生活相談員・支援相談員について
書類作成等の事務作業は、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。
意思疎通が十分に図れる利用者について、本人・家族の理解を得て行うなど、適切に対応する。
特に契約に関する説明や、重要事項の説明をテレワークで実施する場合、必ず利用者本人及び家族の同意を確認した上で、内容が適切に利用者・家族に伝わっているか等、特に留意して確認する必要がある。
相談員が現場を不在とすることで、事業所全体としてのサービス提供に影響が出ないよう、また他の従業者の業務負担が過重なものとならないように、特に留意する。
⑪ 保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等(地域包括支援セン ター)
地域包括支援センターの各職種については、センター内における相談対応の他、対象者や外部機関との面談・調整、地域の会議への出席など、各職種に求められる業務の場が、センターの内外にまたがっていることを踏まえ、職種間や従業者間で連絡・フォローをしながら、 来所相談への対応や特定の従業者による対応を要するケース等に関する申し送り等を行うことが求められる。
そのため、書類作成等の事務作業はテレワークで実施しても利用者の処遇に支障がないと考えられる。
ただし、以下の体制を維持できるように留意すること。
(i) 営業時間中、いずれか 1 人以上の従業者がセンター内に滞在する等により、急な来所相談にも対応が行える体制
(ii) センターを不在としている従業者への連絡・フォローを行う ことのできる体制
⑫ 福祉用具専門相談員について
福祉用具の選定や納品、提供後の使用状況の確認、使用方法の指導 や修理等の業務は、原則として、テレワークでの実施は認められない。
書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。ただし、テレワークを実施する場合は、福祉用具の提供に関わる突発的な事態等に対応できる体制を事業所において整備しておく必要がある。
個人情報の適切な管理について
テレワークの実施にあたっては、利用者の処遇のほかに管理者・現場従事者とも個人情報の適切な管理が前提となります。
今回の通知では、個人情報の外部への漏洩防止や外部からの不正アクセスの防止のための措置を講じることなどを求め、関連するガイドラインなども示されています。
ぜひ、ご確認ください。
*【介護保険最新情報】:vol.1237介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項ついて(2024年3月29日付け通知)
テレワーク・ICT活用に関する関連記事
- 管理者や施設長のテレワークが可能に―厚生労働省が考え方を明示(2023年9月12日ニュース記事)
- ICTリテラシー向上と介護事業所の管理者によるDX推進テーマにした連載コラム(NPO法人タダカヨ )
- 連載「介護業界のDXを推進するキーパーソンたちに聞く」(医療健康ジャーナリスト・新村直子氏取材)