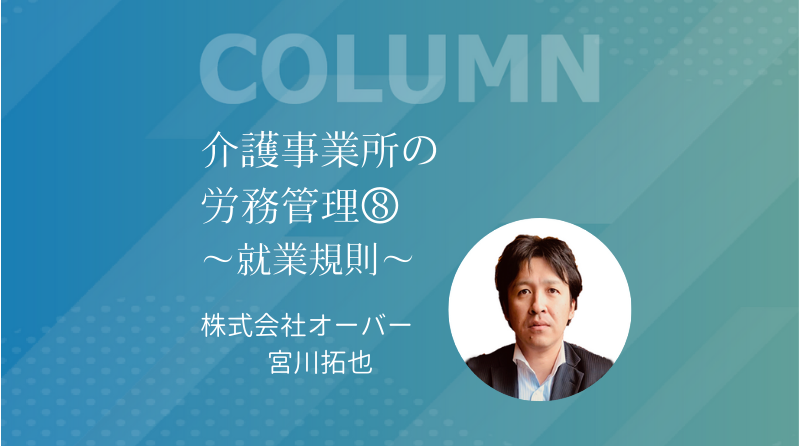多様な働き方を受け入れる上での「相対的必要記載事項」の重要性
前回は、就業規則が必要な理由について以下を指摘しました。
1つ目の理由は、法律で定められているから。
2つ目の理由は、会社(職場)のルールを従業員に伝えるため。
3つ目の理由として、就業規則は、会社を成長・発展させるもの。
働き方改革が進められている昨今、また、その中でも多様性への対応を求められている今、2つ目の役割は大変重要です。
私は、社会保険労務士として介護事業者に助言する際、「会社として働き方の多様性を認めるのであれば、その分だけ基礎となるルールは明確に、そして分かりやすく伝えてください」と伝えています。
実際に、就業規則等で申し分のないルールを定めていたとしても、その内容が伝わりにくければ、受け止め方が変わってしまうのも事実です。
就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、各事業所内のルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)がある事を前回お伝えしました。多様な働き方を受け入れ、円滑な事業運営を行うには、この相対的必要記載事項が重要です。
【相対的必要記載事項】
(1)退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(2)臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
(3)費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
(4)安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
(5)職業訓練関係
職業訓練に関する事項
(6)災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8)その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
中小企業の人事労務では、「この取り扱いはどうだったかな?」とよく悩まれる項目です。
その都度異なる対応をしていては、後々のトラブルにつながります。
正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者等の非正規労働者との間の不合理な待遇差や差別的取扱いが禁止されている今、ルールを明確に定めておくことが重要です。
では、今回も就業規則に記載する内容について、具体的な項目を挙げながらポイントを見ていきたいと思います。
時間外労働について記載する際のポイント
(時間外及び休日労働等)
(1) 第○条 業務の都合により、第○条の所定労働時間を超え、又は第○条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性労働者(以下「妊産婦」という)であって請求した者及び18歳未満の者については、第2項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。
4災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
人事労務では、時間外労働に関するトラブルが多発します。
「残業分の賃金が全く払われていない」「残業分が一部カットされている」といったトラブルの原因は、「会社が意図的あるいは無意識に支払っていない」か「残業時間の管理方法での誤り」がほとんどです。
そこで経営者が認識すべきは、従業員が自身の労働時間と賃金の関係について、今まで以上に強く意識するようになっているということです。
こうした意識を強くした理由の1つとして、副業が進んでいる事が挙げられます。
A社では、○時間は労働したので○円、B社では、○時間は労働したので○円と収入の計画を立て、生活設計する従業員はこれから、ますます増えていくでしょう。
時間外労働を含む労働時間の曖昧な取り扱いは従業員の生活に直結するのです。
時間外及び休日労働等については、そのルールを定めた上で、あくまでも業務命令とし、ダラダラ残業を阻止することも必要です。そのため、業務の効率化を図るため文言を盛り込みます。
例えば、「時間外労働は、原則業務命令により行う事」「時間外労働が命じられた場合は、原則拒否することができない(育児・介護休業制度等により所外労働の免除等の対象者のぞく)」といった文言の付与です。
従業員には、職務に専念する義務があります。
ただ、入職後間もない従業員には、細かく業務を命令することも必要ですが、一定の経験や成果を出している従業員に対しては、目標を設定・提示した上で、ある程度の主体性、自己裁量を与えることが有効です。
そのため、時間外労働は許可制とし、業務が時間外に及ぶ時はその承認を得るという仕組みも効果的です。
この際、「どのような業務が時間外に発生し、どれぐらいの時間を要するのか」を会社が把握する事も事業運営の上では意義があります。時間外労働の申請内容は、経営を改善する上で重要な情報として扱う事をおすすめしています。
年次有給休暇の取り扱いと就業規則に記載する際のポイント
(年次有給休暇)
第○条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える

2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

3 第1項又は第2項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
4 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
6 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
① 年次有給休暇を取得した期間
② 産前産後の休業期間
③ 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間
④ 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
7 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。
8 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。
9 会社は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細書に記載して各労働者に通知する。
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
年次有給休暇については、労働基準法の改正により、2019年4月から、全ての事業者において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。この改正に伴い、年次有給休暇の消化に関するご相談が増えました。
その中でも多いのが、退職時に消化しきれなかった年次有給休暇、在職しているが消化できずに消えてしまった年次有給休暇、法律を上回る年次有給休暇(例えば、法律では10日の付与で足りる部分を、13日等法律を上回って付与されている場合における“上回っている日数”)の取り扱いです。
前提として、年次有給休暇の買取りは労働基準法で禁止されています。
例えば、20日間年次有給休暇を持っている従業員に「うちの会社では、なかなか有休を取れないから、あらかじめ10日分をお金で払います」と対応することは違法です。
しかし、退職時に消化しきれなかった年次有給休暇、在職しているが消化できずに消えてしまった年次有給休暇、法律の定めを上回る年次有給休暇の買取りは認められています。また、その額は法律で定められていません。これら買取りに関する取扱いは就業規則に記載する必要はありませんが、ルールを定めておくべきでしょう。
法改正の多い育児・介護休業等への対応のポイント
(育児・介護休業、子の看護休暇等)
第○条 労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業え等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業規定」で定める。
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
昨今、育児・介護休業法が改正を重ねています。就業規則内にそれらの規定を盛り込んで運用しなければならないことは多く手間を要します。また、規則自体も非常に読み込みにくい構造となりがちです。
そこで、「育児・介護休業規定」を別途設けて、法改正の都度に規定を改訂し運用される事をおすすめします。
なお、マタニティハラスメントへの事業者の対策として、現在の制度が従業員に浸透し、理解されていることが重要です。
労働基準法に定めのない特別休暇についての取扱い
第○条 労働者が申請した場合は、次のとおり特別休暇を与える。
2 本人が結婚したとき _日
3 妻が出産したとき _日
4 配偶者、子又は父母が死亡したとき _日
5 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき _日
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
特別休暇は慶弔休暇と表記されている事業者もありますが、定める内容は同じです。労働基準法上の義務ではありません。
しかし、従業員の生活上に生じる事由へ配慮することは意義が大きく、特別休暇(慶弔休暇)についても規定される事をおすすめします。
なお、この特別休暇(慶弔休暇)については、有給・無給どちらでも問題ありません。
そもそも、労働基準法で定められていない休暇ですので事業者の自由です。
第9回目は、「就業規則のポイント なぜ就業規則が必要なのか③」をお届けします。
※この記事は、難しい用語を極力削減し、わかりやすさを重視しています。
この記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。