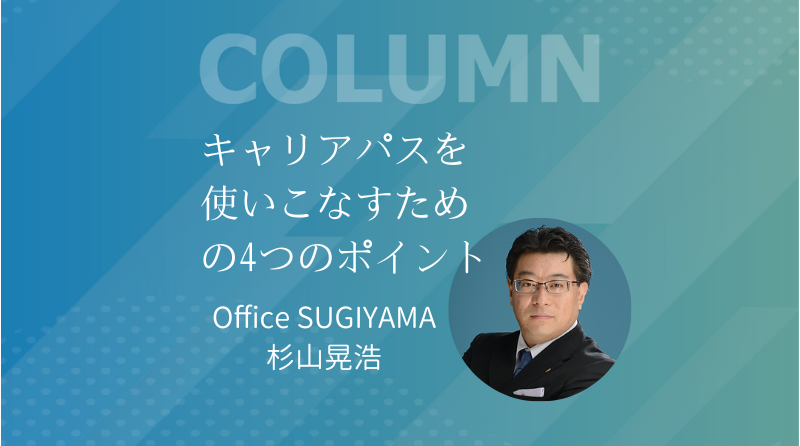1.キャリアパスは介護事業所の人事制度の集大成
処遇改善加算の活用が一般的となり、キャリアパスを作成していない介護事業所は少なくなってきた感があります。一方で、キャリアパスを作ったけれども、上手く運用できないといったといった悩みを抱えている介護事業所も増えてきています。
キャリアパスは基本的に、人事制度を構成する【等級制度】、【評価制度】、【賃金制度】、【育成制度】をシンプルかつ可視化したものといえます。
山形県が関係機関・団体の御協力を得て作成し、一般に公表している小規模法人・在宅事業所版のキャリアパスモデル例を参考にして人事制度を考えてみましょう。

(出典:「山形県介護サービス事業所・施設のモデル給与・服務等規程について」より)
等級制度に関わる項目は、「職位」、「職責(役割)」、「対応役職」、「職務内容」となります。
評価制度に関わる項目は、「求められる能力」です。
賃金制度に関わる項目は、「給与」です。
育成制度に関わる項目は、「任用の要件」です。
4つの制度ごとに項目を分けてみると、キャリアパスが人事制度の集大成であるということがより理解しやすくなります。
それぞれの制度と制度に関わる項目の関係を整理することで、キャリアパスを使いこなすことができるのです。
2.任用要件が職員の育成・定着のカギを握る
介護スタッフが、上位の職責を担い、職責に見合った給与を手に入れるためには、キャリアパスに明示された任用要件をクリアする必要があります。キャリアパスがうまく機能していれば、任用要件をひとつひとつクリアすることで、昇進、昇格、昇給に繋がり、専門職としての能力が高まります。介護スタッフが目指す、職位、職務に到達し、給与が上がれば、離職者がなくなり、介護事業所の経営が安定します。
ところが、『職責や人事評価が給与と見合っていない』、『キャリアパスの基準と職務遂行能力に乖離がみられる』など、キャリアパスの運用に悩んでいる介護事業所も存在しています。そこで、キャリアパス表の任用要件に着目して改善ポイントを探ってみました。
介護事業所のキャリアパスにおける任用要件は、主に次のような指標が利用されています。
①時間軸(経験年数、経験時間)
②資格、社内試験(潜在能力・知識)
③研修受講歴(社内、社外)
④人事評価結果
①時間軸で任用要件を定める際のポイント
経験年数や経験時間が同一であれば、介護スタッフの能力は全て同一レベルに達しているでしょうか。現実には介護スタッフの能力には、ばらつきが生じています。そのため、時間軸のみで任用要件を定めていると、任用要件をクリアして上位の職位に到達したものの業務遂行能力が伴わないという事態が発生する可能性が常に付きまといます。
対応策としては、時間軸のほかに、業務遂行能力を担保する指標を任用要件にプラスすることです。
②資格、試験結果で任用要件を定める際のポイント
介護福祉士などの資格試験に合格すれば、専門分野における一定の知識、能力を担保できます。社内試験においても同様です。ここで重要なことは、各種試験で担保されるのは「一定の」知識、能力であるということです。仮に100点を取ることができたとしても、知識はその瞬間から陳腐化し始めます。
また、資格を保有していることイコール業務遂行能力ではありません。業務遂行にはコミュニケーションやマネジメントの能力が必要不可欠です。有資格者だからどんな仕事もできると感じてしまうのは、ハロー効果による錯覚です。実際に、『資格者だから管理者に任命したけれど部下がついていかない』、『退職者が続出する』などと悩んでいる介護事業所も多数存在しています。
対応策としては、資格や試験結果は介護スタッフの潜在能力を測るものであることを認識し、顕在能力を表す指標を任用要件に加えることです。
③研修受講歴で任用要件を定める際のポイント
職責や職務遂行にあたって必要な研修を受講することのみを任用要件としている場合、資格・試験結果と同様に、それが潜在能力を測るものにすぎないことを肝に銘じておかなければなりません。研修の中には効果測定がセットされたものもありますが、多くの場合は、受講したら終了というタイプのものです。
私は社会保険労務士としてさまざまな企業研修を実施してきました。そして多くの企業が継続研修、ドロー研修を望まない実態があります。経営者にとって、短期的には、研修をした実績さえ残しておけば、トラブルがあったときに『研修をしていました』という事実が重要な意味を持つのでしょう。更に、時間もお金も節約したいという考えもあると思います。しかし、長期的にみれば、せっかく研修したのだから、この時間を将来に活かしきるために継続研修が必要だと私は考えます。
対応策としては、単発的な研修ではなく、継続研修、フォロー研修といった研修効果が陳腐化し難い研修を対象とすることです。
④人事評価結果で任用要件を定める際のポイント
人事評価の結果であれば、総合的に介護スタッフを評価できるため、任用要件としての役割に最適です。ただし、人事評価制度が正しく設計され、運用されていなければ、トラブルを招く原因になります。
次の5つの点をチェックしてください。この5点で問題がなければ、任用要件として素晴らしい効果を発揮します。
☑評価項目や評価基準が明確であるか
☑評価基準が合理的なものとなっているか
☑評価方法が適切なものとなっているか
☑評価者によるばらつきがないか
☑評価結果に著しい偏りがないか
3.事業所の成長にキャリアパスの運用よりも大切なこと
ところで、貴社の従業員満足度(ES)はどのような状態になっていますか。
もしかしたら、『キャリアを高めて職位が上がることによって責任を取りたくない』、『頑張って給与額を上げるより、適当に働いて今の給料がもらえればよい』、『人間関係が良くないので早くこの職場を退職したい』などネガティブな考えを持つスタッフがいるかもしれません。そして、事業所内にネガティブな考えのスタッフが多ければ多いほど、キャリアパスの運用は難しくなります。
従業員満足度が低い介護事業所で『利用者の満足度』が高められますか。
従業員満足度が低い介護事業所で『サービス向上』は望めますか。
従業員満足度が低い介護事業所で、職員は『キャリアパスの実現』に向かって行動しますか。
任用要件を見直し、改善してもキャリアパスの運用がうまくいかないときは、従業員満足度の現状を見える化し、従業員満足度を高める取り組みからはじめてください。
従業員満足度を高めるためには、調査結果から重要な項目やキーワードを抽出し、優先順位付けして、PDCAをまわすことが必要です。
さまざまな従業員満足度チェックツールがありますが、優先順位付けがし難かったり、対処法が商材への誘導になってしまっているものが多いように感じます。
そこで、私がこれまでさまざまなツールを見てきた中で最もわかり易く、使いやすいと感じた「従業員満足度結果報告書」をプレゼントします。研修材料としてご活用いただき、優先順位付けや対処法を考える練習をしてください。
◆「従業員満足度結果報告書(例)」のプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
以下のリンクから簡単なアンケートにお答えいただくと、 「従業員満足度結果報告書(例)」を希望者全員に無料プレゼントします。
お気軽に下記からお申し込みください。
「従業員満足度結果報告書(例)」プレゼント希望