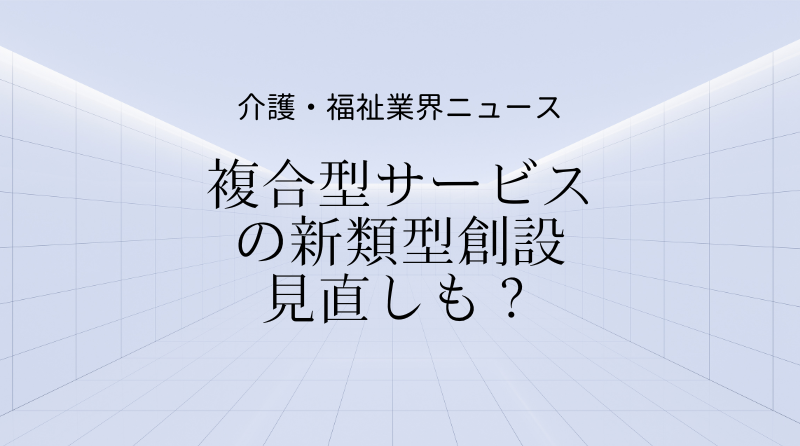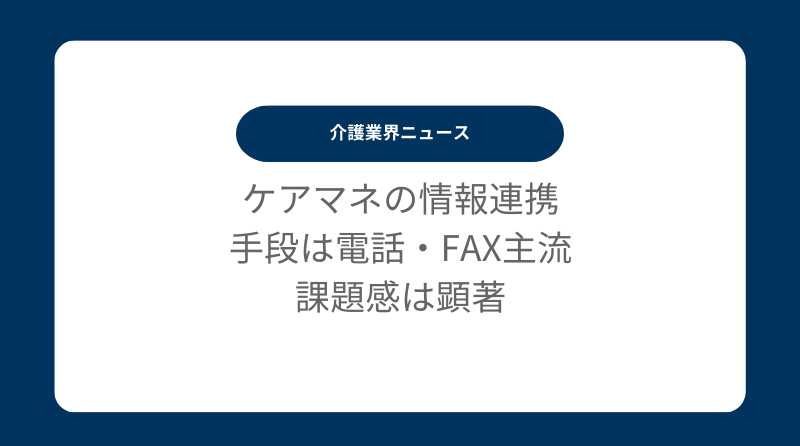2024年介護報酬改定に向けた検討事項の中でも行方が注目されているものの一つが、”新しい複合型サービスの創設”です。訪問介護と通所介護を組み合わせた新しいサービス類型を創設するという提案がなされていますが、これに対して疑問を呈する意見も数多く示され、24年度改定での対応が実施されるかどうかの可否について見通し辛くなってきました。
そもそもこの、”複合型サービスの創設”は事業者にとってどのようなメリットや懸念事項があるのでしょうか。社会保障審議会・介護給付費分科会でこれまでに行われてきた検討をもとに整理します。
複合型サービスとは?なぜ新類型の創設が検討されているのか
「複合型サービス」とは、地域密着型サービスの類型の一つで、居宅要介護者に対して複数の介護保険サービスを組み合わせて一体的に提供するサービスのことをいいます(介護保険法第8条23)。

この「複合型サービス」として、現在は厚生労働省令(介護保険法施行規則第十七条の十二)に「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせた「看護小規模多機能型居宅介護」が認められています。
2024年度介護報酬改定で対応すべき課題の一つに、介護ニーズが急増する大都市部での介護サービスの基盤整備があり、この手段として”既存資源を活用した、複合的な在宅サービスの整備”の重要性が指摘されていました。ここで、新たな複合型サービスの類型として、訪問介護と通所系サービスを組み合わせることが示唆されています。
8月末の同分科会(第222回社会保障審議会・介護給付費分科会)で改めてこの「新しい複合型サービス」をテーマとした際、厚生労働省は
- デイサービスやホームヘルプのニーズは2025年以降も増えることが予測される
- これに対し、人手不足などによって事業所数は頭打ちになっている
ことをデータで示し、特に訪問介護のニーズと人材確保の実態が乖離していることを強調しています。
半数以上の事業者が訪問介護と通所介護の両方を運営
訪問介護の利用者のうち、46.7%がデイも利用
この日、厚労省は、訪問介護の利用者のうち、46.7%がデイサービス(通所介護または地域密着型通所介護)を併用していることを示すデータも共有しています。

(【画像】第222回社会保障審議会・介護給付費分科会資料3より(以下同様))
また、事業者側を見ても、通所介護事業所を運営する法人の55.4%が訪問系サービスの事業所を運営していることがわかります。訪問介護事業所を運営する法人の場合は、53.4%が通所系サービス事業所を運営しています。
さらに、双方の事業所はほとんど併設されていることも読み取れます。

介護事業者が通所系サービスと訪問系サービスを併設する利点
令和4年度老人保健健康増進等事業では、通所系サービスと訪問系サービスの両方に職員が勤務している法人に、そのメリットも尋ねています。
それによると、
- 双方の事業所の人材を有効活用できる
- 利用者の状態をより正確に把握できる
- 利用者と職員との信頼関係がしやすい
ことなどが挙げられています。
既存サービスとの違いが不明瞭・メリットがわかりにくい等の懸念も
新しい複合型サービスの類型ができれば、例えば、デイサービスの職員による訪問が特別な資格なしでも認められるなど、現状より柔軟な人員配置が認められる可能性が高く、事業者は効率的な運営ができるようになる可能性があります。
しかし、同分科会では以下の通り様々な立場の委員から懸念も表明されています。
- 小多機や看多機との棲み分けについて整理が必要。違いが分かりにくい(※𠮷森俊和委員/全国健康保険協会理事ら複数の委員が指摘)
- 複合型サービスは地域密着型サービスであり、受けられるサービスの地域格差が拡大することを懸念する。また包括報酬だったり、要介護者に限定されるサービスになれば、利用者が生活や身体の状況に合わせて選択できるものとは言い難い。
- 現行の小多機でも訪問が十分に提供されてない場合があったり、訪問介護のスキルが不十分な職員がいたりする事業所も多いとも聞く。ホームヘルパー不足の根本的な人材不足への対応すべき(鎌田松代委員/認知症の人と家族の会代表理事)
- 訪問系サービスと通所系サービスを併用するメリットが事業者間で情報連携をすれば解決できるもののように感じる。なぜこの新たなサービスが必要なのか、また、それによって制度がさらに複雑化する可能性が高い点について、て十分整理、検討する必要がある。(井上隆委員/経団連・専務理事)
- 同じ職員による一貫したサービス提供が「利用者の安心感に繋がる」というメリットが指摘されているが、今回示された調査研究の報告書には、”裏を返せば利用者の精神的な逃げ場をなくすことにもなりかねない”との指摘もある。また、サービスが過剰になるという懸念、訪問系サービスに従事する際と通所系とでサービス特性の違いによる意識の切り替えが難しいという意見も多い。
- 現場では訪問で働く人、通所で働く人それぞれ得手不得手を考慮しながらその職に就いている部分があると考えられる。また、連絡調整の煩雑さや、情報共有の難しさを乗り越えて対応していくには、見合った賃金処遇を保障する必要がある。(小林司委員/労連・総合政策推進局生活福祉局長)
いずれにせよ、8月末までの検討では、ケアマネジャーをどういった位置付けにするか、具体的な人員配置や報酬をどのように設定するかといった踏み込んだ検討には至っていません。
介護経営ドットコムでは、本テーマを巡って議論がどのように進んでいくのか注視してまいります。