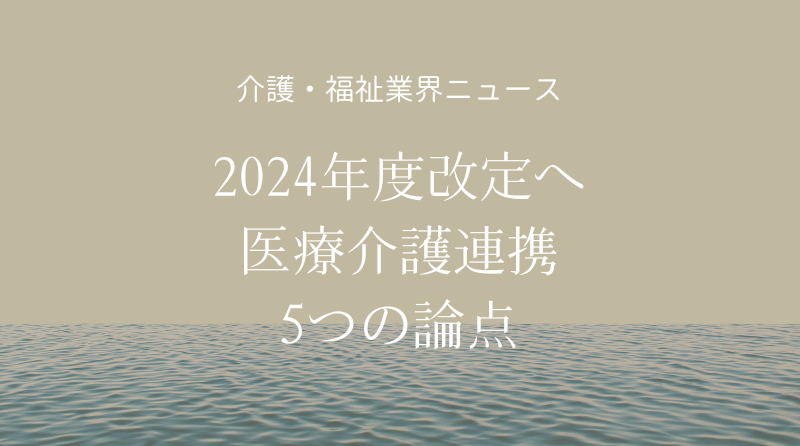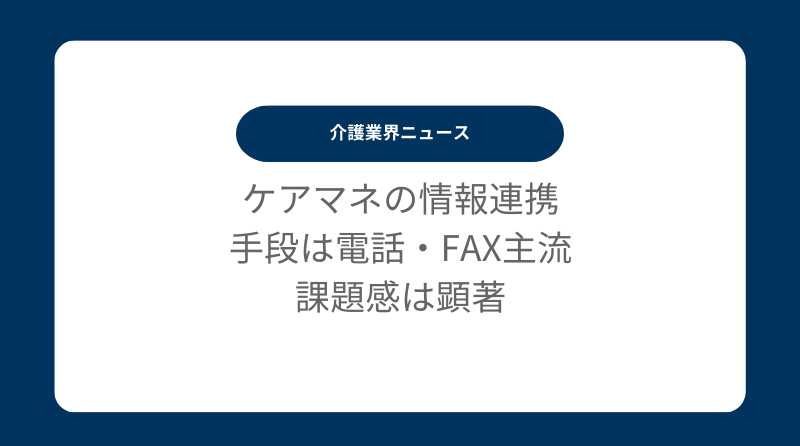2024年度は介護報酬・診療報酬同時改定のほか、介護保険事業(支援)計画や医療計画が新たにスタートするタイミングです。そこで現在は、医療と介護の連携を進めていくために両計画の整合性を取りつつ、必要なサービスを各地域で整備するための検討が進んでいます。厚生労働省は直近の会合で、今後の検討テーマを「⼈⼝構造の変化への対応」「デジタル化・データヘルスの推進」など5つに整理しています。
2024年度(令和6年度)医療介護同時改定に向けた論点とスケジュール
都道府県や市区町村は、24年度に合わせて新しい介護保険事業(支援)計画や医療計画を作成します。それに先立ち、国はこれらの方向性を示すための基本的な方向性をまとめます。
これに関連して現在、「医療介護総合確保促進会議」(以下、促進会議)では、介護保険事業(支援)計画や医療計画の方針のさらに上位概念に位置付けられている「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(以下、総合確保方針)の改正について話し合いが進められています=下の図表参照=。

【画像】2040年までの医療介護制度に関わるスケジュール案(7月29日開催の第16回医療介護総合確保推進会議資料より)
*関連記事:前回開催での検討内容はこちら
厚労省は7月の会合で、この総合確保方針の改定を巡る検討事項として、以下を新たに示しています。
- ⼈⼝構造の変化への対応
- 「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築
- 人材確保と働き方改革
- デジタル化・データヘルスの推進
- 地域共生社会づくり
2040年を見据えた医療・介護のサービス提供を巡る課題
厚労省がここで示した論点は、40年を見据えたサービス提供体制の整備を進める上で同省が課題として捉えている事項といえます。今後、これらを踏まえた第9期介護保険事業(支援)計画や第8次医療計画の策定が促されることになるでしょう。
各テーマをブレイクダウンして見ていきます。
⼈⼝構造の変化への対応
人口構造の変化については、特に、以下の要素が焦点となっています。
- 高齢者人口の増加は緩やかになる⼀⽅で、⽣産年齢⼈⼝の減少が加速する
- 85歳以上人口(要介護認定率や1⼈当たり介護給付費が急増する年代)が35年頃まで⼀貫して増加する
- 人口構成の変化や医療・介護需要の動向が地域ごとに異なる
「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築
こちらのテーマでは、急性期病床の削減や在宅医療の充実などを目指す医療提供体制の改革を指す「地域医療構想」の推進が中心的な論点となってます。そのほか、在宅高齢者へのケアの提供に関わりが深い切り口として、以下が示されました。
- 新興感染症などが発⽣した際にもサービスの提供体制を迅速かつ柔軟に切り替えることができるような体制の確保
- 介護サービスの基盤整備や住まいと生活の一体的な支援、医療と介護の連携強化、認知症施策の推進、介護予防の充実等を通じて、地域包括ケアシステムの深化・推進を図る
サービス提供⼈材の確保と働き⽅改⾰
こちらは、⽣産年齢⼈⼝が急減する中でいかに医療・介護サービスの質を確保するかというテーマです。医療領域の施策では、医療従事者の専門性の発揮や働き方改革を進めるため、職種のタスクシフト・シェア、時間外・休日労働の上限規制が進められています。
介護人材の確保については、介護報酬の加算等の創設による処遇改善のほか、
- 介護従事者について、これまでの処遇改善の取り組みに加え、現場の生産性向上の推進(ICTや介護ロボット、介護助手等の活用)や勤務環境の改善に取り組み、人材の確保を図っていく
ことが示されました。
デジタル化・データヘルスの推進
デジタル化・データヘルスの推進を巡って論点となったのは
- 患者・利⽤者の医療・介護情報をデジタル基盤を活⽤して医療機関・介護事業所等の間で共有・活⽤していくこと
- 医療・介護提供体制の確保に向けた施策の⽴案に当たり、NDB(ナショナルデータベース。レセプト情報と特定健診情報等のデータベース)や介護DB(介護レセプトと要介護認定情報のデータベース)等の公的データベースやこれらの連結解析等を通じて、ニーズ分析や将来⾒通し等を⾏っていくこと
の重要性です。
前者に関係する動きとして、マイナンバーカードの保険証利用や医療機関間での情報共有の基盤となるオンライン資格確認(医療保険の加入状況や自己負担限度額などを簡単にチェックできるシステム)の本格運用が21年10月に始まりました。
このネットワークの将来像として、予防接種の情報、電子処方箋情報、 検診情報のほか、医療・介護全般にわたる情報の共有や交換ができるプラットフォームの実現が掲げられています。
また、後者については現在、NDBや介護データベースといったビッグデータが医療計画や介護保険事業(支援)計画の策定や評価に活用されています。これをどのように発展させていくかが検討されました。
地域共生社会づくり
こちらは、医療や介護、福祉分野といった制度・分野ごとの縦割りを排し、地域住民などの多様な主体が参画して資源を有効に活用しようとする政策です。
孤独・孤立、生活困窮などの様々な問題を抱えた個人や家庭が、地域社会とつながりながら生活を送れるような姿を目指していくものです。医療・介護提供体制の確保についても、こうした文脈の中に位置づけていくことが重要視されています。
「地域密着型サービスの重点化を」介護業界団体からの要望
ここまで紹介した通り、同会議での検討テーマは幅広く、構成員の意見も多岐に渡りました。
介護領域の事業者団体や専門職団体の代表者からは、計画上の記載や都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金の使い道において、地域密着型サービスに重点を置くよう求める意見が複数挙がっています。以下が代表的な意見です。
民間介護事業推進委員会代表委員・山際淳構成員の意見
医療介護総合確保基金の使い道について、「小規模多機能であるとか、看護小規模多機能、あるいは定期巡回、こうした包括ケアで利用者を支えながら、比較的低額の財政支出で済むサービスの拡充を図っていく必要がある」。
また、これらのサービスは生活支援サービスを提供する拠点ともなり得ることから、(サービス整備上の)「位置づけを高める必要がある」。
日本社会事業大学専門職大学院教授・井上由起子構成員の意見
地域医療構想に基づくサービス提供体制の最適化を目指すような仕組みと同様の視点が、介護の在宅サービスでも必要ではないか。具体的には、定期巡回・随時対応型訪問介護や小規模多機能型居宅介護、看多機などの包括報酬で柔軟な運用のサービスが伸びていない。「これらのサービスを強化していく、あるいはそれに代わるケアマネジメントを含めた複合的な在宅サービスの在り方を考える必要があるのではないか」
日本看護協会・齋藤訓子構成員の意見
地域密着型のサービスをもう少し重点的にという意見に同意。
「市町村で介護保険事業計画等々を立てるときに、今後は在宅医療のニーズが増えてくるのだということをしっかりと認識していただいて、小規模多機能あるいは定期巡回、看護小規模多機能を整備計画の中でしっかりと位置づけていくことが大事ではないか」
このほか、介護関連の意見としては、地域医療介護総合確保基金を活用したICTやロボットの介護現場への導入支援について、実効性・柔軟性のある仕組みへの見直しを求めるものなどがありました。