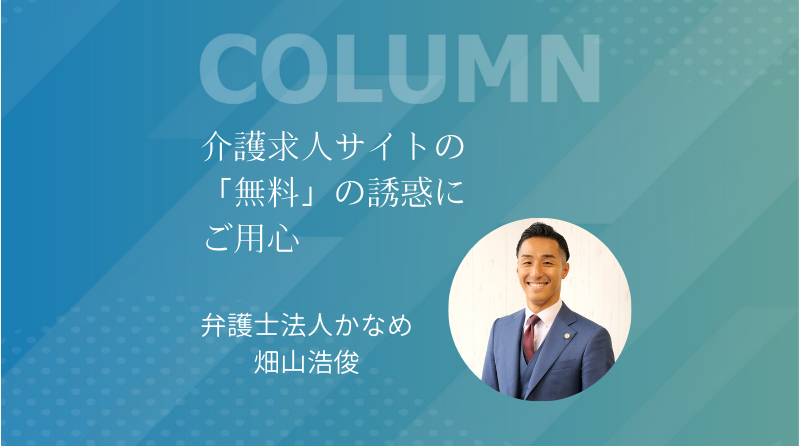1.進まない介護人材の確保が引き起こす問題
2025年問題、いわゆる「団塊の世代」の方々が全員後期高齢者となるまでの高齢者の急増とその後に起こる現役世代の急減によって、様々な問題が顕在化することが危惧されています。
中でも、介護現場を支える「人員の確保」の重要性が叫ばれており、厚生労働省は、第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について、2025年度には約243万人もの介護職員数が必要であると公表しています。
(厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02977.html)
介護現場における人材不足問題が深刻化する一方、人材不足問題解消の一手段として注目された外国人労働者も、長引くコロナ禍で思うように来日できておりません。
こんな中、介護事業者を専門的に支援している我々弁護士法人かなめでは、以下のようなトラブル事例の相談を受けることが多くなっています。
2.昨今増加している無料求人サイト運営会社とのトラブル事例
管理者A:もしもし、デイサービスかなめ(仮称)ですが。
求人サイト会社B:こちら求人サイト運営会社のBです。今、御社では介護人材不足に悩んでいませんか。
A:もちろん悩んでいますよ。求人を出しても全然応募もきませんし。人材紹介会社を経由して採用すると、とてもコストもかかりますし、困っています。
B:今なら良い方法がありますよ。2週間無料で求人サイトに求人情報を載せられます。無料ですから、一度試してみませんか。
A:えっ、無料ですか。それはとても有難いサービスですね。どのように申し込めば良いのでしょうか。
B:今からFAXで申込み用紙を送りますので、そちらで申し込んで頂ければ大丈夫ですよ。
A:分かりました。
・・・約1カ月経過
A:なんの請求書だろう。開封してみよう。
え!?20万円?無料って言ってたじゃないか!どういうことだ、Bに問合せてみよう。
B:無料の掲載期間が終了していますから、当然、有料契約に移行していますよ。きちんと支払って下さいね。
A:そんな、きちんとした説明も無かったじゃないか!こんなの詐欺じゃないか。
B:FAXの申込み用紙に、2週間経過後は自動的に有料になることが書いてありますよ。
A:そんな細かな部分をきちんと読んでないよ・・・。どうしよう・・・。
このようなトラブルに巻き込まれた介護事業所からの法律相談が増えています。
経営者が自らこのような求人サイトへの無料申込を行うケースも勿論ありますが、印象的なのは、会社としてではなく、会社が運営する一事業所の管理者が会社に事前の許可を取ること無く勝手に申し込んでしまうケースが目立つことです。
介護事業所は、いわゆる会社の本部とは物理的に離れている場合もあり、さらに、同一法人が運営する事業所であっても、それぞれの事業所ごとに固定電話番号が異なることから、求人サイトの運営会社から直接事業所に連絡があり、会社が関知できないことからケースのようなトラブルに発展してしまうことがあるのでしょう。
3.果たして契約は有効なのか?―管理者による申し込み時の注意点
さて、そもそも、このような求人サイト運営会社の手法で、契約は有効に成立しているのでしょうか。様々な個別事情により法的な判断は変わりますが、ここでは一般論の解説をします。
読者の皆様は、「2週間の無料掲載期間が終わったら有料の契約に自動的に更新されるなんておかしい。」「たとえFAX申込み用紙に有料自動更新の条項が入っていたとしても、字が小さすぎて見落としてしまう。」と違和感を覚える人が多いと思います。
読者の方の中には、このような場面を救済する法律として「消費者契約法」という法律を思い浮かべた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際、消費者契約法の中には、消費者にとって重要な事実を故意又は重過失によって告げなかった場合、契約を取り消すことができる旨の条項が存在します(消費者契約法第4条2項)。
しかしながら、消費者契約法が適用されるのは、あくまで「個人」の場合に限定されており(消費者契約法第2条参照)、今回のケースのような事業者対事業者の契約には適用されません。
そうすると、契約自由の原則に立ち戻ります。すなわち、契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができ、当事者間で結ばれた契約に対しては、国家は干渉せず、その内容は尊重しなければならない、というルールです。
よって、ケースのようなパターンであっても、FAX申込み用紙に2週間の経過後は有料になることが明記されている以上、その契約は原則として有効と考えて対処していく必要があります。
4.防止策の重要性:介護事業所内における周知徹底を急ごう
このような契約に対して、どのように争うかは事情によって千差万別です。
弁護士法人かなめでは、このようなトラブル事例に数多く対処していますが、公序良俗に反する契約であり無効であるとの民法90条に基づく主張、申込み者である一管理者に会社を代理して契約をする権限が無いという無権代理に基づく主張等々、法的には様々な対処法が考えられるところです。しかしながら、訴訟に発展するケースも実際にはあり、問題が起こる前に如何に事前に対処できるのかが重要になります。
筆者としては、ケースのようなトラブル事例が存在することを社内に予め周知徹底することで、安易に求人サイト運営会社の「無料掲載」の謳い文句に引っかからないようにすることが最も有効な防止策だと考えています。本記事を社内で周知する方法も一つの防止策ではないでしょうか。
5.困った時は自分で対処せず、弁護士へ相談しよう
ケースのような事例で、請求書が送られてきたことに動揺し、中には、求人サイト運営会社に言われるがままお金を支払ってしまうことがあります。
また、自分で反論を試みるものの、法律上契約は有効である、ということを前提に、求人サイト運営会社と折り合いがつかずに事態がより悪化する場合もあります。
このような事例に遭遇した介護事業所の方々は、決して一人で悩むことなく、速やかに弁護士に相談するようにして下さい。
※なお、本稿では求人サイト運営会社とのトラブル事例を紹介しておりますが、全ての求人サイト運営会社が悪質であるという訳ではありません。あくまで一部にそのような悪質な業者が見受けられるという指摘に留まるものである点を念のため付記させて頂きます。