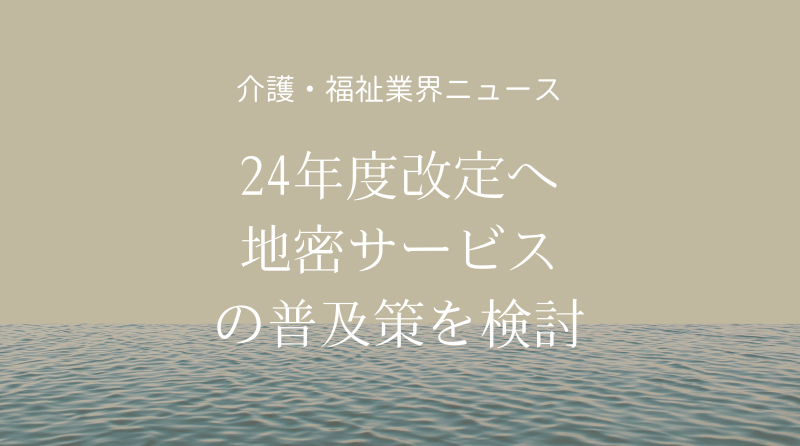社会保障審議会・介護給付費分科会は6月28日、具体的なサービス種別を挙げて2024年度介護報酬改定に向けた検討課題や論点の整理に入りました。
このうち、小規模多機能型居宅介護および認知症対応型共同生活介護を巡る検討状況について紹介します。
地域密着型サービスの”さらなる普及策”が議題に:社保審・介護給付費分科会
同日の分科会では、以下の5つのサービスが議題にあがりました。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
これらのサービスには、中重度の要介護状態の人が在宅生活を継続できるよう支援する役割が期待されています。厚生労働省は基本的にこれらのサービス供給量を増やしていく方針で、同分科会ではそのための施策などが検討されます。
もう一つ重要な論点は、人員確保の方策です。厚労省は、介護人材の効率的な活用方法についても意見を求めました。
小規模多機能型居宅介護:ケアマネ変更の壁に言及集まる
厚労省が小規模多機能型居宅介護を巡る現状整理として示したのが、管理者の兼務制限についてです。
小規模多機能型居宅介護支援事業所の現状の管理者が兼務可能な職務として認められているのは、併設されている地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設、認知症グループホームの管理者などです。
この兼務の範囲が限定されているため、「例えば同一敷地内の通所介護があったとしても管理者を兼務できない」ことに対し、見直しを求める声が挙がっていることを取り上げました。これに対し、ほかにも同一法人内の計画作成担当者などでも兼務を認めることを要望するなど、複数の委員から要件緩和を前向きに検討するよう求める意見がありました。
また、小規模多機能型居宅介護の利用開始には、それまで担当していたケアマネジャーから、小多機事業所に所属するケアマネジャーへ変更が必要である点も論点となりました。
厚労省は議論の土台として、担当ケアマネジャーが小多機の利用を紹介したものの利用開始に至らなかったケース320件のうち、「利用者が現在のサービスの事業所や担当者を変えたくなかった」(90件)、「利用者が現在のケアマネジャーを変えたくなかった」(52件)がその理由の上位であったとする調査結果を示しています。

(【画像】厚生労働省「第218回社会保障審議会介護給付費分科会 資料2」より
委員らからも「本事業は在宅介護の延長上の事業であり、これまでの担当ケアマネとの連携等により、利用者とケアマネとの関係性を維持できるような運用を可能とする仕組みを求める」などとした意見が挙げられています。
また日本介護支援専門員協会の濵田和則委員ら複数の委員が、それまでに担当していたケアマネジャーと小多機能に所属するケアマネジャーとの”選択性”の仕組みを提案しました。
認知症対応型共同生活介護:夜勤の人員基準弾力化が焦点に
認知症対応型共同生活介護については、医療ニーズへの対応強化と夜勤を中心とする人員配置の緩和が論点として示されています。
この日は、前回の21年度改定で実施された3ユニットの事業所に一定の要件化で導入された”2人夜勤”体制の効果について現場管理者の意見を紹介したうえで、今後の施策について意見を求めました。

(【画像】「第218回社会保障審議会介護給付費分科会 資料4」より
これに対し、全国健康保険協会の𠮷森俊和委員は「サービスの質の担保を前提に施設運営上の課題が無ければ、人材の有効活用の観点から、夜勤体制についても人員配置基準の緩和対策も検討に値するのではないか」と言及。さらに複数の委員が見守り機器やICTの活用を求める意見を提示しました。
これに対し、日本労働組合の小林司委員は「夜勤は休憩時間すら取れていない声も多い。利用者の安全面やケアの質という観点から、夜勤にしっかり人員配置できるようにしていくことが重要。夜勤の人員配置基準を安易に緩和してはならない」と提言。
認知症の人と家族の会の鎌田松代委員は「人材が不足しているから配置基準を緩める、という考え方にとても不安を感じている。拙速な緩和の実施はかえって現場の負担を増やす。介護労働者や事業者にどのような影響が出るのかをきちんと調査検証してからにしてほしい」と、人員配置要件に関して慎重な検討を求めました。
同分科会では24年4月の介護報酬改定に向け、他の各サービスについても論点の整理を進めます。次回開催予定は7月10日です。