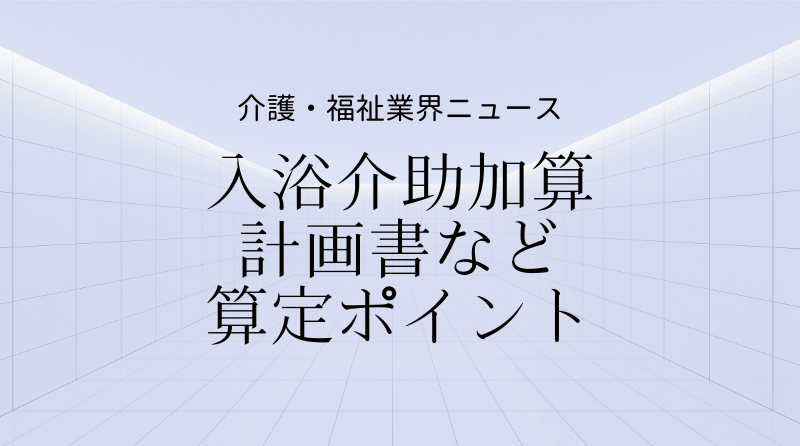令和3年度介護報酬改定で、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、個別の入浴計画に基づくサービスを評価する新区分が設けられました。一方、新区分の要件に満たない場合は実質減算となる単位数の変更もありました。新区分の算定について、計画書の作成など詳細のQ&Aが発出されています。入浴介助加算の算定に関わる情報をまとめて確認しておきましょう。
入浴介助加算とは?
入浴介助加算とは、入浴中の利用者の観察・介助を行う場合に算定する加算です。2021年度の介護報酬改定にて、利用者が自宅で入浴する際の自立を図る観点から、利用者の居宅での入浴を前提とした個別の入浴計画の作成と、計画に基づくサービス提供を評価する区分が新たに新設されました(入浴介助加算Ⅱ)。
一方で、改定前の入浴介助加算(50単位/日)と同様の算定基準のみを満たす場合は、入浴介助加算Ⅰ(40単位/日)に単位数が見直しとなり、改定前と比べて単位数が実質10単位減となってしまいます。
入浴介助加算の対象サービス・単位数
対象サービス
通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
通所介護等の単位数
入浴介助加算(Ⅰ):40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ):55単位/日
※加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可
通所リハの単位数
入浴介助加算(Ⅰ):40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ):60単位/日
※加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可
入浴介助加算加算(Ⅱ)の目的
利用者が居宅において、自身または家族や居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等の介助によって入浴ができるようになることを目的として、新設されました。
入浴介助加算の算定要件・留意事項
入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件等 (改定前の「入浴介助加算」と同様)
・入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものであり、入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行うこと。
・この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行う。結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となる。
・利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、シャワー浴や部分浴等である場合も、加算の対象に含まれる。
・利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。
入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件等
「入浴介助加算(Ⅰ)」の算定要件等に加えて、下記の要件を満たすこと。
①医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士(通所リハは除く)、介護支援専門員等(※1)が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価する(※2)。
②通所介護事業所の機能訓練指導員等(通所リハ事業所の場合は、事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等)が共同して、利用者の居宅を訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。
③ ②の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(※3)で、入浴介助を行う。
※1)利用者の居宅を訪問し浴室環境等を評価する者とは
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士(通所リハは除く)、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定されています。(Q&A vol.8問2より)
上記に該当する者は、利用者の状態に応じ、「自身または家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるか」を念頭に置いた上で、算定要件の①~③を実施することが求められます。
※2)浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価した結果
利用者自身でまたは家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、サービス提供事業所に対して情報を共有します。(評価可能な専門職が事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意する)
利用者の居宅の浴室が、利用者自身または家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると判断した場合は、訪問した評価可能な専門職が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行います。
※3)「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは
手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し、利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えありません。
例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、いわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えありません。(Q&A vol.8問5より)
Vol.974 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.8(令和3年4月26日)」の送付について
入浴介助加算Ⅱの計画書の作成について
「個別の入浴計画に相当する内容を通所介護・通所リハ計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする」
このように解釈通知が発出されています。加算Ⅱの算定要件のひとつである「入浴に関する個別計画書」の作成については、通所介護計画・通所リハ計画の中にまとめて記載することができます。
参考資料:留意事項通知(PDF)
入浴計画書の項目とは
計画書に載せるべき項目や、評価の頻度については現時点で明記されておらす、各事業所ごとに定める必要があります。
仮に通所介護・通所リハ計画に、入浴に関する個別計画の評価をまとめる場合、「各計画に合わせて評価期間を設定することが望ましい」と明記している自治体もあります。事業所の所属する自治体のQ&Aが発出されていないか、確認しておきましょう。
参考資料:令和3年度介護報酬改定におけるQ&A(vol.3) 旭川市(PDF)
入浴計画書等の評価頻度
個別の入浴計画の見直しや、利用者の居宅を訪問して浴室における利用者の動作や浴室環境を評価することについては、当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に、再評価や個別の入浴計画の見直しを行う必要があります。(Q&A vol.8問3より)
利用者の「居宅」と想定される場所とは?
入浴介助加算Ⅱの算定要件である、利用者の「居宅」として想定される場所は、「利用者の自宅」のほか、利用者の親族の自宅が想定されます。
「利用者の自宅」には、高齢者住宅(居室内の浴室のほか、共同の浴室を使用する場合を含む)も該当します。
自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者については、以下①~⑤をすべて満たすことで、当面の目標として通所介護・通所リハ等での入浴の自立を図ることを目的に、加算Ⅱを算定できます。(Q&A vol.8問1より)
① 事業所の浴室において、利用者の動作や浴室環境を評価できる専門職(※)が、利用者の動作を評価する。
② 事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。
③事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や、事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。
④ 個別の入浴計画に基づき、各事業所において、入浴介助を行う。
⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護・通所リハ等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。
※①の専門職
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士(通所リハは除く)、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定されている。
「自立を図る入浴介助」の具体的な方法とは?
入浴介助加算Ⅱの算定要件である、「個別の入浴計画に基づき個浴など利用者の居宅に近い環境で入浴介助を行うこと」について、具体的にどのような介助が想定されるのでしょうか。
厚労省は下記の内容を示しています。(Q&A vol.8問4より)
・入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助を行う。
・一方、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。
利用者の状態に応じた身体介助の例
座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合
| 利用者の動作 | 介助者の動作 |
| - | シャワーチェア(座面の高さが浴槽の高さと同等のもの)、浴槽用手すり、浴槽内いすを準備する |
| シャワーチェアに座る | - |
| シャワーチェアから腰を浮かせ、浴槽の縁 に腰掛ける | 利用者の足や手の動作の声かけをする。必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える |
| 足を浴槽に入れる | 利用者の体を支え、足を片方ずつ 浴槽に入れる動作の声かけをする。必要に応じて、利用者の上半身を支えたり、浴槽に足をいれるための持ち上げ動作を支える |
| ゆっくり腰を落とし、浴槽内いすに腰掛け て、湯船につかる | 声かけをし、必要に応じて、利用者の上半身を支える |
| 浴槽用手すりにつかまって立つ | 必要に応じて、利用者の上半身を支える |
| 浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりをつか み、足を浴槽から出す | 必要に応じて、浴槽台を利用し、利用者の上半身を支えたり、浴槽に足を入れるための持ち上げ動作を支える |
| 浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワーチェア に腰掛ける | 必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える |
| シャワーチェアから立ち上がる | - |
※上記は一例であり、算定に当たって必ず実施しなければならないものではありません
入浴介助加算Ⅰ・Ⅱの利用者が混在する場合の算定方法
同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する利用者と、入浴介助加算(Ⅱ)を算定する利用者が混在することは問題ありません。
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」 等に記載する際には、混在している場合でも、「加算Ⅱ」と記載します。
「加算Ⅱ」と記載した場合であっても、入浴介助加算(Ⅰ)を算定することは可能です。(Q&A vol.8問6より)