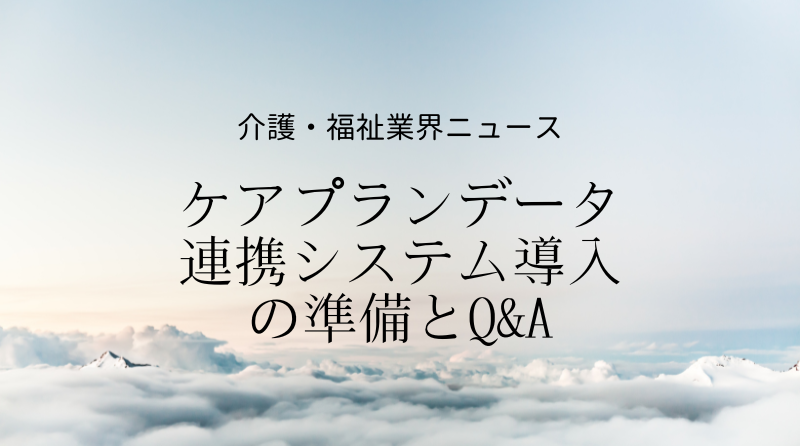厚生労働省からシステム概要が公表されて以降、「ケアプランデータ連携システム」への関心が高まっています。現段階で明らかになっている情報をもとに、事業所で必要な準備やよくある質問・疑問に対する回答をまとめました。
ケアプランデータ連携システムでできること
ケアプランデータ連携システムは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所間のケアプランに記載した情報のやりとりをオンラインで完結させるための情報連携基盤です。現在、厚労省主導のもとで国民健康保険中央会がシステム開発を進めています。
具体的に送受信できるデータは、居宅サービス計画書(1)(2)・サービス利用票(提供票)、サービス利用票(提供票)別表(ケアプランの第1表、第2表、第6表、第7表)になる予定です。
今後のスケジュールは、2023年2月からパイロット運用がスタートし、同年4月から本稼働となっています。そのほかシステムのイメージや年間の利用料金・コスト削減効果の試算などが既に厚労省の通達で示されています。

(*厚労省の通達の内容はこちらでより詳しく紹介しています。)
介護ソフトによっては、同様の機能を既に備えているものもあります。しかし、異なる介護ソフトを導入している事業所間のやり取りについては、データ形式の統一などが進められてきたものの、そのデータ形式の細かい部分や介護ソフトの操作性に違いがあります。そのため、実態として現場の負担軽減には結びついていなかったようです。
ケアプランデータ連携システムの構築は、こうした現状を打開し、現場の業務効率化・ICT化を加速しようとする政策です。
ケアプランデータ連携システムを導入するにあたっての準備
ケアプランデータ連携システムをご自身の事業所で導入する際、必要な準備や対応は以下の通りです。
①パソコン(Windows10以降)
②厚生労働省のケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフト ※1
③介護給付費請求に使用する電子証明書の発行 ※2
④ケアプランデータ連携クライアント(システム)のインストール
※1
介護ソフトによって該当/非該当があります。
自社でご利用中の介護ソフトが対象になるかどうかはソフト提供会社に直接お問い合わせください。
※2
国保連のソフト以外で請求(伝送)を行っている場合は、基本的に電子証明書の発行が必要になると推察されます。なお、ケアプランデータ連携システムのみで電子証明書を利用する場合は発行手数料が無料になる予定です。
ケアプランデータ連携システムを導入するにあたっての注意事項
ケアプランデータ連携システムの導入にあたり、以下のような注意事項があります
双方の事業所が導入していないと使えない
ケアプランデータ連携システムをつかう条件として、送信/受信する双方の事業所でケアプランデータ連携システムを導入している必要があります。そのため、使用前に相手の事業所がシステムを導入済みか確認が必要です。
請求は介護ソフト(伝送ソフト)から行う
ケアプランデータ連携システムから請求を行うわけではなく、最終的にはご利用中の介護ソフト(もしくは伝送ソフト)から請求を行うことになります。
あくまでもケアプランデータ連携システムは、「情報連携」するためのシステムであって、請求システムではないことをご認識ください。
各介護ソフトの対応状況の確認が必要
介護ソフトによって同システムへの対応方針や状況が異なってくると考えられます。
リリース(23年4月)に合わせて対応するソフトもあれば、周囲の導入状況等を確認しながら時期を見定めるソフトも出てくるかもしれません。もしくは、提供票(別表)のみなど一部対応する可能性もあります。
ケアプランデータ連携システムの導入を検討される際は、ご利用中の介護ソフトがどのような方針なのかをご確認ください。
ケアプランデータ連携システムに関するQ&A
ケアプランデータ連携システムについて、国民健康保険中央会がよくある問い合わせと回答をまとめています。主なものを以下に抜粋します。
| 質問 | 回答 |
| ケアプランデータ連携のシステムの仕様に関する質問 | |
| ケアプランの標準様式以外のデータ(入院時・退院時情報等)の送信は可能なのか。 | 標準様式以外の情報は、PDF等で出力したものを添付ファイルとして送信可能。 |
| 受信一覧画面で、送信元の事業所名を表示できないか。 | どの事業所から送付されたケアプランデータであるかが分かるよう、事業所名を表示する予定。 |
| 本システムを導入することで転記不要になるのは、どの部分なのか。 | 現在FAXで送られてきているケアプランを介護ソフトに手入力しているところを、本システムと介護ソフトを組み合わせて運用することで、手入力が不要になる。
※サービス事業所側は、ケアマネ事業所から送られてきたケアプラン(予定)を、居宅介護支援事業所側はサービス事業所から送られてきたケアプラン(実績)を介護ソフトに入れる部分。 |
| メールで添付するのと何が違うのか。 | 要配慮個人情報であるケアプランデータをやり取りするにあたり、強固なセキュリティ対策を講じた本システムを利用することで安心安全に送信することが可能になる。業務に関係の無いメール等が混在する心配もないため管理が容易となる。 |
| 送信したケアプランデータを蓄積し、将来的に利活用する想定はあるか。 | 本システムはデータを蓄積しない仕様であり、サーバに集まったデータは、一定期間経過後に削除される。 将来的なデータの蓄積については今後厚労省において検討される想定。 |
| 送信したケアプランデータが受信側に届いたことを送信側が認識することは可能か。 | 受信側が事業所のPCにデータをダウンロードしたことを、送信側の送信一覧画面上で認識することが可能となる。 |
| 事業所が用意するケアプランデータ連携システムクライアントは、既存の介護ソフトがインストールされているクライアントPCと共用はできないのか。 | ケアプランデータ連携クライアントをインストールするクライアントPCは、動作環境の条件が双方のソフト共に満たされていることを前提に、使用中の介護ソフトがインストールされているクライアントPCを使うことを想定している。 |
| 費用に関する質問 | |
| ライセンス料をどのように徴収するのか。 | 以下の2通りによる徴収方法を想定。ただし、利用者と提供側双方の事務負担軽減の観点から、①を基本と想定している。
①介護給付費からの差引 ②請求書送付による口座振り込み |
| ライセンス料が徴収される時期は。 | 2023年4月の本稼働直後から利用する場合、2023年4月の請求(5月支払分)からの徴収を予定。 |
| 新規開設事業者は、「年額「2万1,000円」のライセンス料と、3年ごと「1万3,200円」の電子証明書発行手数料の両方が費用としてかかる」という認識で間違いないか。
また、すでに1万3,200円支払済みで有効期間内の介護保険伝送請求を行っている事業所の、費用の内訳と金額は。 |
新規開設事業所については、質問の通り。すでに介護保険伝送請求を行っている事業所(有効な電子証明書を持つ事業所)は、ライセンス料の年額2万1,000 円のみの費用となる。 |
| ケアプランデータ連携システム用の電子証明書発行は、「(1)既存の介護保険電子証明書と同じ(1万3,200円、有効期間3年)」「(2)既存の介護保険電子証明書より安価な証明書 を新設」のいずれになるのか。 | (2)既存の介護保険電子証明書より安価な証明書を新設(料金は無料)となる。
なお電子請求受付システムを利用するために既に発行済みの介護保険電子証明書(1万3,200 円、有効期間3年)がある場合、その電子証明書をそのまま利用し、(2)の電子証明書の発行をする必要はない。 |
| 利用料金の1事業所単位の考え方は。 | 1事業所番号あたり2万1,000円が必要。複数事業所を運営している場合も同様。 |