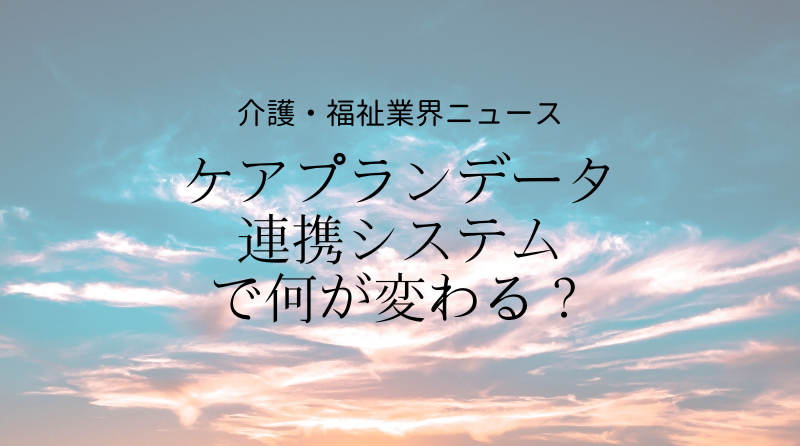厚生労働省が9月6日付けの事務連絡で概要を公表した「ケアプランデータ連携システム」。居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やりとりをする居宅サービス計画書、サービス利用票(予定・実績)などについて、データの送受信を可能にするためのプラットフォームのことで、国民健康保険中央会が構築を進めています。
こちらの記事では、今後開発が進められる「ケアプランデータ連携システム」について、現段階で明らかになっている情報を整理しました。
ケアプランデータ連携の状況とシステム開発までの経緯
厚労省はこれまでにも、介護現場の負担軽減や職場環境の改善のための取り組みの一環として、居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携を推進しようとしてきました。
具体的には、これまでに、異なるベンダーの介護ソフトを使用している介護事業所間でも情報連携を行うことができるよう、データ形式やフォーマットを統一するための標準仕様を公開しています。これは、ケアプランや提供票などのデータをCSVファイル形式で出力したり取り込んだりできるようにすることで、業務の効率化や入力作業の正確性向上を図るための取り組みで、標準仕様に対応した介護ソフトの導入は、地域医療介護総合確保基金におけるICT導入支援事業(補助金)の対象にもなっています。
しかし、実情としては介護ソフトが異なるとデータ形式の細かい部分や操作性などに違いがあり、情報連携をオンラインで完結しようとすると新たに煩雑な作業やリスクが発生するといった課題が残っているため、浸透していません。今回概要が公表された「ケアプランデータ連携システム」によって、こうした状況の打開が期待されるところです。
なお、8月30日付の事務連絡では、今後「ケアプランデータ連携システム」などでの活用を見据えて、標準仕様の改訂版が発表されています。

(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1095より引用)
厚労省が公表したケアプランデータ連携システムの概要
システムの全体像
「ケアプランデータ連携システム」とはどのような仕組みなのでしょうか。今回の発表によると、これは主に居宅介護支援事業所や介護サービス事業所に導入する「データ連携クライアント」 と、運用センターが設置される「データ連携基盤」とで構成されることになっています。
国保中央会のWEBサイトからインストールした「データ連携クライアント」を通じて、ケアプランなどのファイル送受信が可能になるのですが、その時にクラウド上の「データ連携基盤」が介されることになっています。
 (厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1096より引用)
(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1096より引用)
費用効果は試算上年間81万6,000円の削減
ところで、厚労省はケアプランデータ連携システムの概要の周知に当たり、導入事業所における費用効果を強調しています。
具体的には以下の費用削減効果を試算しています。
- 人件費削減を考慮した場合・・・年間約81万6,000円の削減
- 人件費削減を考慮しない場合・・・年間約7万2,000円の削減
これらは、従来のやり取りでかかっている印刷費、郵送費、交通費、通信費(FAX)の削減によって見込まれる金額です。
事前準備
今回の発表では、事業所の業務フローの概要も説明されています。
まず、ケアプランデータ連携システムを通じてデータを送受信する場合の前提として、送る側と受け取る側の双方がケアプランデータ連携システムを利用している必要があります。その際の事前準備として、以下の手順が示されています。
(1)介護事業所の利用者は、ケアプランデータ連携システムのWEBサイトから利用申請
(2)介護事業所の利用者は、「ケアプランデータ連携クライアント」ソフトを国保中央会のWEBサイトよりダウンロードし、介護事業所のパソコンにインストール
(3)ケアプランデータを送信するためには、電子証明書が必要
電子証明書を既に持っている場合は、電子証明書の発行申請とダウンロードは不要です。電子証明書を持っていない場合は、電子請求受付システムのWEBサイトにアクセスし、電子証明書の発行申請とダウンロードを行う必要があります。

(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1096より引用)
システムの使い方(業務フロー)
次に、システムの使い方について見ていきます。
まず居宅介護支援事業所が以下の作業を行います。
(1)介護ソフトでケアプランデータ予定ファイルを作成、CSVファイルとして出力(保存)
(2)出力したケアプランデータ予定ファイルをデータ連携クライアントにアップロード
(3)ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ連携基盤へ送信(電子証明書は自動付与)

(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1096より引用)
続いて介護サービス事業所が以下の作業を行います。
(4)ケアプランデータ連携クライアントを操作し、最新情報を確認し、ケアプランデータ連携基盤から受信(通信は暗号化される)
(5)ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ予定ファイルをダウンロード(6)ダウンロードしたケアプランデータ予定ファイルを介護ソフトに取り込み確認
(7)介護ソフトにケアプランに基づく実績を入力後、ケアプランデータ実績ファイルをCSVファイルとして出力(保存)
(8)出力したケアプランデータ実績ファイルをケアプランデータ連携クライアントにアップロード
(9)ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ連携基盤へ送信(電子証明書は自動付与)

(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1096より引用)
最後に居宅介護支援事業所が以下の作業を行います。
(10)ケアプランデータ連携クライアントを操作し、最新情報を確認し、ケアプランデータ連携基盤から受信(通信は暗号化される)
(11)ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ実績ファイルをダウンロード
(12)ダウンロードしたケアプランデータ実績ファイルを介護ソフトに取り込み確認
介護事業所が負担する費用
ケアプランデータ連携システムの利用料や負担の仕組みは未公表で、国民健康保険中央会は「事業所の過度な負担にならないように検討を進めていく」としています。
ケアプラン連携システムに関わる今後のスケジュール
ケアプラン連携システムにかかわる今後のスケジュールですが、本稼働の予定は2023年4月から開始となっています。
また、2023年2月中旬から自治体を限定し、パイロット運用も行われます。パイロット運用に参加する事業所や自治体の選定は2022年9月末までに行われ、12月末までに参加事業所や自治体との交渉、調整がなされます。
システムの利用料や負担の仕組みがどのようなものになるのか、また、実際にデータ連携をする際の手間はどのくらいかかるのかなど、システムの導入にはまだ不安感もあるかもしれません。ケアプラン連携システムについては、介護経営ドットコムで引き続き情報を収集し、お伝えしていきます。