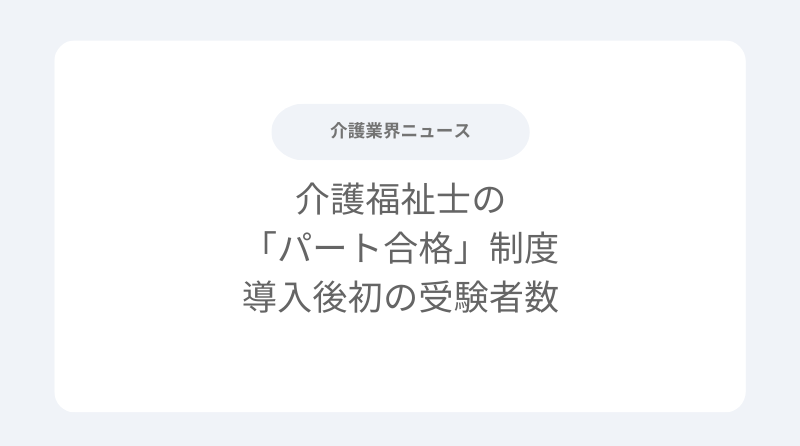介護業界では、後継者不足などを背景に、M&A(合併・買収)が活発になっています。
しかし、M&Aの需要増加に伴い、「買収後に代金が支払われなかった」「聞いていなかった負債があった」といった悪質なトラブルも増えているのが実情です。
この記事では、近年の介護施設や事業所のM&Aにおける悪質なトラブルの事例とトラブルを避けるためのポイントについてご紹介します。
1.介護施設・事業所のM&Aの動向~需要は増加傾向
国内の中小企業によるM&Aの実施割合と件数
近年、経営者の高齢化や後継者の不在を背景として、国内の中小企業によるM&Aの実施割合や件数は増加傾向にあります。


(【画像】中小企業庁「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について」より)
介護業界の倒産件数とM&Aのニーズ
東京商工リサーチの調査結果によると、利用者獲得競争の激化やコロナ禍によるダメージ、人手不足、介護用品の高騰などが重なったことを背景として2024年度の介護事業者の倒産件数は過去最大を記録しました。

(【画像】東京商工リサーチTSRデータインサイトより)
経営環境が厳しくなっていることを受け、会社や事業を売却をしようとする動きも活発になっています。象徴的な例として、M&Aマッチングサイト上などで、売却を希望する介護事業者が「譲渡金額1円」で買い手を募っている案件も確認できます。
一方で、高齢化の深化に伴う市場の拡大を商機とみる新規参入者が数多く存在していることから買収側のニーズも高い状況となっています。
特に、異業種からの参入の場合、介護事業の運営のノウハウや人材を獲得する手段としてM&Aが有力な選択肢となっています。
2.介護施設・事業所のM&Aで増える悪質なトラブルの事例
M&Aの需要が事業存続や経営の安定化のための一手として拡大する一方、残念ながら悪質トラブルも発生しています。
その代表的な事例を紹介します。
クロージング後に個人保証が解除されなかった事例
クロージング後、売手経営者の個人保証について、売手から買手に何度依頼しても契約に基づいた移行がなされなかった。 その上で、買手が売手の現預金等の資産を回収したが、必要な事業資金の送金がなされず、売手は倒産。この結果、経営者保証が残っていた売手経営者が債務を負うこととなり、個人破産に至ってしまった。 (※引用:中小企業庁ウェブサイトより)
通常、売り手側の経営者の「個人保証」(会社の融資に対し、経営者個人が返済責任を負う仕組み)は、買収に伴って買い手へ移行するか、保証解除する契約を交わします。
しかし、この事例では、売り手側が契約に基づく個人保証の依頼をしたにもかかわらず、買い手側の個人保証の移行が実施されなかったようです。
譲渡対価の分割払い・退職慰労金の後払いが履行されなかった事例
M&Aの成立時点での譲渡対価は低額であったが、成立後一定期間後に相当程度の退職慰労金が支払われる契約を結んだ。 しかし、契約に定める期日が訪れても退職慰労金が一向に支払われない。 (※引用:中小企業庁ウェブサイトより)
株式譲渡契約では、「譲渡対価(売却代金)」の支払い方法や時期を定めます。
この事例では、契約通りに支払いが行われなかったことになります。
M&Aによる経営者交代後に前オーナーの使い込みが発覚した事例
首都圏を中心に37カ所の有料老人ホームを経営していた(株)未来設計(TSR企業コード:294993290、東京都中央区、洞寛二社長)が1月22日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。 負債総額は有料老人ホームの運営会社としては53億8,600万円の大型倒産となった。 負債には利用者が入居時の預り金なども含まれる。その預り金などを失った個人債権者は1,500名、総額は約34億円にのぼる。 未来設計は、2002年の施設開設以来、介護市場の拡大を背景に成長を遂げてきた。 だが、M&Aによる経営者の交代をきっかけに前オーナーが法外な報酬を得ていたことや粉飾決算の疑惑が発覚。入居者やその家族など多くの人を巻き込み、波紋は広がっている。
(※引用:東京商工リサーチデータインサイトより)
こちらは、持株会社の株式を買い取り経営権を取得した後に粉飾決算が発覚し、恒常的に赤字が発生していることや、運転資金がショートする恐れがあることが発覚した事例になります。
3.介護施設・事業所のM&Aで起こるトラブルの原因
ここでは、介護施設・事業所のM&Aで起こるトラブルの主な3つの原因を解説します。
①情報漏洩による信頼の棄損
会社の譲渡や売却を検討しているという情報が伝わることで不安や不信感が煽られ、従業員の退職や取引先との契約打ち切りに繋がる可能性があります。
また、売り手側の情報管理の不備は、買い手側の不信感を呼び、交渉が決裂してしまう可能性もあります。
②簿外債務の隠ぺい
中小企業のM&Aにありがちなのが、貸借対照表にない未払いの給与や残業代(簿外債務)の隠蔽に起因するトラブルです。
売り手側は、簿外債務など自社に不利な情報を開示しないケースもあります。
株式譲渡の場合は、買い手側が簿外債務を引き継ぐことになり、発覚した場合は買い手側の事業所・施設の経営に影響する可能性もあります。
③仲介事業者の専門性不足
介護業界におけるM&Aでは、仲介事業者の専門性が不足している場合、トラブルの一因となることがあります。
介護報酬や人員配置基準、運営基準など、介護事業に特有のルールを十分に理解していない仲介事業者が介入すると、重要なリスクを見落とす恐れがあります。
例えば、加算の算定条件や人員要件を把握しないまま譲渡が進むと、買収後に報酬の返戻となったり、行政指導を受けたりするケースがあります。
業界知識を欠く仲介事業者が関わることで、買収後の経営リスクや信用低下につながる可能性があります。
4.介護施設・事業所のM&Aで悪質な事例・トラブルを避けるには?
トラブルの主な原因を踏まえ、円滑なM&Aを実施するためのポイントを紹介します。
①情報機密を厳守する
情報漏洩を防ぐ手立てとして、機密保持契約を締結します。
また、関係者への適切な説明を行い、全員が機密保持の重要性を理解することで情報漏洩のリスクを減らすことができます。
②デューデリジェンスを怠らない
簿外債務などのリスクを低減するためには、適切なデューデリジェンスを実施することが必要です。
デューデリジェンスとは、売り手企業の企業価値や経営リスクを把握するための事前調査を指します。
介護事業のM&Aでは、隠ぺいしている未払残業代、未払社会保険料、買掛金、リース債務、債務保証などの簿外債務、あるいは介護報酬の不正請求など専門的な確認が必要な項目があり、デューデリジェンスを怠ると、買い手側の事業所・施設の経営に深刻な影響が発生する可能性もあります。
そのため、適切なデューデリジェンスを実施し、売り手・買い手の双方が正確で客観的な情報をもとにM&Aの契約を進めることがトラブルの予防に繋がっています。
③信頼できる仲介業者を選択する
トラブルを避け、M&Aによる目的を達成するには、信頼できる仲介事業者を選ぶことが重要です。
以下のポイントを確認しておくと安心です。
M&A支援機関登録制度に登録している事業者であること
「M&A支援機関登録制度」は悪質な仲介事業者を排除し、透明性を高めるために、中小企業庁が2021年に創設した制度です。
登録事業者は「中小M&Aガイドライン」に基づく行動指針の遵守を宣言しており、企業をデータベース化したもので、事業者ごとの手数料の体系などを確認できます。
なお、ガイドラインには、トラブル事例でも挙げた経営者保証の解除や買い手への移行を確実に行うための対応についても明記されています。
仲介手数料の透明性があること
仲介事業者とのトラブルを避けるためには、仲介手数料の料金体系もチェックしましょう。
「完全成功報酬制」を採用している仲介会社であれば、M&Aが成立しなかった場合の費用が不要で、事前にコストを把握できます。
介護業界に特化した仲介事業者であること
介護事業のM&Aには、行政手続き・報酬請求・人員基準など、他業種とは異なる専門知識が求められます。
介護業界に精通した仲介事業者であれば、制度や現場の実情を踏まえた的確な査定とマッチングが可能です。
介護業界で確立したネットワークがあること
既存の介護事業者とのネットワークを持つ仲介会社であれば、買い手のニーズを詳しく情報収集しているため、信頼できる相手とのマッチングが実現しやすくなります。
5.まとめ
介護事業のM&Aでは、悪質なトラブルも発生する可能性があります。
機密情報の保持やデューデリジェンスの徹底、そして信頼できる仲介事業者の選定がトラブル回避の鍵となります。
特に、介護事業のM&Aの場合、強いネットワークと専門知識を持つ仲介事業者を選ぶことが、安心・安全の要といえるでしょう。
そこで弊社が提供しているカイポケM&Aサービスでは、豊富な介護・福祉・医療のネットワークを利用して、最適なパートナーとの事業承継・M&Aをサポートしています。
下のバナーからお気軽にお問い合わせください。
介護のM&Aに関連するそのほかの記事
*介護事業所の売却を検討するタイミングと事業譲渡・事業売却の流れ