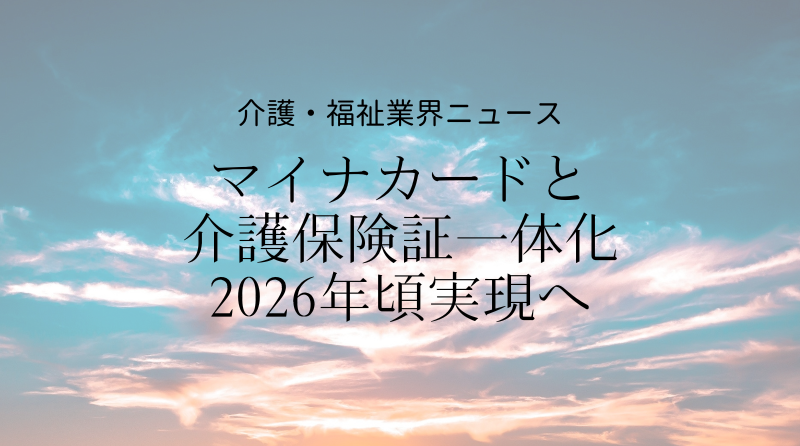介護保険の被保険者証(以降、介護保険証)のマイナンバーカードとの一体化と保険証に記載されたデータの電子化について検討がはじまっています。これが実現すれば、介護現場の実務はどのように変化していくのでしょうか?直近の検討状況やスケジュールについて整理しました。
介護保険証のデータが紙から電子へ移行。何が変わる?
2月末の社会保障審議会・介護保険部会では、マイナンバーカードを活用した介護保険証の電子化が議題になりました。医療保険については、来年秋に健康保険証を廃止し、「マイナ保険証」に一体化する方針がすでに政府から示されています。介護保険証もこれに一体化されることになりますが、紙の保険証の廃止は今のところ想定されていません。
介護保険の保険者証は現状、被保険者が65歳に到達した時に保険者から一斉送付されます。要介護認定申請等の際には保険者に保険証を提出、必要情報(要介護度や自己負担の割合など)が記載されて返付されます。被保険者が要介護認定を受けた後は、ケアプランの作成を初めとしたケアマネジャーとの連携やサービスを利用するために介護事業所などへ提示するなど、紙の保険証は多くのシーンでやり取りされています(※以下のイメージの青い矢印部分)。

(画像引用:第106回社保審介護保険部会「介護保険被保険者証について(資料2)」)
さて、一方で国策として推進されている介護DXやデータ活用という文脈としては、自治体・利用者・介護事業者・医療機関などが利用者(被保険者)に関する介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤の整備が進められています(「全国医療情報プラットフォーム」構想)。

(画像引用:第106回社保審介護保険部会「介護保険被保険者証について(資料2)」)
厚生労働省はこの日、このプラットフォームとマイナンバーカードと一体化した介護保険証の将来的な活用イメージを示しています。これは、行政と居宅介護支援事業所や介護事業所との間で紙の保険証をやり取りしなくても、マイナンバーカードを読み取り用の端末などにかざして情報連携ができれば、業務効率化につながるというものです。

本格運用は26年度からの見通し 実現に向け調査研究開始へ
厚労省の提案に対し、委員からの異論はありませんでした。
厚労省はまず、介護情報等の電子的な共有の仕組みやマイナンバーカードと介護保険証の一体化に伴う業務フローの見直しの必要性、導入のメリットデメリットなどを把握するための調査研究を実施します。
カードと介護保険証の一体化について、具体的な運用開始スケジュールは調査研究の結果を経てからになりますが、2026年度から全国の自治体で本格的な運用を始めることを目指しています。