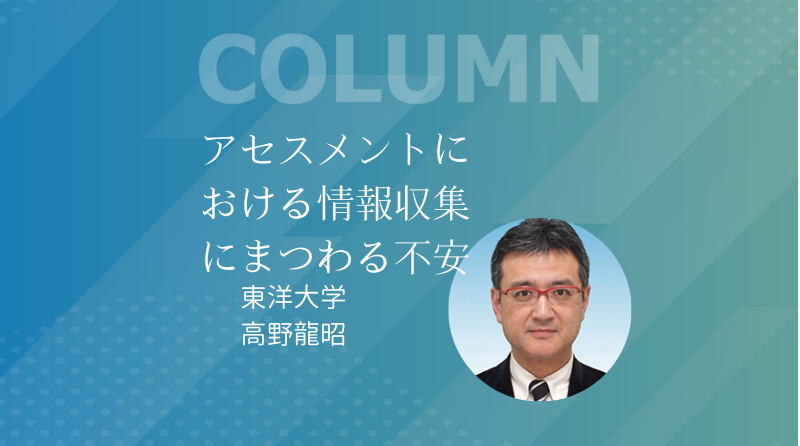このコラム(連載)は、高齢者社会ラボによる『介護の質の評価に関する調査』(アセスメント編、ケアプラン~モニタリング編・以下「本調査」)の結果から、私が「気になるポイント」を示しながら、介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」)のみなさんの実務に役立つ論考を行うものです。当初から、実践現場のケアマネジャーには少し「耳の痛い」話もお示ししています
*第1回:ケアマネジャーの「孤立」、第2回:「医療・介護連携」に悩むケアマネジャー
今回(第3回目)と次回は、ケアマネジャーの中核的な業務と言ってもよい「アセスメント」について、その「情報収集」の課題について触れてみます。
アセスメントとは何か…「情報収集」と「分析」の過程に分けて捉える
日頃から私は、“ケアマネジメントにおける「アセスメント」は、①「情報収集」と②「分析」から成り立つ”と説明しています。この構造を図1に示します。
(【図1】)

簡潔に説明を加えれば、利用者の生活の全体像について、多様な手段を用いてさまざまな角度から「情報収集」を行い、それをもとに、生活上の問題に関して「分析」を行って、ケアプランに示す課題(ニーズ)などを明らかにすることと言えます。
つまり、本稿で焦点をあてる「情報収集」は、アセスメントの入口にあたる重要な過程と言えるわけです(「分析」については次回以降に触れます)。
兼ねてから「ケアマネジャーはアセスメントが不十分」だと指摘され、ケアマネジャー自身も「アセスメントが苦手」と語ることが多くあります。ケアマネジャーがそれを克服しようとする際には、「情報収集」と「分析」、そして「ケアプラン(原案)作成」にアセスメントの過程を分割してスキルアップの方策や対応策などを検討する必要があるでしょう。
アセスメントの際の情報収集がケアマネジャーにとって「苦手」な分野
先述の調査で私が気になったポイントのひとつに、「アセスメント時の情報収集」に関する結果があります。この調査では、ケアマネジャーにアセスメントの各項目についてどの程度情報収集をしたのか尋ねているのですが、その各選択肢について「十分に収集している」と回答した比率が50%を下回っているものが少なくなかった点がとても心配に感じました(図2)。
(【図2】)

私はソーシャルワーカーのひとりでもありますから、このなかでも、とりわけ「生活状況」(「十分に収集している」:42.4%)や「24時間の生活リズム」(同:40.3%)といった情報の収集を苦手とする傾向が示されたことに、大きな懸念を抱いています。
確かに、私がいくつかの保険者(市町村)の依頼を受けて行う“ケアプランの点検”の事業や、アドバイザーとして出席する“地域ケア個別会議”でも、アセスメント表などでそれらの項目が空欄のまま提出される資料や、それらの状況についての質問に答えることができないケアマネジャーが散見されます。今回の調査データは、そうした私の経験を裏付けるものとも言えます。
アセスメントにおける「生活状況」とは、生活歴や現在どのように生活しているのか(家族構成や経済状況、暮らしぶりなど)、病歴などを指します1)。これらの情報が十分に収集できていないとすれば、高齢者の個別性に着目し、その価値観に沿ったケアプランを作成することはできないでしょう。
これらの項目の情報収集が苦手だとすれば、そのケアマネジャーは図1の情報収集の手段として示す「面接・インタビュー」が不得手なのだと言わざるを得ません。相手の「生活状況」を把握するためには、一般的には大変に聴きづらいことを尋ねることとなります。しかし、そこを聴き取ることができるのがケアマネジャーの本来の姿です。ケアマネジャーのみなさんには面接技法のスキルアップに努めて欲しいと思います。
また、「24時間の生活リズム」は、介護給付のケアプラン標準様式第3表の「主な日常生活上の活動」欄に記載されるようなことを指すものと考えられます。この欄には、利用者の起床や就寝、食事、排せつなどの平均的な1日の過ごし方について記載することとなっています2)。この情報が十分に情報収集できていないとすれば、排せつの支援や栄養状態改善に向けた関わりを検討したり、認知症に伴う行動・心理症状の起こりがちな時間帯を把握してそれを軽減する支援を検討したり、さらには介護者である家族の負担感などをリアルに把握することなど、まずもって難しいのではないでしょうか。
このような情報の収集が苦手だとすれば、ケアマネジャーは図1の情報収集の手段として示す「面接・インタビュー」に加え、「観察」「他者への照会」などをしっかりと行って、利用者の生活リズムを把握する必要があると考えられます。利用者や家族の話・訴えを単に聴いているだけで情報収集ができるものでもありません。
アセスメントの大義は利用者の生活への理解
ケアマネジメントにおけるアセスメントの大義は、利用者の「生活」を理解することだと言ってよいでしょう。さらには、利用者一人ひとりの「人間理解」を深めるための手段だと言ってもよいと考えられます。
それにも関わらず、ケアマネジャーが、利用者の生活歴・暮らしぶり・病歴、1日の過ごし方などを把握するのが苦手なのだとすれば、生活や人間理解には程遠いのではないでしょうか。
ケアマネジャーのみなさんには、ADLや主訴など目に見え、聴き取ることのできる事実だけでなく、専門的な観察や適宜の照会などの技術を駆使して、利用者一人ひとりの思いや価値観、暮らしの個別性を把握するようなアセスメントを実施するよう望みたいと思います。
【注】(参考文献)
1) 介護支援専門員実務研修テキスト作成委員会(編)『七訂介護支援専門員実務研修テキスト上巻』pp415-417,長寿社会開発センター,2018
2) 『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』(平成11年11月12日・老企第29号/令和3年3月31日・老認発0331第6号改正)