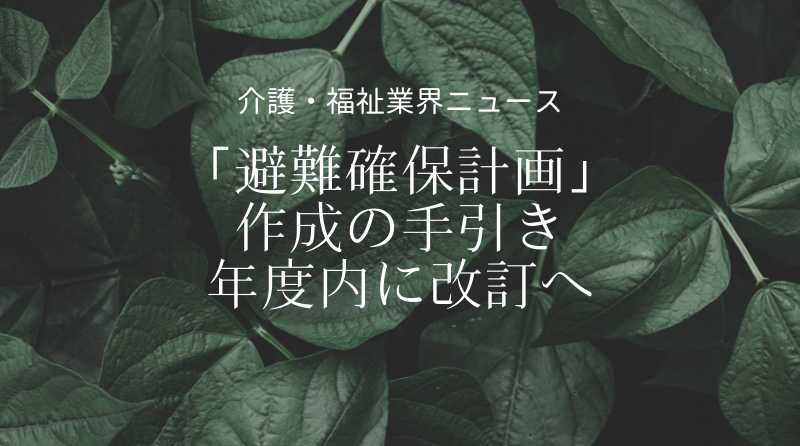2月24日、2021年度高齢者施設等の避難確保に関する第2回検討会が開催され、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」の改定に向け、有識者からさまざまな意見が聞かれました。今期に入り、国土交通省と厚生労働省が連携して話し合いを進めており、年度内の公表に向けた最終的な取りまとめが実施されました。
第2回検討会にて議論された改定案の概要と、本会議としての結論をまとめてご紹介いたします。
高齢者福祉施設の入居者らの避難確保の方策を国交省と厚労省が連携して検討
熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した令和2年7月豪雨を機に、高齢者福祉施設の入居者らの避難確保の方策などに関する検討が厚労省・国交省共同で進められてきました。
昨年12月に開かれた第1回の本検討会では、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する人が利用する施設。)における避難確保計画を作成するためのガイドラインである「要配慮者利用施設における避難確保作成・活用の手引き」の改定内容ついて議論が交わされています。手引きの改定は、要配慮者利用施設における災害時の避難の実効性を高め、避難確保計画の見直しや充実を促すために行われるもので、第2回目の会合では、有識者から前回の意見を踏まえた最終草案が国交省から提示されました。
>参考記事:高齢者施設等の避難確保計画作成の手引き改定案を提示 第1回フォローアップ検討会
介護事業業におけるBCP策定の義務化と対応状況に向けて
2021年度介護報酬改定では、感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、すべての介護サービス事業者を対象にBCP策定が義務付けられました。具体的には、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務化されています(経過措置期間:3年間)。
しかし、福祉医療機構が昨年11月半ばに公表したアンケート調査結果によると、すべてのサービス種別に共通した傾向として、「事業継続計画の策定」「研修の実施」「訓練の実施」のいずれの取り組みへの対応状況も5割未満と低迷しています。中でも「訓練の実施」への対応割合は最も低く、2割〜3割程度に留まる結果が公表されました。

本検討会にて取りまとめが実施されている「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」は、BCP策定等に活用できる内容が総合的に記載されています。中でも対応割合が低迷する「訓練の実施」に関して、ガイドとして画像やチェックリストを交えた情報が集約されており、活用が期待されます。
*参考記事:LIFEの利用状況、サービス種別間で格差―登録率は老健がトップ
時系列に従って避難行動をまとめる”タイムライン”作成参考資料の見直し
今回の「手引き」の改定では、施設職員や避難支援協力者が避難確保計画の内容をわかりやすく理解するため、要配慮者利用施設の管理者に対し、時系列に従って避難行動をとりまとめておく「タイムライン」を作成することを求めています。
この検討会では、管理者がタイムラインを作成する際の参考資料(「手引き」内に記載)についても話し合いを行っており、これまで「災害パターンや避難先に応じて作成する必要がある」「日中と夜間や施設の特性などに応じたものを作成する必要がある」などの意見があげられていました。今回は、それぞれの要素が追加されたガイドとひな形が提示されました。

これに対し、委員からは「地域でワークショップを実施すると、どこから手を付けて書き始めればいいか分からないとの声が多い」といった状況から、「手引き」上での説明を追記するよう求める意見や、避難先の確保をするためには、「関係機関との連携」に加えて、「同種団体や地域ネットワークを深めていく必要がある」といった趣旨の指摘などがありました。
米国AAR(After Action Review)の考えに基づいた訓練内容に関する説明の追加
訓練の実施に関して、第1回検討会での「訓練時に目的と目標を設定することで訓練結果の振り返りチェックがしやすくなる」との意見を踏まえ、最終草案に米国AARの考え方を参考にした訓練の実施を勧める旨が追記されました。AARへの理解を深める説明文も併せて提示されています。

【画像】令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォローアップ会議)第2回より抜粋
これに対し、座長を務める跡見学園女子大学の鍵屋一氏は「避難訓練では課題を発見し、解決に向けて取り組むことが重要。振り返りの重要性が伝わる文言の追記や分かりやすいひな形への改良を」と、現場レベルでの導入に対する期待を込めた課題点を述べました。
検討会としての結論と今後の流れ
「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」は一部の表現等について検討の余地が残っているものの、今回提示された内容に沿って取りまとめられ、3月中を目途に国交省のホームページ上にて公表される見込みです。
また、今回作成された手引きに関して「ボリュームがありすぎる」との声も聞かれましたが、2022年度以降、簡易的に情報を集約したリーフレットを作成予定である点も示されました。