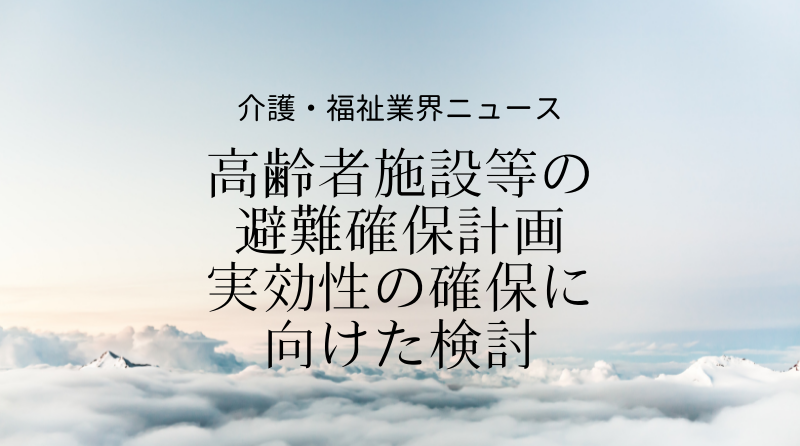国土交通省と厚生労働省は20日、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」の改定に向け、有識者会議で意見を求めました。
熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した令和2年7月豪雨を機に、厚生労働省と国土交通省は共同で、高齢者福祉施設の入居者らの避難確保の方策などを検討し、対策を進めてきました。両省が12月20日に開いた「令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会」では、「避難確保作成の手引き」の改定について検討が進められました。
本検討会で議論された改定案の概要と今後のスケジュールをまとめてご紹介します。
「避難確保作成の手引き」に求められる役割
避難確保計画は、大雨による浸水や土砂災害が発生するおそれがあるとき、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。
2020年7月、熊本県球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」で14名の人的被害が発生した豪雨災害を受け、これまでの避難計画の“作成”に向けた指針をまとめた手引きから、より実効性を持って“活用”できる指針を示していくためにこの手引きの改定が検討されてきました。
なお、水災害に対する高齢者等の安全確保についての施策は、大きく以下の3つの柱で構成されています。
1.安全な場所への立地誘導(高齢者施設等)
2.避難の実効性確保(高齢者施設等)
3.在宅高齢者等の避難確保(高齢者施設等との連携)
このうち、2つ目の柱である「避難の実効性確保」に「避難確保計画の作成・活用の手引き(改定版)」の提供が位置しており、高齢者施設等への技術的支援の一環として指針を示す役割があります。

【画像】2021年度第1回高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォローアップ会議)資料より抜粋(以下同様)
「避難確保計画の作成・活用の手引き」の概要と改定が検討されている項目
本検討会で示された改定案の骨子では、これまでの手引きの項目に「施設が有する災害リスク」「事前休業の有無と実施基準」「避難に要する時間と避難開始基準」「緊急安全確保の方法」「タイムライン作成ガイド」などが新たに追加されています。

「施設が有する災害リスク」の項目においては、施設のリスクを適切に把握することの重要性を踏まえ、対象となる災害の種類の記載とともに、浸水深や浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域の該当の有無などを記載することが明記されました。
「タイムラインの作成」は、情報収集や情報伝達、体制確立、装備品等の準備、避難誘導の実施などの防災行動を時系列で考え事前に整理しておくものであり、避難行動における留意点や課題について新たな“気付き”を得られる効果が期待されます。
多くの施設職員等が参加して作成するのが望ましいとされ、作成または見直しを訓練や防災教育の一環として取組む方法が一案として提示されました。

これらの改定案に対し、三重大学大学院工学研究科准教授の川口淳氏による「避難先選定のフローチャートがちゃんとあった方がいい」といった提案など、有識者によるさまざまな意見が集まりました。
今後のスケジュール
高齢者福祉施設における被害の再発防止を図るため、2020年10月に「令和2年7月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会」を設置し、高齢者福祉施設の避難の実効性を高める方策等がとりまとめられました。また、2021年5月には水防法・土砂災害防止法、災害対策基本法が一部改定されました。
本検討会は上記の流れを受けてのフォローアップ会議の初会合であり、第2回検討会が2022年2月ごろに開催される予定です。その後、検討内容を踏まえた「避難確保計画の作成・活用の手引き(改訂版)」について、2022年春頃の公表を目指すスケジュールとなっています。