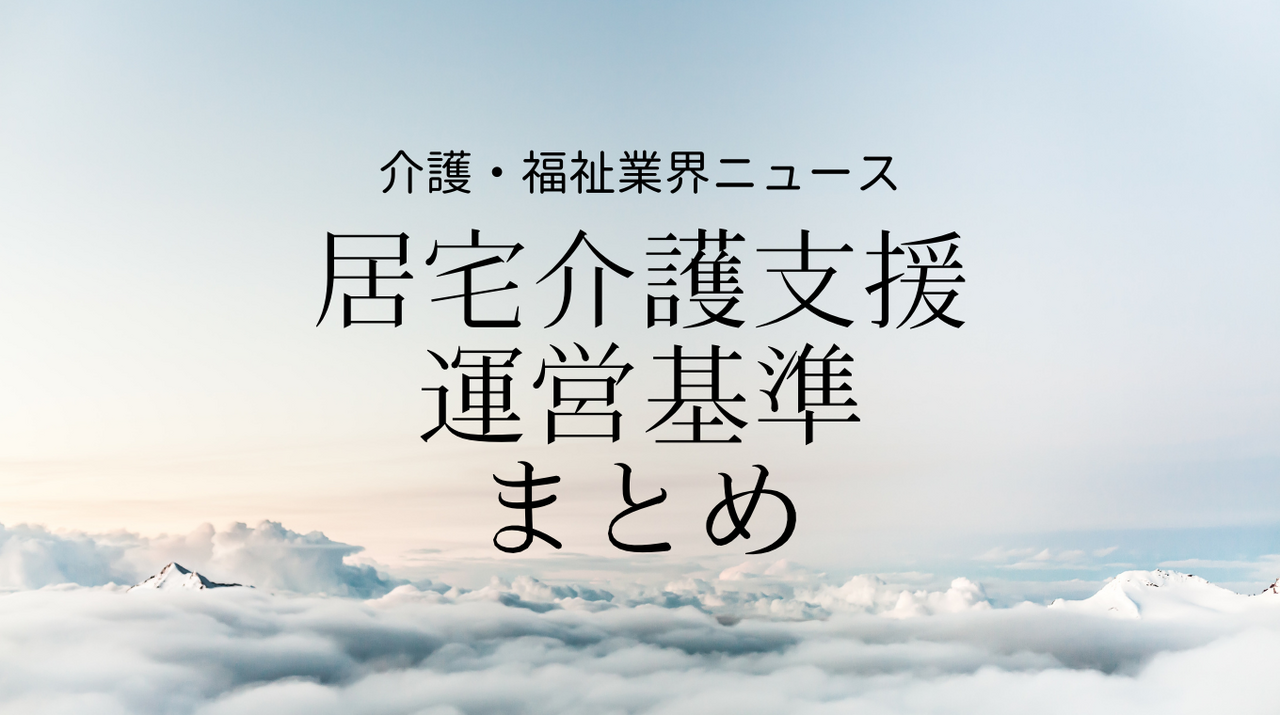2021年度介護報酬改定に向けた「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」について、本記事では【居宅介護支援】に関する省令※の改正内容を整理していきます。
※省令…指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準。以下「運営基準」とします。記事本文では該当する条項の内容を要約しています。
情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
【基本方針・居宅介護支援基準第一条の二 6(新設)】
全てのサービスについて、省令上にて「介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない」という規程が新設されました。具体的には、以下の点が運営基準として求められます。
●LIFEを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上に努めること
質の高いケアマネジメントの推進
【内容及び手続の説明及び同意・居宅介護支援基準第四条2(追加)】
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下の2点について、利用者に説明を行い、理解を得ることが新たに運営基準として求められます。
●前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
●前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
分科会ではケアマネジャーの事務負担への懸念や、利用者への説明頻度について質問があがりました。厚労省は事務負担を鑑みて、説明頻度など具体的な方法を検討したい、としています。
会議や他職種連携におけるICTの活用
【指定居宅介護支援の具体的取扱方針・居宅介護支援基準第十三条 九(追加)】
感染防止や多職種連携の促進の観点から、サービス担当者会議について、テレビ電話などICTの活用が可能になります。利用者またはその家族が参加してする場合は、テレビ電話等の活用についての同意を得る必要があります。
生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応
【指定居宅介護支援の具体的取扱方針・居宅介護支援基準第十三条 十八の三(新設)】
生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランについて、事務負担にも配慮して、ケアプランの検証の仕方や届出頻度の見直しを行います。区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業者を対象とした、点検・検証の仕組みが導入されます。
●検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行う、サービス担当者会議等での対応を可能とする
●届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする
●効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行

ハラスメント対策の強化
【勤務体制の確保・居宅介護支援基準第十九条4(新設)】
介護現場で問題となっている様々なハラスメントへの対策強化が、運営基準に盛り込まれました。居宅介護支援を含めたすべてのサービスを対象に、ハラスメントによって職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化など、必要な措置を講じることが義務付けられます(経過措置なし)。
業務継続に向けた取り組みの強化
【業務継続計画の策定等・居宅介護支援基準第十九条の二(新設)】
感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築することが、次期改定の柱の1つです。これを踏まえ、業務継続に向けた以下の3点が運営基準で義務化されます。
●業務継続に向けた計画(業務継続計画・BCP)を策定し、感染症や非常災害発生時には計画に従って必要な措置を講じること
●業務継続計画を職員に周知するとともに、必要な研修や訓練を定期的に実施すること
●定期的に業務継続計画の見直しを実施し、必要に応じて計画内容の変更を行うこと
上記の運営基準の改正に際し、省令施行日から2024年3月31日まで、3年間の経過措置期間を設けるとしています。
感染症対策の強化
【感染症の予防及びまん延の防止のための措置・居宅介護支援基準第二十一条の二(新設)】
介護サービス事業者の感染症対策を強化する観点から、以下3点の対策が義務化されます。
●感染症の予防・まん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催すること。その結果について、職員等に周知徹底を図ること。(委員会はテレビ電話など情報通信機器を活用して行うことができる)
●事業所における感染症の予防・まん延の防止のための指針を整備すること
●職員等に対し、感染症の予防・まん延の防止のための研修・訓練を定期的に実施すること
なお、経過措置期間は省令施行日から2024年3月31日までの3年間が設けられます。
運営規程等の掲示に係る見直し
【掲示・居宅介護支援基準第二十二条2(新設)】
現行では、各サービスにおける運営規程等の重要事項は、事業所内の見やすい場所への掲示が義務付けられています。この点について、介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、閲覧可能なファイル等で据え置くなどの対応が可能となります。
具体的には、重要事項に関する書面を事業所に備え付け、かつ、関係者がいつでも自由に閲覧できる状態とすることで、掲示の代わりとするとしています。
高齢者虐待防止の推進
【基本方針・居宅介護支援基準第二十七条の二(新設)】
介護福祉現場で問題となっている高齢者への虐待に関して、利用者の人権の擁護や虐待の防止等の観点から、以下の4点が義務付けられます。
●虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。(委員会はテレビ電話など情報通信機器を活用して行うことができる)
●事業所における虐待防止のための指針を整備すること
●職員等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること
●上記の虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと
虐待防止に関する運営基準の改正に際し、省令施行日から2024年3月31日まで、3年間の経過措置期間が設けられます。
記録の保存等に係る見直し
【電磁的記録等・居宅介護支援基準第三十一条(新設)】
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、諸記録の保存・交付等について、原則として電磁的な対応が認められ、必ずしも紙媒体で保存する必要がなくなります。
利用者への説明・同意等に係る見直し
【電磁的記録等・居宅介護支援基準第三十一条2(新設)】
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担を軽減する観点から、利用者やその家族に対する説明・同意等※のうち、書面で行うものについて、相手の承諾を得たうえで、電磁的な対応が認められます。
具体的には、ケアプランや重要事項説明書などの説明、同意を得る際に、必ずしも紙の書類を用意する必要はなく、タブレットやPCなどを使ってデータで提示する運用も可能となります。
※説明・同意等…交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの
引用:第199回社保審・介護給付費分科会「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」より