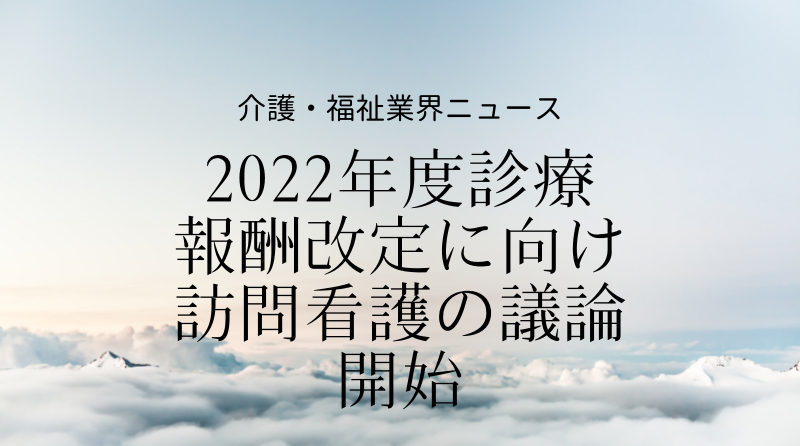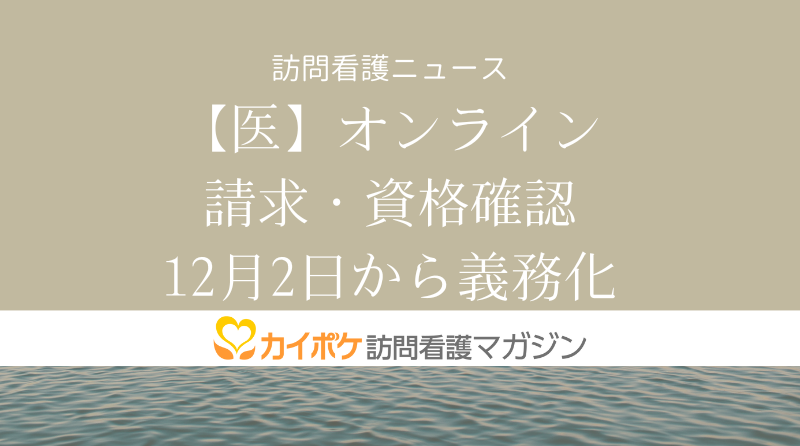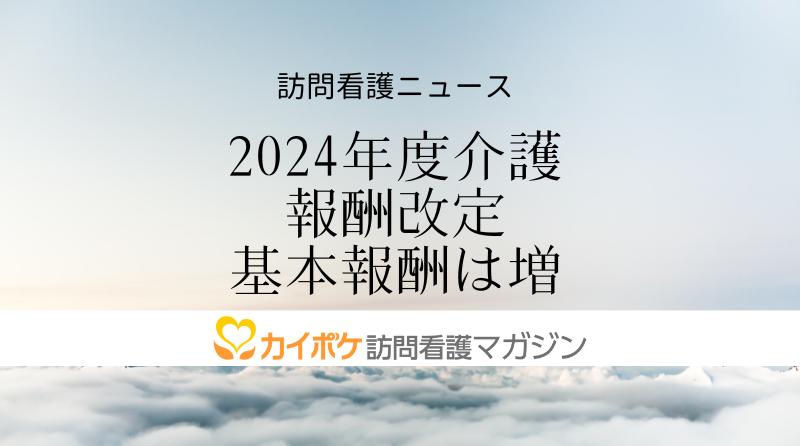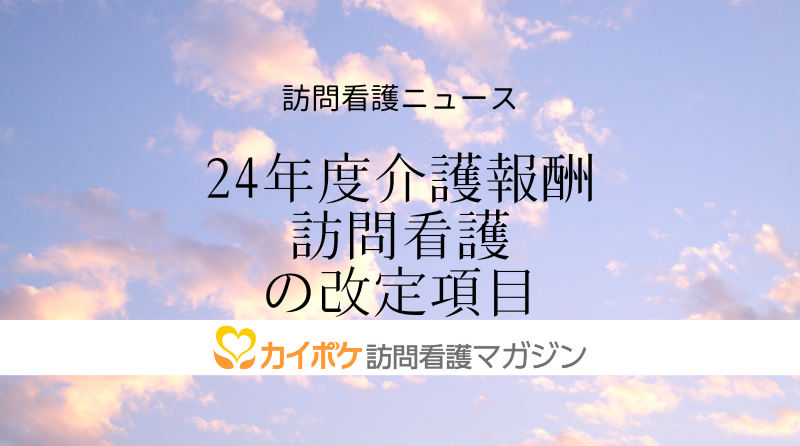介護報酬改定から、早くも5カ月が経過しようとしています。ここで次の動きに視線を送ると、2022年4月に控える診療報酬改定に向けた議論が本格化しています。介護保険制度との関わりという面で直近の診療報酬改定項目を振り返ると、ここしばらくは、医療と介護の連携強化や医療保険制度と介護保険制度との整合性などが盛り込まれています。今回は訪問看護事業所の運営に関連する論点について、介護保険制度ととつながりを意識しつつ現在の議論の状況などを整理しました。
*関連記事:訪問看護の単位数 2021年度介護報酬改定、【訪問看護】2021年度報酬改定 加算の創設・見直し要件まとめ 厚労省・審議報告
2022年度改定に向けた議論の状況と訪問看護の位置付け
介護報酬改定については、社会保障審議会・介護給付費分科会がその方向性や具体的なルールなどについて検討するのと同様に、訪問看護療養費を含む診療報酬改定の内容は「中央社会保険医療協議会」(以下・中医協)で検討されます。中医協では現在、委員が以下のテーマに沿って意見を交わし、論点を整理しようとしているところです。
●コロナ・感染症対応
●外来医療
●入院医療
●在宅医療
●歯科
●調剤
●そのほかの個別事項(医師などの働き方改革の推進 、不妊治療の保険適用、 医薬品の適切な使用の推進 、 歯科用貴金属の随時改定)
中医協はこれらのテーマに沿った「意見の整理」を9月にまとめ、そこで上がった課題などを解決するためのアクションとして厚労省が具体的な報酬改定項目について検討材料を示すことになります。

【表】 第482回中央社会保険医療協議会 総会資料より(7月7日)
訪問看護の2022年度改定に向けた方向性と厚労省の課題感
訪問看護を巡っては、8月25日に検討が始まりました。
議論に先立ち厚労省は、訪問看護を巡る現状として、
▽訪問看護ステーションの利用にかかる費用は、医療費及び介護給付費ともに増加しており、医療費の伸び率が大きいこと。
▽看護職員数の多い訪問看護ステーションが増加傾向であり、機能強化型訪問看護管理療養費の届出も増加傾向にあること。
▽訪問看護ステーションにおける職種別の従事者数のうち、理学療法士等が占める割合が増加傾向にあること。 などを示しています。



【画像】 第486回中央社会保険医療協議会 総会資料より(8月25日)
また、訪問看護の診療報酬上の評価については
▽訪問看護ステーションの利用者の主傷病は、「精神及び行動の障害」が最も多く、精神科訪問看護基本療養費を算定した利用者の主傷病のうち、統合失調症等の利用者が半分以上を占めていること。
▽2020年度診療報酬改定では、機能強化型訪問看護ステーションの人員配置要件の見直し、小児への訪問看護に係る関係機関の連携強化、専門性の高い看護師による同行訪問の充実の評価を行ったこと。
▽ 訪問看護ステーションにおいて、褥瘡ケア等のニーズを有する在宅療養者に対する専門の研修を受けた看護師による同行訪問の算定件数は増加傾向にあること。
▽ 特定行為研修修了者が増加するなか、就業場所も多岐にわたっており、特定行為研修修了者のうち約4.5%が訪問看護ステーションで就業している
ことなど示し、「2020年度診療報酬改定の考え方を踏まえ、質の高い訪問看護の適切な評価を推進しつつ、地域包括ケアを推進する役割を果たしていくため」には、2022年度改定ではどういった対応が必要であるか議論を促しました。
これに対して委員からは「特定行為ができる看護師の活用について何らかのインセンティブを検討してもいいのではないか」「医科・歯科・調剤と比べても訪問看護にかかる費用の伸びは著しい。患者の状態に応じた適切な訪問看護が行われているのかどうか、適切な職種が適切頻度で訪問看護を行っているのか、エビデンスを基に議論していくことが必要」などといった趣旨の意見が上がっています。
近年の診療報酬改定と介護報酬改定、訪問看護の方向性
今後の議論の方向性を予測するうえで、最後に近年の訪問看護をめぐる診療報酬改定・介護報酬改定の動向を確認してみましょう。

※画像クリックで拡大表示
こうして改定項目を時系列で見てみると、25日の論点として厚労省が示したテーマである中重度者を支えるための「24時間体制」や「医療ニーズの高い患者への対応」、「訪問看護にかかる費用の適正化」といったテーマについて、診療報酬(医療保険制度)と介護報酬(介護保険制度)は相互に影響しながら対応していることがわかります。厚労省は2022年度改定でも、こうした方向性を踏襲していく方針であることがキックオフミーティングの内容からも伺えました。
介護経営ドットコムでは、訪問看護事業を運営するうえで、地域における連携や営業先、看護師の採用や育成戦略をご検討いただけますよう今後の議論の方向性を引き続きレポートしていきます。