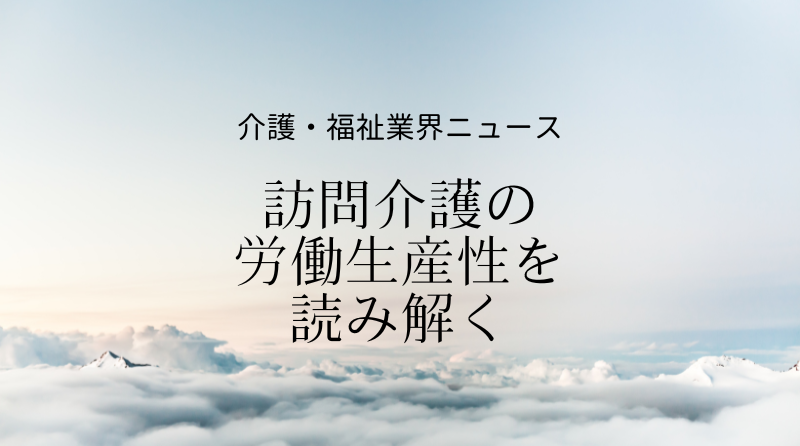訪問介護事業の経営に関わる皆さまは事業の拡大を検討するうえで、多角化や多店舗展開が視野に入るのではないでしょうか。
今回は「労働生産性」に着目し、訪問介護の事業特性の評価を試みている研究データをご紹介します。事業の実態を掴むためのデータの一つとして、ぜひ最後までお読みください。
介護サービス情報公表システムの事業所別データを分析
今回ご紹介するのは、学習院大経済学部の鈴木亘教授による研究「訪問介護産業の労働生産性ー事業所データを用いた分析」です。
介護サービス情報公表システムの事業所別データ(2014年度から2017年度にかけてのもの)を分析したもので、訪問介護事業の経営を考えるためのヒントを読み取ることができます。
介護産業の労働生産性を考える上での定義
まず、この分析では「労働生産性」を以下の3つに定義しています。
(1)労働生産性1=介護労働者1人当たり(労働時間ベース)のサービス提供時間
(2)労働生産性2=介護労働者1人当たり(労働時間ベース)の介護報酬単位数
(3)労働生産性3=介護労働者1人当たり(労働時間ベース)のサービス利用者数
労働生産性1、2については勤務時間内のうち、実際にサービスを提供する時間や回数の割合のことなので、「稼働率」に近いかもしれません。
介護産業を含むサービス産業の生産性は、需要変動に合わせて、いかに無駄なくサービスを同時提供できるかが大きな要素を占めます。鈴木教授は、介護労働者1人当たりが効率よく直接的なサービス提供に関わる時間を増やしたり、報酬算定につながる業務量を増やすことの重要性を指摘しています。
介護予防訪問介護や居宅介護支援との兼業の効果
まず、この分析から、訪問介護事業所と他事業所を兼業することで得られる効果についての知見が得られます。
訪問介護事業と介護予防訪問介護事業を同一法人が兼業すると16.8%から27.5%、労働生産性が押し上げられるという結果がでています(数値は採用する労働生産性の指標によって変動)。
実際に、同一法人が介護予防訪問介護を兼業している割合は実に96.7%にも及んでいます。
居宅介護支援の兼業については、併設ケアマネジャーが同じ法人の訪問介護サービスを勧めて過剰な誘発需要を生み出すという批判もありますが、やはり労働生産性を17.7%から26.8%、押し上げています。
鈴木教授は、同じ法人が居宅介護支援を行っていた方が、訪問介護事業所の稼働状態を良く把握していて、移動時間やサービス提供時間を無駄なく調整できるメリットがあるとも指摘しています。
多店舗展開は必ずしも労働生産性の向上につながらない?
切り口を変え、一法人あたりの事業所を増やしたり事業所の合併や連携を進めたりする効果を考えてみましょう。
同一法人が運営する訪問介護事業所数の規模ごとに労働生産性を見てみると、1法人が1事業所を運営している場合は、5.7%から6.7%労働生産性が低い状況です。

【画像】「訪問介護産業の労働生産性—事業所データを用いた分析」(学習院大・鈴木亘教授より)
ここから、複数事業所を持つことや、零細事業者の合併や連携を進めることは労働生産性向上に有効と考えることができます。
一方で、この分析では2事業所以上を運営しているからといって規模の経済が働いているかどうかは明確になっていません。
その背景としては、
・指定申請・届け出などの様式が市区町村ごとに異なること
・人員基準によって同一法人の隣同士の事業所間で介護労働者を繁閑の差に応じて融通し合うことができないこと
などが挙げられています。
言い換えると、複数の訪問介護事業所を広域で展開しても、現行の諸規制は規模の経済が働きにくい構造を生み出しているのと考えられます。
こうした事情を踏まえると、ドミナント経営を戦略に取り入れることも有効な手段かもしれません。
処遇改善加算や特定事業所加算を算定すると労働生産性も高まる
この分析では、サービスの質と労働生産性との関係にも言及されています。
その指標としては、処遇改善加算や特定事業所加算の算定状況が用いられています。
処遇改善加算や特定事業所加算の算定をしている事業所ほど、労働生産性が高くなっていることがほぼすべての加算区分で確認されているのです。
鈴木教授は、サービス提供体制や介護労働者の質が高い事業者ほど利用者が多くなり、稼働率が高まる効果があるものと考えています。