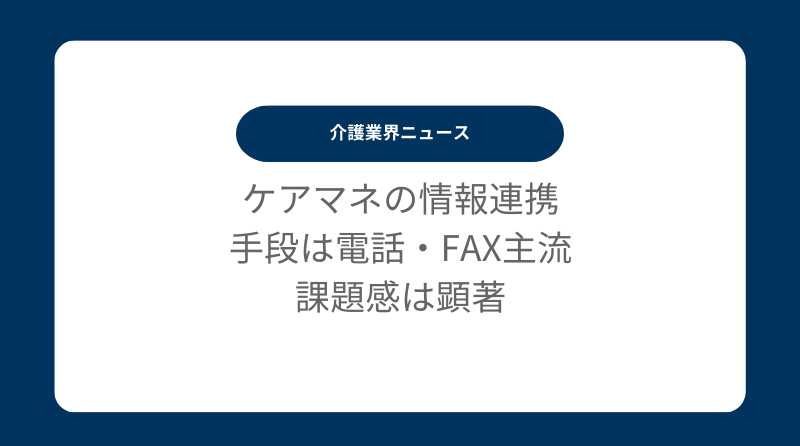課題はやはり人材採用・育成
現在の事業内容を教えてください
・訪問看護ステーションが1か所
・予防のデイサービスが2か所
・福祉用具が1か所
・工房とカフェ
・保育園
・放課後等デイサービス
・チョコレート屋
・就労支援
の事業を展開しています。
これまで介護事業の経営・運営において抱えていた課題は何ですか?
課題として大きいのは人材採用・育成です。生産性向上やマネジメントはいろいろと試行錯誤していますが依然として課題ですね。また、人事考課やコミュニケーションについても課題感はあります。
一方で、法改正はコントロールできないし、自分たちではどうにかできるわけではないので、もちろんチェックはしていますが、課題という意味では特に感じていません。
デザイン経営を取り入れて採用ブランディング等に活用
課題とされていた人材採用・育成についてはどのような取り組みをされていますか?
採用の取り組み
採用については、間口を結構広げています。広げるというのはどういうことかというと、介護の求人募集でだけでなく、スポーツ分野とか他の分野にも募集をだしています。
例えば、チョコレートの販売でリクルートして、高齢者にも興味があるということであれば、介護側に配属するというようなことで、そうなりやすいようにタッチポイントを増やすようにしています。現在では、福祉用具で採用した方をデイサービスで機能訓練の手伝いネットワークをうまく活用したり、トイザらスで働いていた方が運動指導をしていたりします。
それ以外でも、ブランディングに力をいれています。弊社の言うブランディングとは、デザイン経営をあらゆることに取り入れて実践していることです。デザイン経営についてもスタッフが挑戦できるとか、そういうことをサイト上に訴求し、対外的にうちだすことで、 どこでやっても同じと見えないように努めています。
育成の取り組み
育成の取り組みとしては、当社で働く上でやってほしいことを明確化し、社内研修を強化しています。その他にも言葉の認識の違いも多かったため、経営方針書というものを作成、配布し、共通認識がもてるようにしています。それらにより、目指す方向性も明確になってきているという声や、コミュニケーション量が増えたという声がでてきています。
また、人事面での大きな課題として、人事考課が可視化されていないということがありました。なぜ昇給するのかが曖昧で、年功序列のようになりつつあったのも不安でした。
そこで、評価項目と個人の目標達成に重きをおいて改善し、できるだけ目標達成度を数値化するようにしました。数値で測りにくいような利用者さんからの評価などもアンケートで満足度をはかって、それを数値化するようにしました。個人の目標の妥当性についても、上位となる役職者に対して、部署目標⇒現場サイドで考えるというように仕組み化して、可能な限りムラがないように努めています。
マネジメント層の人間力向上のため心理学の研修などを実施
採用、育成の取り組み実施後の変化はありましたか?
まだ変化の実感はありませんが、目標の未達が多かったのが、目標達成できる人は増えてきたように思います。また、人の定着はよく、退職者が年間1名~2名程度と少なく、人間関係もすごく良いと思います。
これには、マネジメント層の人間力の向上の取り組みとして研修をやっていて、心理学、具体的には選択心理学<自分は変えられる、人は変えられない>のようなこともやっているからだと考えています。
経営におけるこだわり、大事にしていることは何ですか?
繰り返しになりますが、デザイン経営に力をいれていることです。デザイン経営のデザインとはビジュアルイメージでとらえがちですが、問題解決に使うことをさしています。もう少し詳しく言うと、デザインシンキングの思考をケアの質を向上する部分に活用しています。
例えば、旅行にいくということも、ただの旅行でなく、思い出づくりと体験を一緒にパッケージ化して考え、提供することなどです。デザイン経営を取り入れたのは、私たちにしかできないことを創造していくということを志向する中で、それがあったからです。2025年までは高齢者人口は増えていきますが、それでも差別化ができていないとやはり苦しいと思います。
今後は、身体だけでなくVR等で視覚的な変化など新しい楽しみをつくりたい
今後はどのような展開を考えていますか?
会社としては、街づくりに注力<医療、福祉>し、できることからやっていきます。今はじめているのは、高齢者とかだと役割づくりがあまり感じられない人が多いので、高齢者が自ら役割を見出せるような場所づくりをしていきたいと考えています。
そして、アートの導入も考えていて、そういうものを事業所に展開するということも考えています。今は、運動機能の訓練のように身体機能のアプローチはありますが、視覚的なものはあまりできていないので、絵を見せて、視覚的な変化をあたえることを考えています。例えばVR旅行なども考えていて、そういった新しい楽しみをつくっていきたいですね。
コロナ後の世界と生き残るために重要だと思うことは何ですか?
変化に柔軟であることが大事です。
法改正やコロナなど周りはびくびくしていますが、ある程度想定をして先回りして動き方を考えていくことが必要で、自分たちしかやっていないことがあれば淘汰はされないと考えています。
それをやっていれば、利用者さんから評価をされるだけでなく採用面でもプラスになっていくと考えています。