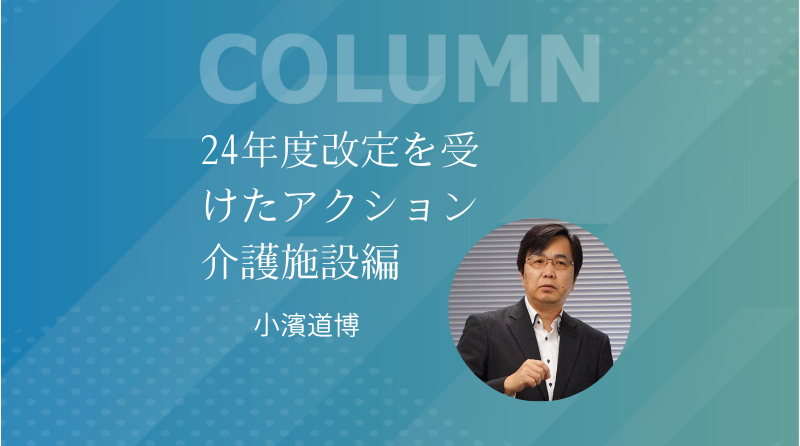これまで2024年度介護報酬改定のポイントをサービス累計別に振り返ってきた(*居宅介護支援、在宅系サービス)。今回は本企画の締めくくりに施設系サービスについて解説したい。改定の影響が大きく、多岐にわたると考えられる介護老人保健施設のほか、特別養護老人ホームの改正点について見渡していく。その上で介護施設に共通する改正点と運営への影響や必要な対応を整理していこう。
1,多床室料の自己負担化が現実となり、長期滞在型老健の経営にダメージ
まず、給付と負担の在り方を巡って攻防が続いていた老健と介護医療院における多床室料の自己負担化が現実となった。老健については、療養型とその他型が、介護医療院はⅡ型が対象となる。対象となる入所者は、月額で8,000円程度の負担増となる。
低所得者への配慮として、利用者負担第1~第3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させないという配慮はあるが、確実に長期滞在型の介護老人保健施設の経営を直撃する。多床室料が全額自己負担となった時点で、特養との月々の利用者負担額の差が大きくなるからだ。老健の長期滞在者の一部は、割安感の増した特養に移動するだろう。
介護報酬単価を見たときに、明らかに特養より高いに関わらず、長期滞在型の老健が経営維持出来ていた理由は、多床室型の老健には、特養との実質的な支払金額の差が少なかったからだ。
特養の待機者が減少し、空床も生じている今、入所者の移動が起こることが想定される。
2,介護老人保健施設には現状維持を廃しレベルアップが求められる改定に
その老健の基本報酬は、施設類型によって明暗が大きく分かれている。
在宅強化型が4.2%のプラスであるのに対して、その他型が0.86%、基本型が0.85%と大きく差が開いた。中間の区分である加算型は、特養並みの改定率となった。介護事業経営実態調査の結果で老健全体の収支差率が-1.1%だったことを考えると、1%に届かない改定率では経営環境は非常に厳しいと言える。特に、その他型は前段で触れた通り多床室料が月額で8,000円程度の自己負担増となる分、ダブルパンチである。
こうした改定となったのは、その他型や基本型は、実質長期滞在型の老健となっており、“病院と居宅の中間施設”という老健本来の役割を果たしていないという評価だ。今改定で、長期滞在型老健の経営モデルは破綻したと考えるべきだろう。そうした施設は、短期〜中期ビジョンの中で、まずは加算型への転換を早急に検討すべきだ。
また、老健の施設類型、すなわち基本報酬のランクを決める評価指標のハードルが引き上げられた。具体的には入所前後訪問指導割合、退所前後訪問指導割合の引き上げに加え、支援相談員に社会福祉士の配置が無い場合の点数が減らされた。これによって、さらに上位区分の基本報酬算定が難しくなった。入所前後訪問指導割合、退所前後訪問指導割合の指標が最大35%以上に引き上げられ、15%以下の場合の配分は0点である。支援相談員に社会福祉士の配置が無い場合は、点数が2点減点される。現在、ギリギリの点数で強化型、超強化型を算定している施設では状況によってランクダウンが想定される。
老健においては、現状で満足することなくレベルアップすることが求められているということだ。基本型が加算型に移行するためのハードルも上がり、その影響が懸念される。
2024年度改定で変更があった老健の加算・緩和措置
ここからは、老健の加算に目を移そう。認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、これまでと同等の単位を算定するには「入所者の居宅を訪問し生活環境を把握する」という要件を満たさなければならない。できない場合は、加算単位が半分に減額される。
短期集中リハビリテーション実施加算では、入所時及び月1回以上ADL 等の評価を行うことなどを要件とする上位区分が設けられている。また、ターミナルケア加算では、死亡日の前日及び前々日並びに死亡日を高く評価する変更が行われた。老健にも看取り対応が求められるということである。
また、全ての入所者に見守りセンサーを導入したうえで夜勤職員全員がインカム等の ICT を使用している場合、夜勤職員配置を2人以上から 1.6 人以上に緩和する措置が取られた。これは、前回の改定で特養に適用された措置に続くものである。
3,特別養護老人ホームについては大きな変更点なし
特別養護老人ホームの基本報酬は、総じて2.8%程度のプラスとなっている。特養単独で見た場合、大きな変更点はない。特養独自の改定項目としては透析患者が施設に入所できないという社会問題の解決策として、施設職員による透析患者の病院への送迎を評価する特別通院送迎加算が創設された。これは、月に12回以上の透析患者の送迎が要件となるが、往復で一回のカウントであるので注意が必要だ。
4,居住費の引き上げはあるものの食費引き上げは見送りに
ここからは介護施設全体に関わる改正点について指摘していきたい。まず、24年8月からは介護施設の居住費の基準費用額の1日当たり60円引き上げられるが、これは焼け石に水の措置である。それ以上に、介護施設の食費の引き上げが見送られたことが経営には打撃となるだろう。食材費の高騰を自己努力で克服するには物価が上がりすぎている。そのため、厨房での炊事を断念して、冷凍食品や真空パックの食事に切り替える動きも加速している。厨房を維持する為の人件費負担が重荷であることと、昨今の人材不足の影響も大きい。
5,新興感染症対策の充実
介護施設系にはほかのサービス累計と比較しても、新興感染症対策が多く盛り込まれた。新興感染症とは、コロナに続く新たなウィルスのパンデミックである。コロナ禍の教訓を踏まえて、次に出現するであろう未知のウィルスへの準備を進めていく。また、入所者の体調急変に備えて、緊急時対応の準備や、24時間体制で相談、診察、入院の出来る医療機関との協力体制の義務化などが強化されている。特養の配置医師緊急時対応加算では、夜間、深夜、早朝に加えて、日中であっても、配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合の区分も創設された。
問題は、連携する協力医療機関との契約である。新たな高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、第二種協定指定医療機関との連携が要件となる。この該当する病院が全国的に限られていて、かなりの狭き門である。課外当病院との連携は、2024年10月以降は算定要件では必須となる。
6,施設基準や加算要件等多岐にわたって盛り込まれた生産性向上への取り組み推進策
このほか横断的な事項として注目すべきは、生産性向上への取り組みについてだろう。短期入所系、居住系、多機能系、施設系のサービスには、3年間の経過措置を設けた上で、生産性向上委員会を設置することが義務化された。同時に、ICT化に取り組み、その改善効果に関するデータを提出することを評価する生産性向上推進体制加算が創設された。この加算はアウトカム評価の加算で、1年程度、10単位の区分Ⅱを算定し、業務改善の結果が出ていると評価された場合は、区分Ⅰに移行できる。区分Ⅰでは、入所者全員に見守りセンサーを導入し、出勤して配置すべき介護職員全員分のインカムを配置し、介護記録ソフトを導入していることが算定要件となる。
新たに創設される介護職員等処遇改善加算の算定要件である職場環境等要件は、生産性向上を目的とした業務改善の取組を重点的に実施するよう内容が改められている。具体的には、業務改善委員会の設置、職場の課題分析、5S活動、業務マニュアルの作成、介護記録ソフト、見守りセンサーやインカムの導入、介護助手の活用などである。基本的に実践にあたっては、厚労省が提供している介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン、介護分野における生産性向上の取組を支援・促進する手引き、介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き、などを参考に進めて行くこととなる。
7,業務継続計画未策定減算と高齢者虐待防止措置未実施減算の注意点
最後に、原則全てのサービス事業所に関わる業務継続計画と高齢者虐待防止についてだ。24年4月からはBCP作成と高齢者虐待防止措置への未対応事業所には減算が適用されるようになっている。BCP減算には特例措置があり、感染症の指針と自然災害BCPが出来ていた場合には25年4月からの減算であるが、虐待防止措置は24年4月から適用される。
業務継続計画未策定減算は、施設系は3%、その他のサービスは1%。高齢者虐待防止措置未実施減算は一律1%である。注意すべきは、BCPの策定が義務となるタイミングは24年4月であることには変わりはないという事だ。減算とならなくても、運営指導で運営基準違反として指導対象となる。
高齢者虐待防止措置未実施減算は、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、専任の担当者の設置の4つを、ひとつでも実施していない場合に減算となる。

(【画像】厚労省資料「令和6年度介護報酬改定の主な事項」)