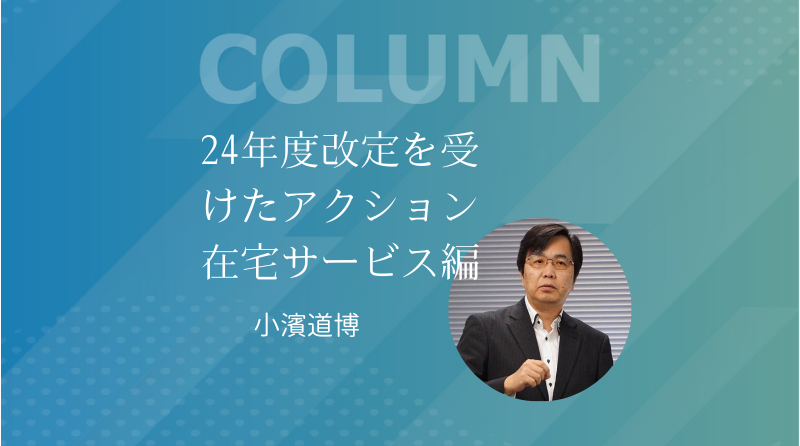今回の介護報酬改定は、すべての介護サービスがプラス改定となった訳ではない。
ヘルパー不足が表面化し、経営環境の厳しさが増している訪問介護の大きな減額は、業界を震撼させた。また、定期巡回サービスも4%以上のマイナスとなった。これらのサービスにおいて”現状維持”という選択を選べば、自動的に減収となってしまう。
一方、デイサービス事業者にとって影響が大きい改正点には、担当者への研修受講義務化など入浴介助加算の算定要件が挙げられる。
今回は、在宅系サービスにおける2024年度介護報酬改定のポイントを振り返り、事業者がとるべきアクションについて解説したい。
(*編集注:居宅介護支援についてはこちらで解説いただいています。)
1,訪問介護と定期巡回が厳しい評価に。訪問看護では理学療法士等によるサービスの評価見直し
基本報酬において訪問介護は、30分以上1時間未満の身体介護で見た場合、2.3%のマイナスとなっている。単位にして6単位の減額だ。
訪問介護は加算の算定でマイナス分をリカバリーしようにも、位置づけられている加算の種類が圧倒的に少ない。
また、稼働率を上げて対応しようにも、ホームヘルパーの有効求人倍率が15倍を軽く超えている現状では、それも難しい状況だ。
そこで、最も効果的であり算定すべき加算は、特定事業所加算である。
同加算の加算率は請求金額の3%〜20%の5区分ある。
もちろん、算定要件のハードルは高く容易に算定は出来ないが、優先事項として検討すべきだろう。
その中でも、新区分Ⅳは3%の加算率であり、この区分を算定することで基本報酬のマイナスは補填できる。
算定要件は会議や研修の実施といった基本要件を満たした上で、「サービス提供責任者を規定よりも1名多く配置する」ことでも算定が可能となるよう要件が緩和された。
従来の「勤続7年以上の介護職員が30%以上」という算定要件とのいずれかを満たすことで算定できる。この勤続年数についても、24年度改定のQ&Aにおいて、「同じ法人内であれば他の介護サービスでの介護職員としての勤務年数を通算できる」とされた。特定事業所加算の算定事業所の割合は少ないが、こうした緩和等が訪問介護事業の収益を改善する可能性は高い。
問題は、会議や文章での伝達といった基本要件での事務負担の増加である。
特に、小規模事業者は経営者やサービス提供責任者が現場に入りっぱなしの状態であるため、「事務負担の増加に対応できない」という声が根強い。
事務負担の軽減策としては、業務改善とICT化が一般的であり、そのためにICT補助金や助成金を有効活用すべきである。しかし、これらも小規模事業者にはハードルが高い。八方ふさがりに近い状況で、有効なアドバイスを送ることが出来るブレーン確保や、業務負担を軽減するためのサービスの活用がキーポイントになるだろう。
従来の手法が通じなくなっている。今までのやり方を基準にするのではなく、「これからどうするか」。思考の転換が急務である。
(【資料】「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(厚生労働省)より(以下同様)
次に、定期巡回サービスは月額で700単位前後のマイナスとなっている。そのため、総合マネジメント体制強化加算で、新たに設けられた上位区分の算定は必須である。上位区分は既存の同加算に200単位プラスされている。この200単位は、既存の報酬区分(今改定では下位区分に位置付けられた「(Ⅱ)」)を200単位減らして付け替えたものだ。上位区分を算定する事で、700単位のマイナスが500単位に圧縮できる。しかし、現状維持を選んだ場合は、マイナス幅が900単位に拡大する。上位区分の算定には、新たな算定要件をクリアする必要がある。今回の介護報酬改定は、現状維持という選択が出来ない厳しい改定でもある。
訪問看護も多くの加算が創設された。専門管理加算、初回加算の上位区分、診療報酬に合わせて増額されたターミナルケア加算、緊急時訪問看護加算の上位区分への対応も必須である。また、理学療法士等による訪問の基本報酬減算及び介護予防訪問看護において12カ月を超えた場合の減算の適用要件が厳格化された。
①訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。
②緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していない。
このどちらかに該当した場合には、理学療法士等の訪問1回につき8単位が所定単位数から減算となる。
2、通所系サービス:デイサービスでは入浴介助加算の算定要件確認との個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)の算定検討を
デイサービスの基本報酬は0.44%、地域密着型通所介護は、0.38%のプラスとなった。
個別の改正点としては、入浴介助加算Ⅰの算定要件に、入浴介助担当者への入浴技術研修が義務化されたことが大きい。
研修自体は、厚生労働省がビデオ講座と解説書を提供しているので、それを活用すれば足りる。しかし、この算定要件の変更を知らずに従来通りの提供を続けた場合、運営指導で報酬返還となるだろう。
また、入浴介助加算Ⅱについては、デイサービス、デイケアともに、介護職員がカメラマン的な立ち位置で居宅訪問が可能となっている。ただし、あくまでもビデオやZOOM中継のカメラマンであって、評価やアドバイスは医師等が行うことに注意すべきだ。
デイサービスの個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)の算定要件である機能訓練指導2名配置中、一名が常勤専従である旨の要件が廃止となり、2名共に機能訓練の時間帯に配置する非常勤配置が可能となった。同時に、非常勤化で人件費が減少するとして、加算単位が減額された。この変更で、リハ職を手厚く配置してきたリハビリ特化型デイサービスが減収となっている。しかし、常勤専従規定がネックでⅠ(ロ)の算定が出来なかった事業所が算定可能となったことはプラスに捉えるべきだろう。
これが算定できた場合、月20単位の増収となる。たとえば、午後から非常勤の療法士が勤務し、常勤で看護職員を配置した場合、この職員を午前中は看護職員、午後は機能訓練指導員とすることで、午後の時間帯は2名体制となってⅠ(ロ)の算定が可能である。
デイケアでは大規模事業所の運営有利に退院時の早期介入も促進
デイケアは、通常型は0.7%であるが、現行の大規模Ⅰは、大規模型の統合の影響で、-2.8%となっている。これは、大規模ⅠとⅡが統合され、大規模型となった影響である。大規模型であっても、リハビリテーションマネジメント加算を全体の80%以上算定し、リハ職を10:1の割合で配置した場合、通常型の報酬を算定出来るとして、大規模有利の方向が示された。
入院中の利用者が退院後に速やかにサービスが開始出来るための措置が多く盛り込まれている。
具体的には入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手することが義務化され、理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する退院後共同指導加算が創設されている。リハビリテーションマネジメント及び栄養アセスメントとLIFE活用を行った場合の新区分が創設された。
また、通所系サービスにおける送迎では、共同送迎を認められるようになっている。

3,訪問介護と居宅介護支援への同一建物減算も改定ポイントに
同一建物減算は、訪問介護で強化され、居宅介護支援にも創設される。訪問介護は、新たに12%減算の区分が創設される。前6カ月の提供件数の内、同一敷地内または隣接する建物に居住する利用者が90%以上である場合に適用となる。このカウントは、4月から9月の半年の集計結果で判断され、減算となる場合は11月から適用となる。そのため、現時点で適用になってしまう事業所でもまだまだリカバリーが可能である。
居宅介護支援に新設されるのは5%の減算だ。事業所の所在する建物と同一敷地内、または隣接する建物に居住する利用者は、1名から減算。同一建物に居住する利用者が20人以上である場合に適用となる。


(【画像】厚労省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」より)
4,リハビリ、口腔ケア、栄養改善の一体的な提供とLIFE関連加算
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの役割には、「リハビリテーション、口腔ケア、栄養改善の一体的な提供」が大きく位置づけられた。リハビリテーションマネジメント加算、短期集中リハビリテーション実施加算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算、特養での個別機能訓練加算などが対象である。
LIFEが始まって以来、この一体提供は重要度を増してきた。特にリハビリテーションと栄養改善は密接な関係にある。今後は、リハビリテーションに偏ることなく、口腔ケア、栄養改善への取り組みが急務となっている。また、理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する退院後共同指導加算が創設されている。
LIFE関連では、すべての加算のLIFEへの提出頻度が3カ月に一度に統一された。また、LIFE自体も4月10日でこれまでのLIFEシステムが終了した。8月1日から新たなLIFEシステムが稼働する。それまでの4カ月間に提出すべきデータは、8月1日から10月10日の間に、遡って提出することとされている。LIFEが使えないとしても、利用者の評価は必要なので要注意である。
5,介護職員等処遇改善加算と職場環境等要件の見直しと支給のポイント
6月からは、現行の介護職員処遇改善3加算が廃止となり、新たに創設される介護職員等処遇改善加算に一本化される。特例として、24年度末(25年3月)までは、区分Ⅴが設けられて、すぐには新加算の要件をクリアできない場合の措置とされている。事業所の対応におけるポイントは、24年度に2.5%、25年度に2.0%のベースアップとすることである。というのもこの新加算の加算率には、2年分の賃上げ分が含まれているため、6月に移行した段階での加算率は現行の3加算と2月からの支援補助金を合計した加算率より高く設定されている。
この増加分は、6月から前倒しで従業員に支給しても良いし、繰り延べて25年度に支給しても良いことになっている。しかし、繰り延べは2つの問題を抱える。一つは、繰り延べて増額した部分の賃金相当分が26年度以降の加算で補填されないこと。すなわち、26年度以降は自腹となる。2つ目は、繰り延べした部分の収益は24年度の収入となり、法人税の課税対象となることだ。厚生労働省は、この税金対策として、賃上げ促進税制の活用を挙げているが、一般的でない。これらの事情を勘案すると、6月から前倒しでの支給がベストの選択といえる。ただし、例外として、定期昇給を毎年実施している場合に、繰り延べて増額した部分で定期昇給を補填することは有効である。26年度以降は事業者の自腹で昇給を実施することは想定内としても、少なくとも25年度の昇給分を加算で補填できるメリットは大きい。
介護職員等処遇改善加算の算定要件である職場環境等要件では、生産性向上のための業務改善の取組を重点的に実施すべき内容に改められている。それは、業務改善委員会の設置、職場の課題分析、5S活動、業務マニュアルの作成、介護記録ソフト、見守りセンサーやインカムの導入、介護助手の活用などである。この要件は25年度からの適用であるが、小規模事業者にはハードルが高く、特例措置が設けられている。