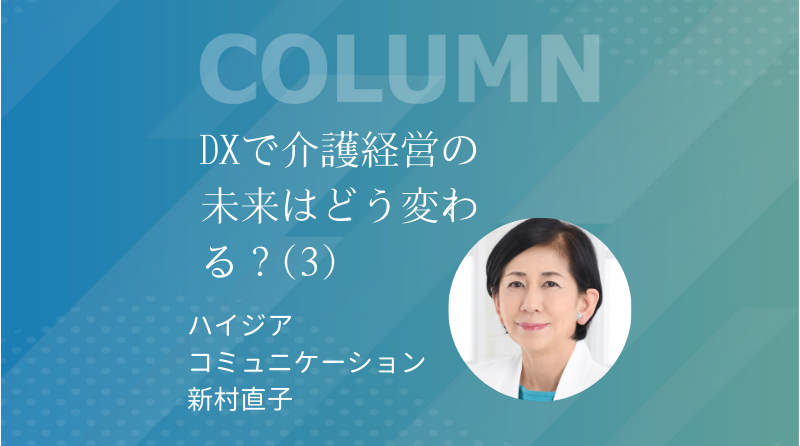介護業界で働く人々と介護事業所をオンラインで繋ぐマッチング事業に取り組み、注目を集めている若手起業家がいます。大学時代に訪問介護事業所を設立し、現在は、株式会社み─つけあの代表を務める洞汐音(ほら・しおん)さん。 「介護にかかわるすべての人を繋ぐ」というコンセプトのもと、難しく見えがちな介護業界の情報をオンライン上でわかりやすく利用者に伝え、介護業界の人材不足を解消するためのマッチング事業に取り組む洞さんに、介護経営の未来像について聞きました。
*連載記事:介護業界のDXを推進するキーパーソンたちに聞く─ DXで介護経営の未来はどう変わる?(1:一般社団法人日本ケアテック協会代表理事・鹿野佑介さん)、(2:社会福祉法人善光会・宮本隆史さん)

【画像】洞 汐音氏
ヘルパーとして現場に飛び込み、非効率な業界の課題に気づく
高校まで米国カリフォルニア州ロサンゼルスで育ち、日本に帰国してから介護領域で起業した経歴を持つ洞さん。若い時から介護に目を向けた理由を尋ねると、「早稲田大学への進学のため日本に帰国し、祖父母が暮らす家に通っていた時に、生活の中で介護が必要となっている局面が見えてきました。自分自身も巣鴨という高齢者が多いエリアに住んでいたこともあり、超高齢社会の日本が抱える介護の課題に関心を持ちました」。
当時、製薬企業でインターンとして働いた経験をもつ友人から、日本の介護保険制度の複雑さや介護職の低賃金問題などについて知らされ、海外と日本の保険制度の仕組みの違いについて調べるように。2016年には、大学時代に自ら訪問介護事業所を設立し、ヘルパーの仕事も経験しました。
介護現場を経験する中で、介護保険制度は3年に1回の改正の度に規約や確認事項が増え、書類仕事が煩雑になりがちであること、そのため書類の作成・管理にも手間がかかり人件費が低く抑えられがちであること、また、運営上ではファックス中心の紙のやりとりや電話での伝達が主流であり、ICT化の遅れが運営の効率化を妨げている事実に気づきます。
そこから、非効率な面がまだある介護業界の運営の仕組みをデジタルトランスフォーメーション(DX)で効率化することで人手不足の課題を解消し、ヘルパーの賃金水準も高めていこうという、現在の起業プランにたどり着いたといいます。
介護を必要とする人、家族に必要な情報が届いていない
「み─つけあ」という社名は、「介護にかかわるすべての人を繋ぐ」というコンセプトのもと、meets(会う)+care(ケア)から名付けました。世界一の高齢化率を誇る日本で、介護ニーズは年々高まる一方。しかし、いざ介護が必要になった時、市町村や地域包括支援ケアセンターなど、介護にかかわる公的機関に迷いなくアクセスできる利用者ばかりではありません。
「まず一般の方にとって、介護保険制度はとても複雑に見えると思います。自分の家族に介護が必要になった時に、どこから情報を探したらいいのか、認定や制度はどうなっているのか、手続きをどうするべきなのか、介護に関する基本的な知識や情報を持っていない方がまだまだ多い。すでに介護保険サービスを利用している方の中にも、例えばケアマネジャーとの相性の悪さを感じているのにもかかわらず、『ケアマネジャーは変更できない』と思い込み、何年も我慢している方もいます。知識のなさから希望する介護を受けられていない方が多いことが、大きな課題と考えました」と洞さん。

そこで、同社はインターネットを通して、介護保険制度や施設に関する情報の提供に取り組み始めます。主力事業の一つは、利用者と介護施設を仲介するマッチング。介護施設を探せるポータルサイト「み─つけあ」では、「介護WEB診断」(上の図参照)と名付けたサイトの入り口から、利用者の介護状態や、家事や買い物などの日常で困っている内容、自宅の郵便番号などを入力していくと、自宅近くで希望するサービスが受けられる介護施設(厚生労働省の介護サービス情報公表システムとリンク)がリストアップされます。
利用希望者はこれを施設選びの参考にできるほか、2021年9月からは、介護に関する相談対応サービス(有料)もスタート。介護福祉士の資格を持つ複数の専門相談員が、現在利用している施設が利用者にとって適切かどうか、より良い選択肢があるかといった相談を受け付けています。相談ツールは電話とLINE。電話相談なら初回は無料で、その後は15分・1000円、LINEでの相談は1件につき最大5往復・1000円で、どのような世代にとっても明快な料金体系となっています。
働き手と事業所とのB to Bマッチングサイトも
2020年4月には、介護の担い手不足の解消のために、介護事業所・訪問介護事業所と非常勤として働く、いわゆる登録介護ヘルパーとを繋ぐマッチングサイト「み─つけあWorkers」を立ち上げました。登録ヘルパーは都合のいい時間のみに働きたいという方にとっては便利な仕事です。
ただ、登録ヘルパーが自分一人で訪問先などの仕事を探すには限界があり、「もっと働きたいのに、登録先の施設の事情で空き時間がなかなか埋まらないという悩みを持つヘルパーさんが多い」と洞さんは指摘します。こうした働き手は、み─つけあWorkersを活用することで希望の時給と場所(市区町村)、募集概要から検索して、働ける場所を探すことができます。面接に行く度にヘルパーには、交通費などの支援金として3,000円も支払われます。一方、事業所は1件33,000円という面接課金のコストのみで、その時間帯に必要な働き手を効率よく確保できることから、採用コストを従来の約4分の1(同社の顧客事業所ヒアリングから推定)に抑えられるといいます。
面接に至る前から、応募者と事業所が電話などで何回でも条件について確認の連絡ができることから、「面接での成約率は9割以上と好調」(洞さん)で、登録事業所数はすでに700社超(2022年1月現在)となりました。
ヘルパーの空き時間をリアルタイムで把握、機会損失を軽減

事業所にとっては、「働き手の確保のみならず、ヘルパーのスケジュールをリアルタイムで管理できることも大きなメリット」と洞さんは話します。登録ヘルパーを多く抱えている訪問介護事業所では、ヘルパーのスケジュール管理が必須。しかし、紙と電話での管理には限界があり、手間を掛けてヘルパーにヒアリングしてスケジュール表を毎週更新したとしても、「先日は空いていたヘルパーのスケジュールが、問い合わせた時点ではもう埋まってしまっていた」という例も少なくありません。
こうしたヘルパーのスケジュール管理をオンライン上で行うことで、事業所側はリアルタイムで最新の稼働可能なヘルパーの空き時間情報を入手できます。「電話での最終確認は必要ではありますが、み─つけあWorkersのヘルパースケジュール(上の図参照)を活用することで電話をする回数は減らせますし、空き情報の精度が高いのが利点」(洞さん)。そのため、仕事の依頼があった際や、急遽人員交代が起きた場合でも、その時点で稼働可能な候補の選定を速やかに行うことができ、営業機会を損失することなく売り上げを伸ばせるといいます。
現在、み─つけあWorkersの登録ヘルパーは2500人(2021年末時点)。これを、「団塊の世代が後期高齢者になる2025年には13万人に増やしていきたい」と洞さんは話します。日本生産性本部などが中心になって発足した政策提言組織・日本創生会議は、2025年に東京都、神奈川、千葉、埼玉県の首都圏で13万人の介護難民が発生すると試算。この数字は同社が目標とする13万人とも符合しますが、13万人のヘルパーを集めるための秘策はあるのでしょうか。
「み─つけあWorkersの活用により、ヘルパーさんたちの隙間時間がスピード感をもって埋められるようになれば収益源・収入が自ずと増えていくので、ヘルパーの方にとって魅力は大きいはず。また、すでに働いている登録ヘルパーさん以外に、介護に関する資格を持ちながらも、現在は他業種で働いている潜在的な働き手がいます。こうした方々の労働意欲の掘り起こしにも繋げたいと考えています」。
ヘルパーの空き時間を活用したC to Cマッチングも稼働へ

同社は、み─つけあWorkersで入手できるヘルパーの空き情報を活用した次の一手にも着手しています。それが、家事支援や配食、フィットネス、移送・送迎といった介護保険外サービス(自費サービス)市場において、ヘルパーが利用者と直接やりとりしてサービスを受託できるC to Cマッチング事業です。
「利用者は、ヘルパーの保有資格や依頼可能な事項を確認した上で、ヘルパーを自分で選択して、生活の困りごとなどのサービスを依頼できます。ヘルパーにとっては、保険適応内サービスに加え、自費サービスの仕事を受託できるチャンスが広がり、働き方の選択肢や収入源の増加につながります」(洞さん)。2022年1月から、すでに都内一部エリアで試験的運用を開始。同社はこのビジネスモデルにより、2026年度中に4億5,000万円の売り上げを見込んでいます。
利用者と介護施設、介護施設と登録ヘルパーのマッチングに続き、利用者とヘルパーのダイレクトなマッチングをDXで促進していくことで、介護を必要とする人と、介護施設、働き手がもっと自由に出会えて、介護保険制度の枠組みを超えてもっと柔軟に介護の困りごとを解決できる社会をつくる──。それが、洞さんが描く介護経営の未来像と言えそうです。
1993年生まれ。米国カリフォルニア州ロサンゼルス出身。2016年3月、早稲田大学国際教養学部卒。大学在籍中に株式会社み─つけあの前身である株式会社BayCareを創業。訪問介護事業所を設立する。介護ヘルパーの資格を取得後、ヘルパーとして現場で働いた経験を生かし、2019年、利用者と介護事業所を繋ぐポータルサイト「み─つけあ」を立ち上げる。同年、社名も「株式会社み─つけあ」に変更。2021年5月、アジア各国で活躍する30歳未満の起業家やリーダーたちをノミネートする『Forbes 30 Under 30 Asia 2021』のヘルスケア&サイエンス部門に選出される。