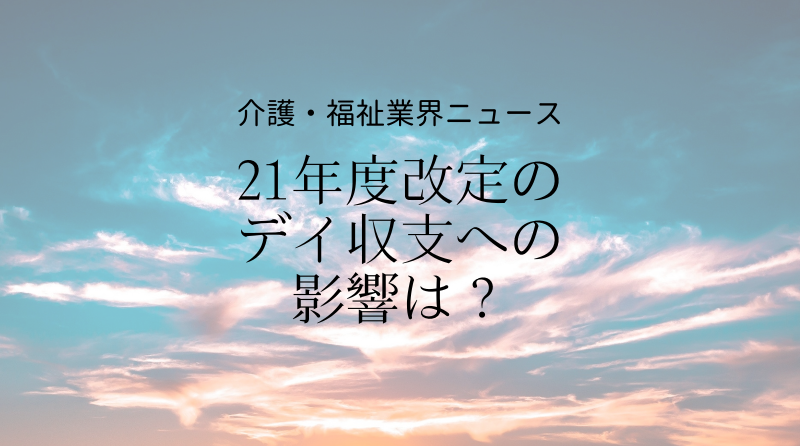2021年度介護報酬改定による影響を確認すると、感染症等により利用者数が減少した場合の措置として新設された報酬上の対応(基本報酬の規模区分変更の特例、または3%加算)を行った通所介護事業所は約3割程度に留まりました。
また、新設された入浴介助加算(II)の算定率は低く、同加算(I)の減算によるマイナス影響を訴える声が挙がっています。
以前ご紹介した福祉医療機構の調査結果をもとに、通所介護事業における報酬改定の影響を読み解きます。
*関連記事:LIFEの利用状況、サービス種別間で格差―登録率は老健がトップ
調査と回答者の概要
本アンケートは、福祉医療機構の貸付先のうち、介護保険法に基づくサービスを実施する 5,701法人を対象にWeb上で実施されました。
・アンケート実施期間:2021年7月29日から同8月25日まで
・アンケートへの回答総数:1,446法人(社会福祉法人は71.4%、医療法人は15.3%、営利法人は10.3%)
・アンケート回答率:25.4%
このうち、通所介護の回答者における事業所規模別の構成は、2021年度の事業規模で「通常規模型」71.7%、「地域密着型」が23.4%であり、20年度とほぼ同様でした。

【画像】WAMの2021 年度介護報酬改定に関するアンケート調査詳細(通所介護)より抜粋(以下、同様)
2021年度介護報酬改定が通所介護の収益に与えた影響
通所介護は特例措置により、感染症等の影響で利用者数が減少した場合に基本報酬の3%加算または規模区分の変更(大規模型のみ)による対応が認められています。
しかし、アンケート結果から見えた実際の対応状況では、約6割から7割が「いずれの対応もしていない」と回答。何らかの対応を取った事業所の割合は約3割に留まりました。

▲感染症等で利用者が減少した場合の報酬上の対応
前年同時期比のサービス活動収益・事業活動収益の変化を見ると、いずれの事業規模の事業所も「減少」と答えた割合がもっとも高く、事業規模が大きくなるにつれ「減少」の割合が高くなる傾向が見られました。

▲前年同時期比サービス活動収益・事業活動収益
利用者一人当たり収益単価は「横ばい」と答えた法人の割合が高く、利用率の変化についてはすべての事業規模で「低下」と答えた割合が高い傾向がみられました(直近の平均利用率は69.3%)。

▲前年同時期比利用者一人当たり収益(単価)

▲前年同時期と比べた利用率の変化
コロナ禍による利用控え、風評被害、自粛、クラスターの発生をはじめ、ワクチン接種後の副反応による本人や家族の体調不良が原因でサービス利用をしなかったケースが増えたことが一因と考えられます。
入浴介助加算の算定状況と現場の声
入浴介助加算は2021年度介護報酬改定にて、医師等が利用者宅を訪問し、個別入浴計画を策定する等の要件を満たすことで算定できる加算(II)が新設されました。その一方、これまでの要件のまま算定可能な同加算(I)は10単位の減算となっています。
入浴介助加算(II)の算定率は低迷
アンケート調査によると、実際の算定状況は加算(I)のみを算定している割合が 71.0%ともっとも高く、加算(I)・(II)いずれも算定している事業所はわずか11.0%、加算(II)のみ算定の事業所は10.5%と、新設された加算(II)を算定した事業所はわずか2割程度に留まりました。

加算(II)を算定していない理由としては、「算定要件(利用者宅の状況に近い環境で入浴介助を行う)を満たすことが難しい」が 25.9%ともっとも高く、次いで「算定要件(利用者宅を訪問)を満たすことが難しい」が 24.3%との結果が出ています。

通所介護サービス利用者の中には、自宅での入浴が困難である機械浴の利用者等も多く、自宅での個浴を前提とする算定要件がネックになったことが考えられます。
現場からは事務作業の負担増、入浴介助加算の実質減に対する不満の声も
今改定に関する自由意見では、「入浴介助加算の(I)の引き下げは職員の労力を考えると残念。かといって加算(II)はかける時間と加算額が見合わない」など、従来の要件が引き継がれた既存の要件で算定可能な同加算(I)の単位数が引き下げられたことに対するへの不満の声が目立ちました。
また、「加算取得のための事務量が年々増えており、誰のための何の仕事をしているのか見通しが立たない」など、加算の取得にかかわる事務作業量の増加が大きくのしかかっている現状がうかがえます。
深刻な人手不足が懸念される中、現場の働き手に寄り添える仕組みの構築が課題となるでしょう。