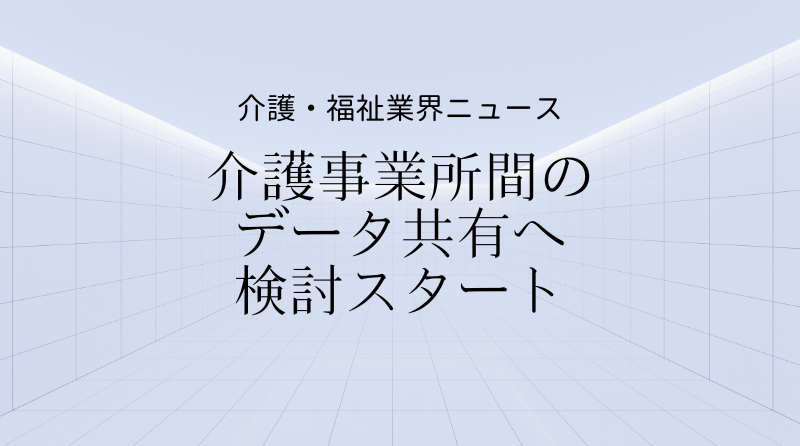介護事業所や施設、医療機関の間でどのような情報の連携を進めていけば業務効率化やサービスの向上に資するのだろうか―。9月に立ち上がった会議で、厚生労働省が問いかけました。
科学的介護情報システム(以下・LIFE)やケアプランデータ連携システムの今後の開発やそれらとの接続も視野に入れながら、意見交換が行われています。介護サービス事業では、多様で複雑なニーズへの対応が求められます。その中においてもデータ活用やICT化を進めていくためにどのような情報整理が必要であるかといった検討や合意形成が進んでいくことになります。
データヘルス改革の方向性と介護情報の利活用
現在、医療や介護、保健分野を含むヘルスケア領域では、データの利活用によってサービスの質や効率、利便性を向上させようとする施策(データヘルス改革)が進んでいます。
具体的には、
- サービスの利用者が自分の保健医療情報に自由にアクセスできる仕組み(日常生活の改善や受診時などで活用)
- 医療機関などが施設や業態の枠を超えて患者の情報を共有する仕組み
の構築などが進められているところです。
これまでは、自身の健診情報や過去に処方を受けた医薬品の情報などが閲覧できる仕組みの構築が先行して進んできました。
国は、こうした保健医療情報の活用範囲を広げ、電子カルテ等の医療・介護全般にわたる情報を共有・交換することができる全国的なプラットフォームを実現する方針を掲げています。患者や利用者の情報は、保健医療従事者だけでなく将来的に介護事業者などとも共有することが想定されています。
そこで、12日には、介護分野に焦点を当て、情報共有や利活用に関して集中的な検討を行うためのワーキンググループが立ち上げられました。
(参考:第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ資料)
介護分野のデータの利活用の工程表とワーキンググループの検討事項
介護分野におけるデータの利活用を巡る政策としては、主に以下の3つの取り組みが進められているところです。
- 利用者自身が介護情報を閲覧できる仕組みの整備
- 介護事業所間等において介護情報を共有することを可能にするための取組
- 科学的介護の推進

(画像:健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第1回) 資料より。以下同様。)
このワーキンググループでは、2番目のテーマを優先的に取り上げ、介護事業所間における介護情報の共有や、医療機関との情報共有も視野に入れたデータの標準化などについて検討を進めます。 スケジュールとしては、「2023年度中までに全国的に介護記録支援システムの情報を含めた介護情報を閲覧可能とするための基盤のあり方についてIT室(デジタル庁)とともに検討し、結論を得る」予定です。
初回の会合となったこの日、厚労省の担当者は、「どういった情報を共有すべきか、どういった情報を標準化していくことなどが考えられるか」について構成員に検討を促しました。まず、介護情報の中で共有すべきコンテンツについて中心に議論を進め、政府全体の動きも踏まえながら、情報の共有や活用をすすめていくためのツールや手法を考えていくという道筋を示した格好です。
「ケアプランデータ連携システム」も検討事項の範囲に
ワーキンググループでの検討に当たり、厚労省は介護サービスの利用者を巡る情報の種類や流れなど、現状について資料をまとめています。



ここで共有されたのは、
- サービス提供のために収集されている情報の全てが利用者に還元されてはいない
- 各データの作成主体・保有主体によって持っている情報が異なる
- 記録や交換の形式について、電子的に集めているか紙媒体であるかさまざまである
といった状況です。
なお、9月6日には厚労省が別途、「ケアプランデータ連携システム」の概要が事務連絡で示されていますが、このシステムの活用や普及についても同ワーキンググループの検討事項に予定されています。
「小規模事業者が参画できる仕組みを」介護のデータ連携を進めるための観点
厚労省はこの日の会合で、介護分野の情報連携を進める上での留意点として以下も挙げています。
- 医療における「治療効果」のように、関係者に共通のコンセンサスが必ずしも存在していない
- 利用者やその家庭などにおいて様々なニーズや価値判断が存在し得る
- 科学的に妥当性のある指標等が確立していない場合があること
厚労省からの論点の提示に対して、構成員からはこの日、以下のような意見などが示されました。
- LIFEで収集されたデータを活用するには、どういった状態の利用者にどういった介入・ケアを行い、それによってどんな結果が出ているか、情報がつながっていることが重要。今後、ケアプランなどに記載するケアの内容にコード付与を進めていくのであれば、それに伴うLIFEでのデータ入力等も視野に入れて検討してほしい。
- 施設入所者と在宅生活者へのサービス提供や情報の流れには違いがある。施設は基本的にワンパッケージである程度情報共有しやすい環境にある。一方で、在宅サービスの場合は、情報の流れが複雑かつ多岐にわたることに留意して検討を進める必要がある。
- 小規模事業者が参画できる仕組みづくりが重要なポイントである。