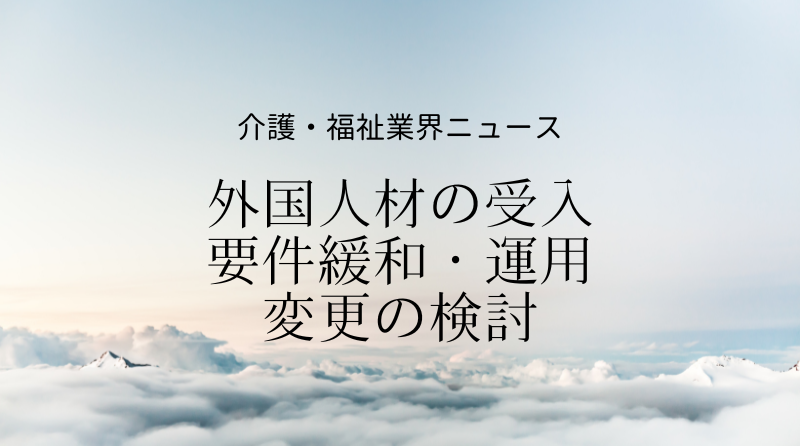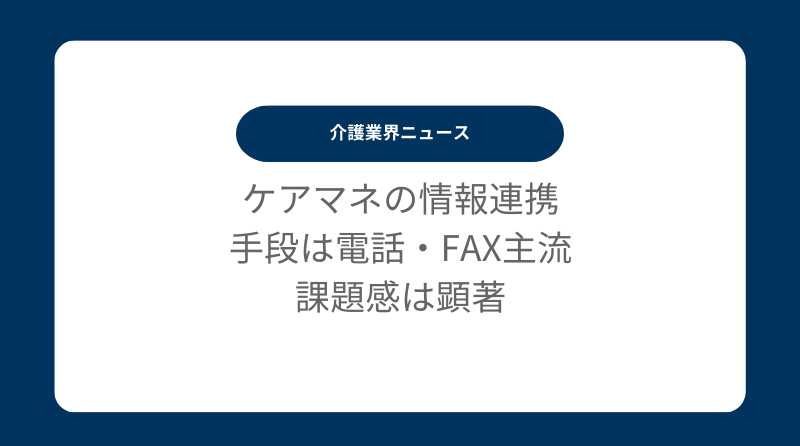現在、外国人材の受け入れに関する規制緩和に向けた検討が進んでいます。
これに伴い、訪問介護事業所での外国人の就労を認めるかどうかなど、技能実習制度や特定技能制度をどのように見直し介護業界で運用するかについて意見が交わされました。
直近の検討状況についてお伝えします。
外国人材受け入れに関する今後の政府方針とスケジュール
中小・小規模事業者を中心に深刻化が進む人手不足を背景として、政府は現在、「技能実習制度」と「特定技能制度」の見直しを進めています。
両制度の見直しに向けては、一定の方向性が既に示されています。その概要は以下の通りです。
- ”途上国への技術移転”や”国際貢献”を名目とする現行の技能実習制度を廃止し、人材確保と人材育成(未熟練労働者を一定の専門性や技能を有するレベルまで育成すること)を目的とする新制度を創設する
- 2019年に創設した特定技能制度は、適正化を図ったうえで引き続き活用する
2つの制度の関係を整理すると、外国人材は、技能実習制度廃止後に創設される新制度を通じて一定の専門性や技能を身につけ、その後の就労で使う制度は特定技能制度に移行することになります。
この新たな制度への移行を前に有識者会議が現状の課題などを整理し、2023年秋ごろを目途に関係閣僚に向けた提言をまとめる予定です。

(【画像】日本での就労が認められる在留資格の一覧表 (第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会資料2より))

(【画像】技能実習制度や特定技能実習制度の見直しに向けたスケジュール (第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会資料2より))

(【画像】技能実習制度・特定技能実習制度の見直しの方向性 (第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会資料2より))
厚労省はこのスケジュールにのっとり、両制度の介護領域固有の要件について検討するための会合(外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会)を7月末に初開催しました。

(【画像】外国人介護人材の受け入れの仕組み(第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会資料2より))
外国人介護人材受け入れの仕組みの見直しに向けた3つの論点
技能実習制度と特定技能制度の見直しに向け、厚労省は介護分野で検討しておくべき事項を3つこの日の会合で示しました。
- 訪問系サービスで今後、技能実習生や特定技能の在留資格を持つ外国人の従事を認めるかどうか。
- 技能実習生の受け入れは設立後3年を経過している事業所にしか認められていないが、新制度ではこのルールを見直すかどうか。
- 技能実習生らは、
①就労開始後6カ月が経過した場合
②日本語能力試験のN2またはN1に合格している場合
のどちらかの場合に人員配置基準への算定が認められているが、この取扱いについてどう考えるか。検討会の構成員からは議題のほかに、当日の会合では既に外国人材を受け入れている施設から人材定着につながる施策の実施など要望があがりました。
1.訪問系サービスなど外国人の受け入れ対象サービスの拡大について
訪問介護などのサービスは、適切な指導や監督体制をとることが難しいことなどから、技能実習生の受け入れが認められていません。
有識者からは、このルールをすぐに改めるべきという意見はありませんでした。
ただし、サービス付き高齢者向け住宅などでの受け入れについては前向きな検討を促すべきとする声もありました。代表的な指摘や意見は以下の通りです。
- 訪問系サービスは、利用者に対して一対一でサービス提供するのが基本。適切な指導体制や人権擁護、在留資格の管理など疑念事項が払拭できないまま緩和を進めるのは難しい。利用者宅での生活援助サービスに適切に対応できる能力も必要であり、慎重な判断が必要。(今村文典構成員/日本介護福祉士会・副会長 )
- 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅は、介護保険施設と労働環境の違いが少ないため、受け入れ対象施設に含めて問題ない。(富家隆樹構成員/日本慢性期医療協会常任理事 )
- 訪問入浴については緩和の方向性で検討を求めたい。(斉藤正行構成員/一般社団法人全国介護事業者連盟理事長)
2.技能実習生の受け入れを事業開設後3年以上とする要件について
こちらも、外国人材の受け入れ対象を拡大するかどうかという論点です。
経営が軌道に載っていない施設では適切な指導体制が取れないという懸念から、現行ルールではで技能実習生を受入れは、開設後三年以上経過している事業所となっています。
この運用は見直す余地があるというのが事業者や専門職を代表する構成員から複数ありました。
- 適切な指導体制が確立できていれば、必ずしも要件として扱う必要はない。ただし適切な指導体制を確認する手段や基準を整理する必要性がある(今村構成員)
- 複数の事業所を持つ医療法人や株式会社であれば、外国人材を受け入れる事業所が新設間もなくとも、経営が安定しているかどうかや教育体制が確保できているかを確認することが可能。受け入れ可能とするかどうかの基準は、法人単位とするべき(富家構成員)。
- 制度の趣旨を踏まえて安易に配置基準を緩和すべきではない。他の介護職員の負担増や、サービスの質の低下、利用者の安全確保、専門性の向上への妨げへの懸念から慎重な対応を求める。(松田陽作構成員/連合総合政策推進局生活福祉局次長 )
3.外国人介護人材と配置の算定基準について
受け入れた人材をどの段階で人員配置基準に算定できるかどうかについては、特に日本語要件について意見が集まりました。なお、特定技能1号の人材(入国時に技能と日本語能力を確認)は、就労と同時に配置基準への算定が認められています。
- 技能実習制度を廃止して創設する新制度で基本的な扱いがどうなるかによって、介護領域固有の日本語要件についても見直すことになる。多面的な視点で議論を進めたい。(斉藤構成員)
- 技能実習生について、給与が発生している以上入職すぐに算定を認めて構わないのではないか。(富家構成員)
- 日本語要件は同水準の試験に合格していても個人差が大きい。人材確保のためには、厳格な日本語要件は逆に足かせになるのではないか。(富家構成員)
- 外国人材が日本で働き生活する上では一定水準以上の日本語能力が必要。実習制度が廃止された後も、外国人介護人材に求められる日本語能力については条件を緩和することのないように求めたい。(松田構成員)
外国人介護人材の受け入れに関するその他の要望や指摘事項
厚労省から示された3つの論点以外にも、多様な意見がありました。その一部を紹介します。
- 外国人材の受け入れについて、踏み切れない施設ではどのようなことを課題に感じていて、既に外国人材を受け入れている施設では悩んでいるのか意見を共有すべき。
- 実際に働く外国人材や利用者の意見についてデータを示してほしい。
- 日本人と同等以上の処遇を担保する方策を確立する必要がある。
- 障害福祉の領域における受け入れルールも整理・検討してほしい。
- 受け入れルートが複雑になりすぎている。できるだけ集約して欲しい。
- 地方での就労を促す方策を検討してもらいたい。