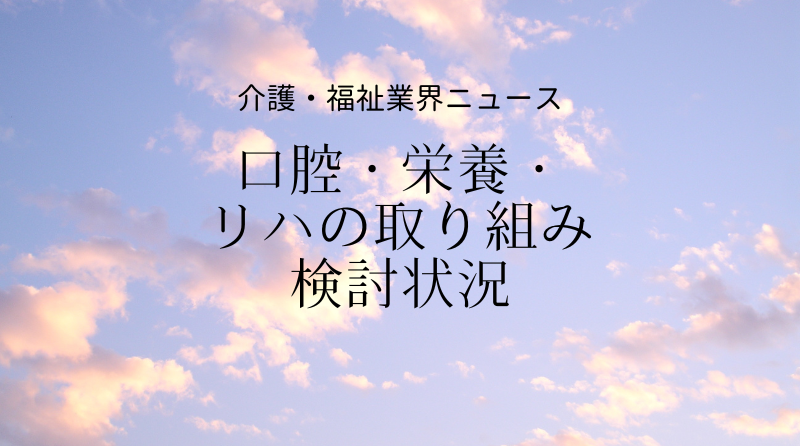先日、2024年度介護報酬改定に向けた今後の検討テーマ(基本的な視点)が整理されました。
たくさんのキーワードが散りばめられている中で、「自立支援・重度化防止に向けた対応」として、「リハビリテーション・口腔・栄養の一体的取り組み」が明記されています。
今後、何らかの形で報酬上のインセンティブが検討されるテーマになるでしょう。ここまでの検討状況をまとめました。
2024年度介護報酬改定に向けたリハと口腔・栄養巡る論点
リハビリテーションや口腔、栄養へのアプローチは、自立支援や重度化防止への効果が期待できるとして、2021年度介護報酬改定でも一体的な取り組みを行うことの重要性が示されてきました。それに伴い、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士らとの連携が促されています。
24年度改定でより一層の取り組みを進めるため、本テーマが議題となった9月の会合で厚労省は以下の論点を示していました。
(口腔)
◼歯科専門職と多職種の連携をさらに促し、必要に応じて利用者に口腔に係る管理や歯科治療を提供するために、どのような方策が考えられるか。
◼栄養管理の必要な利用者が、在宅・高齢者施設・医療機関のいずれの場においても、必要なケアを受けることができるよう、医療機関の連携を充実させる等の観点からどのような方策が考えられるか。
(リハ・口腔・栄養)
◼リハビリテーション・口腔・栄養の一体的取組をさらに推進するため、どのような方策が考えられるか。
何らかの問題がある利用者 口腔で60%・栄養で40%超
これまでの介護報酬改定では、口腔・栄養管理を促す各種加算の創設や見直しが行われてきました。先述の通り、21年度介護報酬改定でも、歯科衛生士や管理栄養士ら専門職の介入に対する評価などの見直しが実施されたところです。
しかし、厚労省が提示した介護現場における調査結果からは、口腔・栄養管理の重要性が十分に認識されていなかったり、各専門職や医療機関への連携が不十分であったりといった課題が伺えます。
例えば、歯科医師が歯周病の管理が必要と判断した高齢者の割合は、通所サービス利用者では22.6%、在宅療養者で31.4%であったものの、実際に歯科医療を受けた割合は、通所サービス利用者では8.1%、在宅療養者が2.3%に留まっています。

(【画像】第224回社会保障審議会介護給付費分科会 資料3より(以下同様))
また、認知症対応型共同生活介護において、歯科治療や口腔清掃が必要な状態の利用者がいるにも関わらず、利用者の54.0%は定期的な口腔アセスメント及び歯科衛生士による口腔衛生管理を受けていない現状を明らかにしました。

さらには、通所サービス事業所において、口腔や栄養に問題がある利用者のいる割合が、口腔で60%以上、栄養で40%以上との結果も公開しています。
約4割のケアマネが口腔情報を取得せず―現場への意識付けが重要
厚労省は、介護現場において歯科医師や歯科衛生士等が限られている現状についても調査結果を示しています。
具体的な数値をみると、歯科衛生士が常勤または非常勤でいる介護保険施設の割合は、介護老人福祉施設が7.7%、介護老人保健施設が13.8%、介護医療院が12.2%、介護療養型医療施設7.4%と、いずれも少なくなっています。

委員からも専門職の確保や配置の難しさにかかわる意見が目立ち、医療機関・歯科医療機関との連携強化や、専門職の介入へのインセンティブ強化、人員配置基準等への対応などを求める意見があがりました。
NPO法人高齢社会をよくする女性の会の石田路子委員は、「利用者の立場からいえば、これほどまでに効果もあり、いい影響があると言われている部分をもう少し進めてほしいというのが強い願いだ」と述べ、「専門職が関わることで効果があがるのであれば、加算も含め人員配置も含め、しっかりとした対応を」と提言しました。
日本歯科医師会の野村圭介委員は、利用者の口腔に関する情報提供を行った介護支援専門員が約3割と少なく、約4割が口腔に関する情報を取得していない現状について「ケアマネからの情報提供がまだまだ十分ではない」と指摘。

「介護保険施設への歯科職種の就業人数は少ないため、家族・ケアマネ・介護職種からの依頼があって初めて歯科職種が関与することになる」と述べ、他職種が理解できるスクリーニングや、早めに専門職や歯科受診につなげる仕組みの構築を要望しました。
また、日本医師会の江澤和彦委員は、「歯科医療機関と介護事業所、介護支援専門員との連携体制の構築が不可欠」と言及し、「医療介護従事者が栄養口腔への意識を高め、潜在的なニーズへの気付きを高めること。また、介護支援専門員のケアプラン策定においても、リハ・栄養・口腔への意識を高めていただくようなプロセスを導入することも必要では」と意見を述べました。
介護給付費分科会はこれから、より具体的な制度設計に向けた検討に移ることになります。委員らの意見がどこまで報酬体系に反映されるのか、それによって事業者はどのような対応が求められるようになるのか、注意深く追ってまいります。