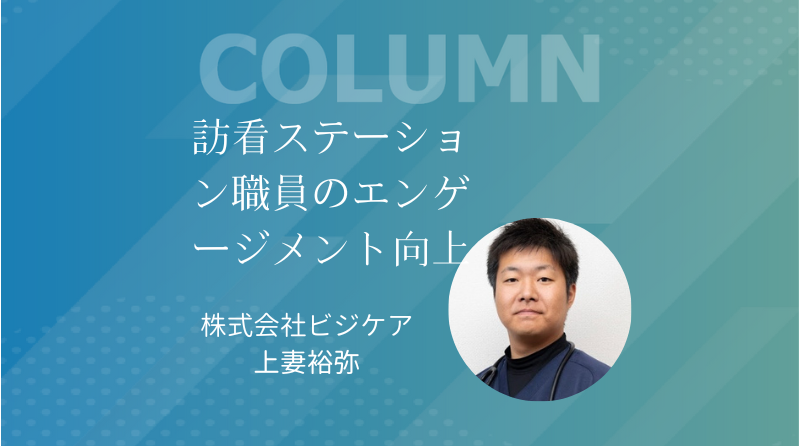前回の「訪問看護ステーションで働く職員のモチベーションの変化」では、独自調査の結果に沿って、訪問看護ステーションが持続的な運営をしていくための方策について述べた。各事業所が自身の特性を理解し、職員がどのような目的をもって入社したり、就労意向を持っていたりするかを把握して、採用と定着に取り組んでいかなければならない。
今回は、従業員の定着をさらに促進するために必要な「エンゲージメント」の高め方について述べていく。
エンゲージメントとは
エンゲージメントとは、一言で述べると企業と従業員の「信頼関係」である。
信頼関係が構築できれば、お互いの必要性が理解でき、ともに成長できて、経営にプラスの影響をもたらすという考え方である。
信頼関係が確立されれば、経営者は働きやすい職場づくりや教育体制の整備など従業員のためにできることを考え、従業員は主体的に仕事に取り組むなど組織に対する貢献の意欲を持つようになる。
モチベーションとエンゲージメントの違い
では、モチベーションとエンゲージメントの違いは何だろうか?
モチベーションとは、職員が働く上での動機づけをいう。
モチベーション―従業員の姿勢や行動を促進する要因―には仕事に対する満足を生み出す「動機付け要因」と職場に対する不満を生む「衛生要因」が存在する(ハーズバーグが提唱している「二要因理論」)。
これに対し、エンゲージメントは環境的な要素に関わらず、従業員が組織に愛着を持ち、主体的な行動を実践している状態を指す。
また、まずモチベーションは自分の中の動機が生まれ、それが行動につながっていくのに対し、エンゲージメントは「事業所のために貢献する」というように、周囲に対する働きかけを意識して行動しようという意欲を指す。
企業と従業員の信頼関係に話を戻すと、両者の信頼関係は以下の2つの軸を基に構築される。
●セルフモチベーション(自発的に自らを奮い立たせる力)
●コミットメント(事業所目標と個人目標をシンクロさせ能動的に行動しようとする力)
経営者や管理者は職員一人ひとりのビジョン達成のサポートを
経営者の中には、「職員に説明しているのにいうことを聞いてもらえない」といった悩みを持つ方も少なくはないのではないか。
しかし、経験が一方的に理念や事業計画・目標を職員に説明したからといって、事業が円滑に進むわけではない。なぜならばそこには職員の個人目標が反映されていないためである。
職員が動かないということは、エンゲージメントが低く貢献意欲を持って主体的に動くことができない状態だ。
そのため、信頼関係を構築する2つ目の軸に述べたコミットメントを意識して、事業所側が職員それぞれのビジョン達成に向けてサポートする役割が必要となる。
訪問看護ステーションの職員のエンゲージメントを向上させる4つの段階
エンゲージメント=個人と企業をつなぐ信頼関係だというだけあって、すぐに経営にプラスの効果が生まれるわけではない。エンゲージメントを向上させるために大事な事はそのプロセスである。
甲南大の北居明教授によると、エンゲージメント向上に向けた過程では、下記の段階をたどる。
第一段階・・・期待の明示
第二段階・・・貢献の実感
第三段階・・・帰属の意識
第四段階・・・成長の実感

【1】期待の明示
はじめに企業は職員に対して期待していることを明確に伝えることが必要だ。既に数年働いている職員らに対しては、個人のキャリアを振り返った上で明示する必要がある。例えば、どこが成長しているか、課題になっているところはどこかなどを伝えよう。
【2】貢献の実感
次に職員には「自分が企業に貢献できている」といった実感を持ってもらわなければならない。期待していることを明示した後、職員が行動を移したことに対するフィードバックである。日頃から実施している面談を、この貢献を実感してもらうための機会としよう。
【3】帰属の意識
帰属の意識とは、「私はここにいてもいいんだ!」「私の意見も尊重される」といった職員の仲間意識である。企業の業績に貢献するために必要な意識だ。
ただ、企業によるこの「帰属の意識」へのアプローチは難しくなってきている。なぜならば、多様な働き方(訪問看護で例えると直行・直帰を導入している事業所など)や、ICT化が進むことでオフラインでのコミュニケーションをとらずとも、情報収集や指示・伝達ができるようになっていることから企業と職員の交流が少なくなりつつあるからだ。
また、業界特有の要素として、職員は国家資格を持つため働き場所に困らず、忠誠心はいだきにくい。
特に看護師が退職を希望する理由は「他の職場への興味」が年齢を問わず多い。(日本看護協会 広報部 2019 年 11月18日)
【4】成長の実感
最後に成長の実感である。
訪問看護事業の経営者からは、「成長すると職員が独立してしまう」という声を耳にすることがある。そのような事態が起こる背景としては、4つの段階がしっかりとたどれていない可能性がある。
一方的な教育だけ行っても、主体的な行動促進には繋がらない。また、帰属の意識がなければ企業への貢献意識なども意識付けしにくい。そのため、成長の実感を得てもらうアプローチは最終段階に位置付ける。
職員のエンゲージメントを高めるための姿勢・考え方
エンゲージメントを高めるアプローチは、業績向上の土台となるものであり、即効性のある効果を求めるものではない。波及効果として最後に業績とリンクすることが期待できるものである。
訪問件数や売上げ、ラダーといったKPIでの評価ではなく、「友達を従業員として企業に紹介できるか?」「自分の意見は尊重されているか?」「親友と思えるような職場仲間はいるか?」などといった定性的な評価でその高さを測ることができる。それぞれの職員にとっての「働く意味」と言い換えることができる。
また、各企業が求める人物像があるため、それぞれで異なる指標の設定が必要だ。さらに企業が求める人物像に沿っているかどうかで評価の度に指標も更新していかなければならない。
エンゲージメント向上へのアプローチは、プロセスを守ることと職員との信頼関係を焦らずゆっくり向上していくことが大切である。