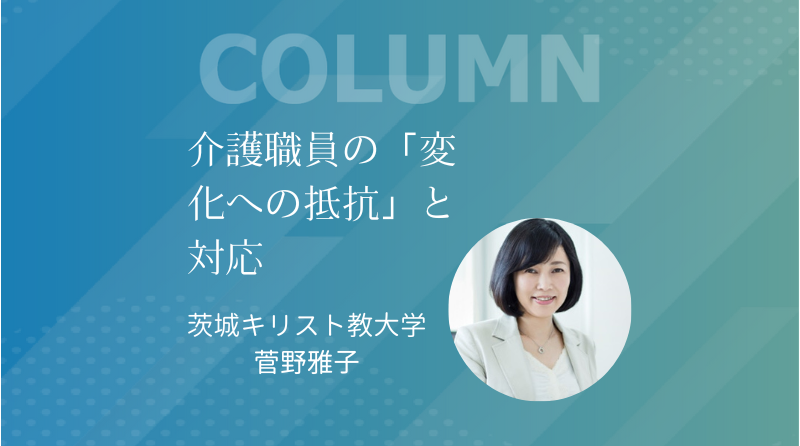このシリーズでは、現場のリーダーや管理者からよく聞かれる悩みを題材に、介護現場で起こりやすい人材問題とその対処法について検討してきました。
最終回は、「変化への抵抗」です。今回は、特養のフロアリーダーEさんの悩みについて一緒に考えてみましょう。
(事例は、筆者が見聞きした実話を題材にしたフィクションです)
フロアリーダーEさんの悩み:「職員が現状から変わることを嫌がります」
Eさん:「職員は現状から変わることを嫌がりますね。これまでやっていた仕事の流れが変わるとか、新しい機器を使ってみましょうとか、新しい介護技術を取り入れてやってみましょうとか、いろいろあるんですけど、やはり嫌がる人が多いですね」
そう語るEさんは、現在の特養で介護の仕事をアルバイトから始めて、2年目に正規職員に転換し、5年目にはフロアリーダーを任されるまでになりました。フロアリーダーとしては3年目となります。
Eさん:「これまでのやり方を変えるということは、やはり、一時的でも負荷がかかりますよね。“ただでさえ忙しいのに、これ以上何かやらなきゃいけないんですか?”という感じで抵抗する人が多いんです」
Eさん:「“では、なぜ今そういうやり方をしているの?”と聞くと、“前からやっているから”という方が結構多いんです。」
「もっと疑問を持って、人に聞くとか、調べるとか、勉強してほしいと思いますね。本来なら自分たちで現状に疑問を持って変えていこうという姿勢を持って欲しいんですよ」
Eさんは、語気を強めてそう言います。
環境変化のスピードが速く不確実性が高い現代において、組織も個人も、いかに変化に対応するかが問われています。
もちろん介護の現場も、例外ではありません。法改正や新たな政策への対応、介護ニーズの高度化・複雑化・多様化への対応と同時に効率化や生産性向上の要請への対応、さらにICTやAIなどの積極的な活用やコロナ禍への対応など、諸々の環境変化に対応していかなければなりません。
組織の変革には抵抗がつきもの
Eさんが言うような変化への抵抗は、介護の現場に限らず、どこの組織でも生じる問題です。
自分がこれまでやってきたやり方が変わるとなると、①せっかく慣れてうまくできるようになったことが、一からやり直しになるという不安感、②今までやってきたことを否定されたような気持ちになる否定感、③新たにすべきことに対する負担感や恐れ、などいろいろな抵抗要因が生じます。誰しも、「これまでの価値観」や「いつものやり方」に固執してしまいたくなります。
今までのやり方で成功体験があるほど、変わることへの抵抗は大きくなるとも言われています。
組織学習の研究では、すでに時代遅れになっているにも関わらず、熟練の人間が成功体験をもとに、今までのやり方に固執してしまうような状態を「熟練化された無能(Skilled incompetence)」と言います。長年それでやってきたという熟練者の自信や成功体験は、必要な変革を妨げることにもなり得るということです。
介護の現場でも、古くからいるベテラン職員ほど、新しいことを受け入れようとしないという話をよく耳にします。
管理者やリーダーは、変わることの意義をわかりやすく自分の言葉で伝える
それでは、一体どう変革を進めていけば良いのでしょうか?
まず、会社の方針や戦略として何かを変えなければならない場合について考えてみましょう。例えば、新しいICTシステムを導入するとか、新しい人事制度を導入するなど、様々なケースがあると思います。
そのために、何か作業が追加されるとか、あるいはこれまでの考え方ややり方を大きく変えなければならない、といったことが生じるとしましょう。
人は他人から言われて何かをやらなければならない時ほど、そして変化の程度が大きく、なぜそれをしなければならないのか腑に落ちていない時ほど、防衛的反応をとるものです。
そのような防衛的反応をできるだけ抑制するためには、なぜ今変える必要があるのか、その意義や有用性を丁寧に伝えることが重要になります。
トップがそうしたメッセージを発信すると同時に、中間層(管理者やリーダー)がそれを咀嚼して現場での変革を主導するという、トップとミドルの連携が重要になります。
現場の管理者やリーダーは、間違っても「会社の方針だから」とか「決まったことだから」というような他責化の言葉を発してはいけません。自分の言葉で、自らの意図や思いとして、変わることの意義・有用性を伝えるという姿勢が必要になります。
意思決定のプロセスに現場を巻き込む
もう一つ考えたいのは、意思決定のプロセスにいかに現場を巻き込むかです。
利用者の最も近くにいて、利用者のこと・現場のことを一番わかっているのは現場のスタッフです。利用者本位の介護を実現するには、やはり現場の知見や情報が何より重要になります。そうなると、「参画型」または「権限委譲型」のマネジメントが有効に機能することが期待されます。
「参画型」は、あくまでも主導するのはトップで、現場の職員の声を聞きながら進めるというスタイルです。一方、「権限委譲型」は、意思決定の権限と責任そのものを現場に下ろすというスタイルです。
どちらが望ましいかは、トップのマネジメントスタイルや変革のレベル、メンバーの成熟度等によっても異なるので一概に言えませんが、少なくとも、現場の声を聞いたり現場での議論を大切にしたりするという「巻き込み」を図ることは重要だと言えるでしょう。
意思決定のプロセスに現場を巻き込むことによって、決定事項が自分ごととなり、変革がスムーズにいくという効果が期待できます。また、変革を実現するためにどのような組織的サポートが効果的かという点も、現場目線で実効性のある方策をとることができます。
利用者本意という原点に戻る
先述のように、変革には抵抗がつきものです。意見が分かれてうまくまとまらないこともあるでしょう。対立や争いが生まれることもあるかも知れません。
そんなとき、一体何のために変えることが必要なのか、ということを改めて問い直す必要があると言えるでしょう。
“利用者本位”という原点に戻り、利用者にとって良いことは何なのかという視点で多面的に情報収集したり、考え直したりしてみると、方向性が定まることも多いのではないでしょうか。
“利用者本意”という軸にブレのない組織づくりができるのが、介護事業の強みであり、変革の推進力になると言えるのかも知れません。