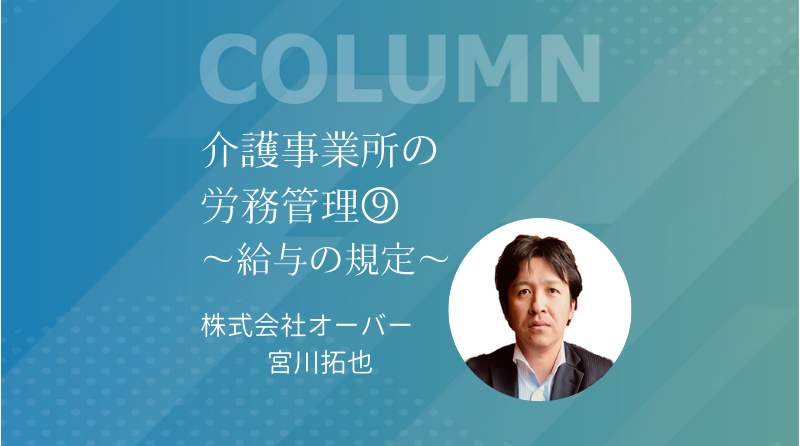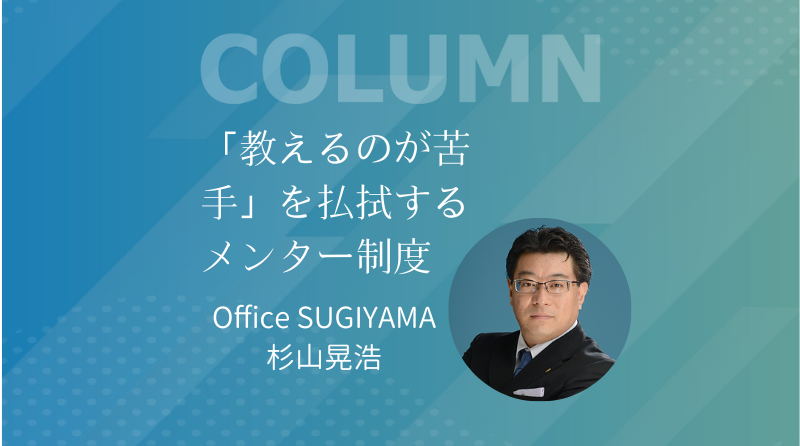第9回目は「就業規則のポイント〜給与に関する規定~」についてです。
給与に関するルールの重要性
前回まで、就業規則が必要な理由について以下を指摘してきました。
1、法律の定めにより、対応する必要がある
2、会社(職場)のルールを従業員に伝える
3、会社を成長・発展させる
ここで考えていただきたいのが、「従業員が貴社で働く目的は何か」です。
採用面接の際に、就職の希望理由を尋ねる企業は多いと思いますが、実際にその希望が実現できているかどうかの確認をされている企業はそれほど多くないのではないでしょうか。
職種、業務内容(責任の範囲を含む)、勤務状況が同等の場合、介護事業所間の給与格差はそれほど大きくはありません。
だからこそ、従業員の職場選びにおいて給与額以外の要素も重要となります。
もちろん、給与の重要性は無視できません。金額もさることながら、給与の在り方が大切です。
例えば従業員が貴社で「〇〇について貢献したい」、「学び成長したい」、「挑戦したい」等の希望を持って入職したとすれば、それを達成した場合に給与で報いる仕組みを敷けば、モチベーションアップや帰属意識の醸成に効果的です。
これが、「会社の成長・発展につながる就業規則」の考え方です。
前回からの繰り返しになりますが、私は介護事業者様に「従業員の多様性ある働き方を受け入れる考えがあるのであれば、基礎となるルールは明確に、分かりやすく伝えてください」と伝えています。
これは給与においても同様です。
それでは、就業規則における給与について見ていきたいと思います。
給与は介護事業者と従業員のコミュニケーション手段
私は経営において、「給与(賃金)」は労使双方にとって事業の成果を示すバロメーターとなるとともに、企業の精神であると考えています。
だからこそ、「給与」に対する“在り方”がとても重要です。
就業規則には、以下のように賃金の構成を記載します。

給与がどの項目で構成され、支給するのかを示します。
基本給のほかに、各種手当や割増賃金といった項目があります。
法律では、労働した分の賃金を支払うこと、賃金の支払い方、最低賃金、割増賃金等について記載することを義務付けていますが、手当の項目については規定していません。
就業規則の改定の支援をさせて頂く際にも、とりあえず設定されたような手当をよく目にします。
例えば、部長、課長、係長などに支給される役付手当は、与えられた職務を会社に提供した場合に支給されるものです。
では、その職務は何ですか?
部長と課長の職務の違いは何ですか?
何をもって価値を提供したことになりますか?
こうした切り口から整理が必要です。
特定の役職であることを理由に支給するのではなく、質的、量的、精神的な貢献を評価して支給するべきでしょう。
また、役付手当は
部長手当:100,000円
といった一律支給をする必要はありません。
50,000円〜100,000円という幅を設けることも可能です。
さらに、役付手当の支給対象は正社員だけに限定する必要もありません。パートタイマー等であっても、マネジメントスキルが高い従業員にはそのような立場で貢献頂く事もあるかもしれません。
実際に、マネジメントスキルの高い方が定年退職後、別の企業で部長補佐のような形で勤務されることも珍しくありません。そのような時、「定年退職後の再雇用だから手当をつけなくても良い」という固定観念にとらわれていては、同一労働同一賃金の視点から好ましくありません。
また、資格手当については、その資格を活かした業務に従事されている場合に支給する文言を付与されてはいかがでしょうか。
例えば、訪問看護事業所で、ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格を持っている場合、資格を保有しているだけで手当を支給する必要があるかということです。
業務における貢献度に応じて報酬で評価することを考えてはと感じます。
各種手当は、会社からの期待や感謝を表現するものです。
言い換えれば、会社の目標に対し、どのような労働を従業員に求め、それ答えた場合にどのように報いるのかを表すコミュニケーション手段です。
〇〇の業務をしてくれてありがとう。
〇〇の責任を担ってくれてありがとう。
あまりにも手当項目が多いのもいかがなものかと言えますが、従業員の取り組みとのつながりが、ある程度見える形で支給する方がモチベーションの向上に繋がるでしょう。
なお、処遇改善加算を手当として支給される場合は、この手当項目に記載しておく必要があります。
月給における欠勤の取り扱い
人事労務、とりわけ給与計算のご相談において、欠勤時の取り扱いに関する事をよく尋ねられます。
「正社員の場合、月給制ですので、休んでも給与は減額できませんよね?」
「給与を減額する場合、どれだけ減額しても良いのですか?」
給与の体系が「月給制」の場合は減額できないという認識の方がおられます。
「月給制」を大きく分けると「完全月給制」と「日給月給制」に分かれます。
完全月給制では、給与は月額として決められており、欠勤・遅刻・早退をしてもその分は差し引かれません。一方、日給月給制は、給与は月額として決められていますが、欠勤・遅刻・早退をした場合はその分が差し引かれる給与体系です。
トラブル防止の観点から、「日給月給」で運用される場合は、就業規則の給与に関する規定で、欠勤・遅刻・早退した分は支給されない事を明記載しておきましょう。
以前の職場で、欠勤しても給与は減額されていなかったため、職場を移っても同じだろうという認識の従業員もおられます。
(実態は、欠勤時は有給として処理されていたので、額面的には減額されていなかっただけというケースもあります)
(欠勤等の扱い)
第○条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。
2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。
(1)月給の場合
基本給1か月平均所定労働時間数
(1か月平均所定労働時間数は第○条の算式により計算する。)
(2)日給の場合
基本給1日の所定労働時間数
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
上記は、厚生労働省の就業規則ひな形です。
このように欠勤・遅刻・早退をした場合の取り扱いについて記載します。
欠勤控除の計算方法は法令で定められていないので、会社で定めることが可能です。
ひな形は、基本給のみを控除対象となっていますが、手当を控除対象とする事も可能です。
そのような場合は、控除の対象とする手当、控除対象としない手当を記載します。
ただし、労働者に不利益な控除方法はトラブルになりますので、合理的な方法で定めてください。
昇給、賞与に関する記載は慎重に
(昇給)
第○条 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年 月 日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
(賞与)
第○条 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
労働基準法において、昇給や賞与に関する規定はありません。
ただし、処遇改善加算を賞与や一時金として支給される場合はこの賞与部分に記載しておく必要があります。
昇給や賞与がなくても法律的には問題ありません。とはいえ、多くの従業員が昇給や賞与は、「普通はあるもの」「モチベーションに大きく影響する要素」、「生活のために不可欠なもの」という意識をもっています。
それゆえ、私個人としては、昇給や賞与支給はすべきと考えますが、昇給を確約する事、賞与支給額を確約する事は経営においてリスクを伴いますので慎重にすべきです。
例えば、就業規則等で「4月に毎年昇給する」「賞与は6月と12月にそれぞれ基本給の1ヶ月分を支払う」という記載があれば、経営状況がいかなる場合であっても会社にはその義務が生じます。
私は介護事業所の経営状況に応じた人事マネジメントの観点で昇給、賞与の在り方を検討します。
従業員の貢献がリアルタイムに給与へ反映されることで、モチベーションが維持・向上につながる場合があります。利益を積み立て賞与として還元する場合、支給時に資金が不足する場合も想定されるリスクがあります。
もちろん、収益が全てではありません。会社へ貢献した者に対する評価という視点も大切です。
人材が流動する時代、特に介護事業所は転退職が多いため、給与、賞与で雇用定着に繋がる仕組みづくりに取り組むことは必須だと感じています。
第10回目は、「就業規則のポイント〜働くためのルールと退職〜」をお届けします。
※この記事は、難しい用語を極力削減し、わかりやすさを重視しています。
この記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。