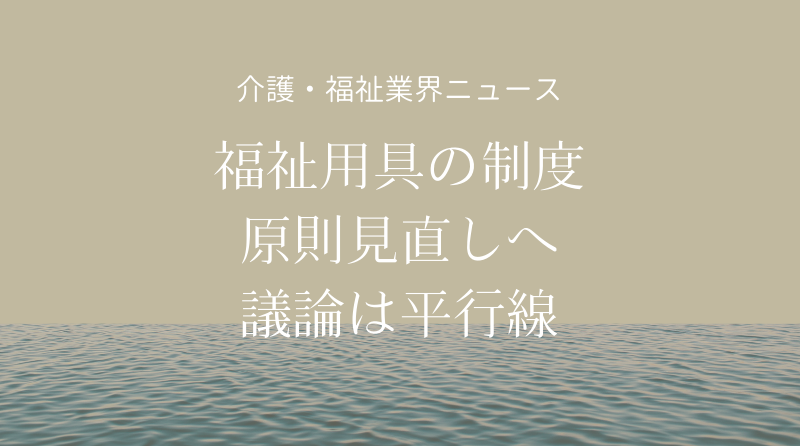4月21日、第3回となる「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」が開催されました。前回に引き続き、介護保険給付の対象となる福祉用具について、要介護者等の”居宅での自立した生活の支援”と”介護保険制度の持続可能性の確保”のバランスを配慮したうえでの、福祉用具「貸与」・特定福祉用具「販売」を巡る制度設計や、福祉用具を使って在宅生活を続ける高齢社に対する介護支援専門員の支援等について、議論が交わされました。
第2回までの本会合では、「貸与原則から販売への移行」に関する財政審の提言に対し、社会保障や在宅介護の専門家からは慎重な議論を求める声が多数挙がっていました。厚労省はこれを受け、新たなデータ等を示して議論の深化を促しています。
福祉用具貸与・販売のあり方を見直すための5つの論点
厚労省は前回会合に続き、以下の視点で構成員に議論を促しました。
<着目すべき5つの論点(厚労省)>
1.現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理の必要性
2.利用者の状態を踏まえた対応
3.福祉用具の使用に関するモニタリング・メンテナンス等
4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス担当者会議等)
5.経済的な負担
また、今回は、厚労省がまとめたデータに加え、3名の専門家による報告書等の提出資料も共有されています。
*岩元文雄構成員(全国福祉用具専門相談員協会理事長):財政審が販売への移行の検討を進めるべき品目としている歩行関連用具や手すりの選定について、専門的視点・個別性を踏まえた介入意義の説明。
*小野木孝二構成員(日本福祉用具供給協会理事長):貸与制度と割賦販売の端的な比較
*濵田和則構成員( 日本介護支援専門員協会副会長):福祉用具貸与サービスの単独利用における 居宅介護支援の実態調査報告書
貸与から販売への移行、折衷案の提案も
5つの論点のうち、”1”について、現状の介護保険制度では福祉用具の利用は「貸与」が原則とされ、貸与になじまない性質もの(入浴・排泄関連用具等)のみ「販売」の対象としています。
この枠組みに対し、利用者の自己負担や介護費用の削減を進める観点から「要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目」について、原則「販売」への移行を求めるという提案がなされてきました。
<介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目(2020年11月の財政審の建議)>
歩行補助杖
歩行器
手すり
スロープ
この論点について、慎重な検討を求める意見が構成員の多数を占める状況は変わっていません。その一方で、建設的な解決策を模索するため、具体的な提案をした構成員もあり、より議題に対して踏み込んだ議論が展開されました。
価格や使用期間、本人の希望を踏まえた選択性の導入を提案
具体的には、「4品目すべてを急激に販売種目として移行するのではなく、借り換えの度合いが比較的小さく、費用も1万円未満で購入可能な安価なもの(固定用スロープ・三角板など)から検討を進めていく」案(テクノエイド協会の五島清国構成員、国際医療福祉大学大学院福祉支援工学分野教授の東畠弘子構成員)や、「一定の使用期間を経過した場合等に、本人の希望を前提として購入への切り替えを選択できるようにする」案(五島構成員、健康保険組合連合会の田河慶太構成員)などの意見が提示されました。

【画像】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回、参考資料2)福祉用具関係参考資料より
また、岩元文雄構成員は、「歩行関連用具」「手すり」を例とし、利用者の状態変化や住環境・介護環境等に応じた貸与本数や種類の変化について資料を提示。「貸与」原則による柔軟な対応が利用者の自立支援や重度化防止に貢献しているという実態を示したうえで、「貸与」原則のメリットを訴え、「販売」原則への移行には慎重な検討を求める意見を添えました。


定期的なモニタリング・メンテナンス等は現実的に可能か
こちらは、3つ目の論点「福祉用具の使用に関するモニタリング・メンテナンス等」に関する議論です。
「販売」へ移行する場合の懸念点とされている定期的なモニタリング・メンテナンスに関する切り口として、22年4月1日より介護保険の特定福祉用具販売の対象種目として新たに追加された「排泄予測支援機器」が着目されました。
同年3月31日に厚労省より発出された通知では、「介助者も高齢等で利用に当たり継続した支援が必要と考えられる場合は、販売後も必要に応じて訪問等の上、利用状況等の確認や利用方法の指導等に努めること」と明記されています。
この指針を具体的な事例として、「販売」への移行後も「貸与」と同程度の定期的なメンテナンス等を求めることはそれほど難しいことではない、言い換えれば、モニタリングやメンテナンスの体制を維持できれば、「販売」制度への移行は可能であるとの主張です。
*関連記事:「排泄予測支援機器」が介護保険給付に。在宅現場の運用で留意すべきポイントは?
ケアプラン上に載らない支援への理解と検討を
多くの専門家から意見が述べられたもうひとつの論点が、介護支援専門員による支援についてです。
財政審では、「福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行うなどサービスの内容に応じた報酬体系とすることも、あわせて令和6年度 (2024年度)報酬改定において実現すべき」などと議論されています。(リンク:直近(4月13日)の財政審の分科会資料)。
立場によって見解が大きく分かれる論点であり、今回の検討会でも多くの専門家から明確な反対意見があがりました。
日本介護支援専門員協会の濱田構成員は、900名を超える介護支援専門員への調査を実施(有効回答者数545名)した調査結果を提出。ケアマネジメントを福祉用具貸与サービス単独利用実態のみによる評価で判断することの危険性を強く訴えています。
在宅介護を支える制度について根幹から見直すこの検討会。拙速な決着をつける訳にはいかず、次回会合にて同様の論点について議論が継続される見込みです。