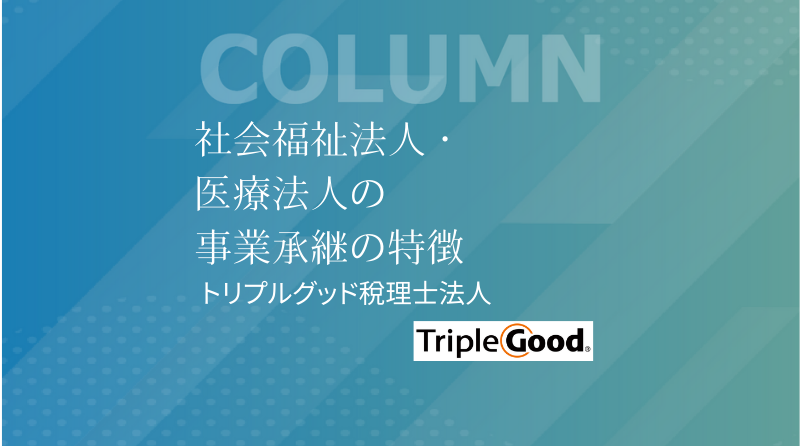前回は、介護事業のオーナー経営者を対象として代表的な事業承継の手法と備えについて紹介しました。
同じく介護事業に関わる社会福祉法人や医療法人でも経営者の高齢化は進んでおり、対策は急務です。
今回は、特殊法人である医療法人と社会福祉法人の事業承継の特徴について解説いたします。
社会福祉法人の事業承継の特徴
■社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、所轄庁による認可により設立されます。
社会福祉法人は非営利法人であるため、法人設立時の寄附者に持分はなく、期末などに剰余金の配当もありません。
さらに、解散時の残余財産は社会福祉法人その他学校法人、公益財団法人などの社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属します。
■社会福祉法人の承継方法
社会福祉法人の代表的な承継方法は、下記の3つです。今回はそのうち、合併と事業譲渡における留意点について解説します。
1.経営権の取得
社会福祉法人を買収しなくても、理事となり経営権を取得することで、社会福祉法人のM&Aを行ったのと同じ効果が得られます。
意思決定機関である理事会の決議は、3分の2以上の決定が必要となります。
理事の合意を得ることができれば、合併や事業譲渡よりコスト削減が可能です。
2.合併
合併とは、2つ以上の法人が契約によって1つの法人に統合することをいいます。
社会福祉法に規定されている合併は、社会福祉法人同士でのみ認められています。
3.事業譲渡
事業譲渡とは、売手の事業の一部またはすべてを買手が受継ぐ方法です。
社会福祉法人の場合、その法人が行っている事業の一部を譲渡することはできますが、事業の全部を譲渡することはできないと考えられます。
■社会福祉法人の合併及び事業譲渡における留意点
【合併・事業承継共通の留意点】
社会福祉法人の有する性格より、社会福祉法人の事業展開は、公益性・非営利性を十分に考慮した事業承継が必要であるため、経営基盤の保全の観点や所轄庁との調整が重要になります。
【合併に関おける留意点】
合併時における役員の選任
評議員・理事・監事・会計監査人の資格及び権限・義務の明確化がされているため、法令に準拠した選任手続きをとる必要があります。
特別の利益供与の禁止
平成28年改正法により、役員等の社会福祉法人の関係者への特別な利益供与の禁止が規定されました。
特別の利益とは、例えば以下のようなものが該当します。
A: 法人の関係者からの不当に高い価格での物品等の購入や賃借
B: 法人の関係者に対する法人の財産の不当に低い価格又は無償による譲渡や賃貸
C: 役員等報酬基準や給与規程等に基づかない役員報酬や給与の支給
合併にあたっては、新たな役員の選定、報酬決定が行われることから、これらに抵触するような報酬支給が行われないよう注意が必要です。
法人外流出の防止
社会福祉法人において、法人外への対価性のない支出は認められていません。
社会福祉法人は持分がないことより、合併契約に基づき又は先立って、合併の相手法人へ金銭を支払う行為や経済的利益を与える行為は、想定されません。
評議員、理事、監事等は、社会福祉法人に財産上の損害を与えることがないよう職務を行う必要があります。
行政への相談
合併の場合、所轄庁より合併認可を受ける必要があります。
このため、事前に所轄庁へ合併の趣旨目的や背景事情などを説明し、合併申請の方法、疑問点などを事前相談することが重要です。
【事業譲渡における留意点】
譲渡事業が譲受法人で継続可能かどうか事前確認等
社会福祉事業は所轄庁による認可が必要な事業が多くあり、社会福祉事業を実施できる法人格が制限されているものもあります。
譲渡事業が譲受法人で継続可能かどうか、許認可等を行う行政庁に事前確認し、事前協議の必要があります。
行政への相談
事業譲渡は、財産の移動を伴うことがあり、所轄庁の承認や国庫補助事業により取得した財産の処分の承認、借入債務にかかる各種手続などクリアすべきものも多くあります。
また、譲渡元における施設の廃止手続き、譲渡先における認可・指定等の手続きの実施が求められるため、所轄庁への事前相談と同時に、許認可等を所轄する行政庁への事前相談も必要です。
特別の利益供与の禁止等
平成28年改正法により、役員等関係者への特別な利益供与の禁止、競業及び利益相反取引の制限等が規定されています。
・特別の利益供与の禁止: 合併の留意点に同じ
・利益相反取引の制限
利益相反取引の制限では、例えば、甲社会福祉法人の理事Aが乙株式会社の代表として乙株式会社のために甲社会福祉法人と売買契約を締結する場合は利益相反取引に該当することから、このような事業譲渡を行う場合には、理事会において重要な事実を開示し、その承認が必要です。
法人外流出の防止と支払対価の関係
社会福祉法人において、基本的には、法人外への対価性のない支出は認められていません。
そのため、事業譲渡の支払対価との関係で留意する必要があります。
譲渡側:事業価値を適切に見積り、少なくともその価値以上の受取対価が必要
譲受側:事業価値を適切に見積り、少なくともその価値以下の支払対価が必要
事業譲渡は組織の移転であるため、事業の価値は、対象事業の不動産の時価と移転する他の資産及び負債だけではなく、将来の収益性を加味したものと考えられます。
単に国庫補助金を返還しないための無償譲渡など、事業価値を適切に見積らずに取引を行うと、法人外流出の可能性があることに注意する必要があります。
国庫補助金の取り扱い
社会福祉法人が国庫補助金を受けて取得した財産を処分する際には、厚生労働大臣等の承認が必要となります。
承認にあたっては、交付した国庫補助金に相当する額の返還や、返還を求めない場合であっても処分を制限するなどの条件が必要です。
補助金を返還しないための無償譲渡は、法人外流出の可能性があるため注意が必要です。
医療法人の事業承継の特徴
■医療法人とは
医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設、介護医療院を開設する社団または財団をいい、都道府県の認可により、医療法に基づいて設立される法人です。
医療法人社団と医療法人財団の2つに区分され、さらに医療法人社団は、出資持分の有無の観点から、「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」にわかれます。
今回は、医療法人社団について解説いたします。
1.医療法人社団
・持分あり医療法人
・持分なし医療法人
2.医療法人財団
■医療法人社団:持分ありの医療法人
持分あり医療法人の承継方法としては、主に4つがあります。
1.出資持分の譲渡(親族承継、親族外承継)
2.出資持分の払戻し(親族承継、親族外承継)
3.合併(M&A)
4.事業譲渡(M&A)
1.出資持分の譲渡
医療法人の理事長が、後継者に対し、自身の出資持分を譲渡することによる事業承継です。
株式会社と異なり、出資持分を譲渡しただけでは事業は承継されないのが特徴です。
医療法人の出資持分は、株式会社における株式とは異なり、定款で定めた場合に認められる財産的な権利しか有せず、議決権などの経営権はありません。
医療法人においては、株式会社における株主に相当するのは社員ですが、社員は、必ずしも出資者である必要はなく、出資持分とは紐付いていません。
そのため、株式会社とは異なり、出資持分を移転しても、経営権は移転せず、経営権を承継するには、出資持分の移転とは別途、社員の入れ替えが必要となります。
2.出資持分の払戻し
出資持分の払戻しは、譲り渡す先生(社員)が医療法人を退社します。
その際に出資持分に応じた払戻しを受け、後継者として譲り受ける先生が医療法人に社員として入社し、出資者となることにより事業承継を完結させる方法です。
3.合併
医療法人の合併には、都道府県知事の認可が必要となりますので、事前に行政官庁との調整が必要となります。
合併では、消滅する医療法人の権利義務を包括的に引き継ぐことになりますので、消滅する医療法人は資産・負債の清算を行う必要はありません。
4.事業譲渡
こちらは複数のクリニックを運営する医療法人が、あるクリニックだけを譲り渡したいときなどに採用される方法です。
個人クリニックと同じで、事業譲渡で開設主体が変わりますので、引き継いだ先生は、新たな診療所の開設者となります。
そのため、都道府県や保健所、厚生局などへの行政手続きが改めて必要となります。
■医療法人社団:持分なし医療法人
持分なしの場合は、理事長側に出資持分はなく、解散時の残余財産は国庫に帰属することになります。
持分ありのような払い戻し・譲渡による課税などは発生しないのが原則です。
そのため、医療法人で定めた役員退職金にそって、医療法人の財産価値を回収する形となります。
社会福祉法人や医療法人の事業承継は制約・調整が多く早めの対策が必要
社会福祉法人や医療法人の事業承継は、特殊法人の重要な役割から、その経営に与える影響、各種法令遵守、関係当事者間、行政官庁との調整など、様々な観点からの検討が必要です。これらの事項を検討し、当該法人にとってどのような手段を用いて事業承継を行うのがベストなのかを検討する必要があります。特に、第三者承継の場合には、そもそも当該法人と合う第三者を探す必要があり、また、行政との事前の相談も重要となりますので、早めの対策が必要となります。