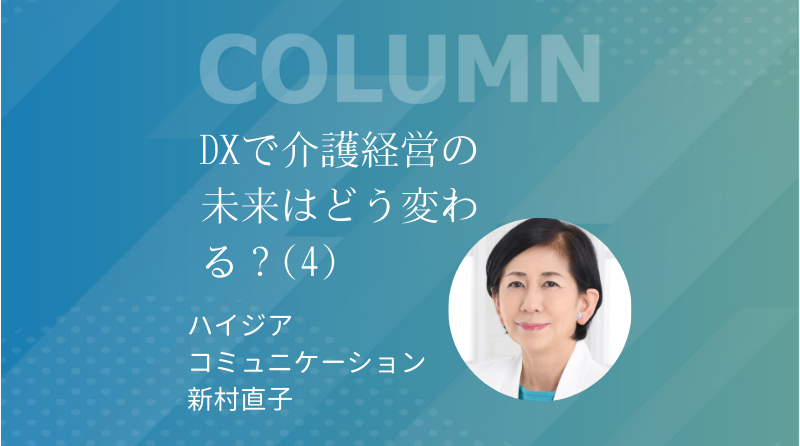宮崎県都城市。人口16万人弱の町においてこの10年で、売上高も職員数も右肩上がりに急成長している社会福祉法人がスマイリング・パークです。総勢420人(2022年2月末時点)のスタッフが働き、売上高は16億2494万円(21年度)。今でこそ、職員の定着率が上がり、大学新卒を含めた職員の“応募が絶えない”法人ですが、ICT化に踏み切る以前は離職率が25%に及んだ時期も。一体どんな施策を打って生まれ変わったのか、理事長として法人を率いる山田一久さんに伺いました。
疲弊する職員たちを目の当たりにして、職場改革へ

【画像】山田一久氏
特別養護老人ホーム「ほほえみの園」をはじめとする各種高齢者施設、在宅ケア、子育て支援、障がい福祉などの幅広い事業を同市内外の35拠点(2022年3月時点)で展開する社会福祉法人スマイリング・パーク。「働くスタッフの幸福度を高める」ことをメインテーマに掲げ、法人名の通り笑顔に包まれる職場づくりを目指しています。
「介護の世界に入る人の多くは“誰かの役に立ちたい”と考えている人たち。ところが、日々の業務に追われて、利用者さんとしっかり向き合う時間が取れない。介護の仕事が面白くなくて辞めていくのではなく、記録等に使わなければいけない時間が面白くないだけなのではないかと。私が施設長となった2011年以降、介護現場へのICT導入に大きく舵を切ったのは、職員たちが利用者さんたちとゆったりとお茶を飲むなど、笑顔でかかわる時間を増やしたかったからです」。山田さんはこう振り返ります。
当時は、業務日誌や個人記録などもすべて手書き。記録作成を繰り返し行わなくてはならず、申し送りのために、定時が過ぎても2~3時間も残らなければいけない。そんな非効率な現場で、職員たちは疲弊し切っていました。離職率は実に25%に達し、介護職の離職率の平均14.9%(令和2年度介護労働実態調査)に比べ、10ポイント以上も高かったのです。
記録の電子化、音声入力の採用で記録づけの苦痛から解放
施設長に就任して真っ先に取り組んだ改革が業務のICT化でした。「まずは、介護記録を電子化しました。使い勝手が悪くアフターフォローも良くなかったシステムの5年のリース期間を終えたタイミングで、職員がiPadを持ったまま、入居者と話しながら、食事や水分の補給、入浴、服薬の状況などを入力・記録できるタイプの介護業務支援ソフトに切り替えました。一度入力すれば転記も不要になり、その他の職員らとも情報共有できるので、苦痛だった記録づけの負担が大きく減りました」。
もう一つ、スマイリング・パークがDXを加速するきっかけとなったのが、14年に導入した音声入力です。利用者の病院受診に付き添った際、医師が問診で音声入力システムを活用しているのを目の当たりにした山田さんは、「介護業界にはタイピングに苦手意識を持つ人がまだ多い。マイクに話しかけるだけでテキスト入力ができる音声入力の仕組みはこの業界でこそ役立つのでは?」と考えます。こうして、ソフトウェア会社側に「音声入力の仕組みを今の介護ソフトに搭載してほしい」と提案。同社が介護業界の専門用語などもAIに習熟させた結果、介護業界では初の試みとなった音声入力支援システム「Voice Fun」の機能開発に繋がりました。

【画像】スマイリング・パーク提供
音声入力に切り替えた成果はというと、「従来のキーボード入力にかかる時間が、音声入力の操作に慣れていくと2分の1程度の時間で済むようになりました」(山田さん)。パソコンに慣れている若者はともかく、介護経験の豊富な職員ほど高齢で、キーボード操作や入力に時間がかかることも多いもの。こうした高齢の職員にとっても、音声入力がICT機器に慣れる大きな助けになったそう。さらに、より便利な記録付けの方法を模索する中で、20年からはタブレット端末でのケア記録も音声入力で行える「Voice fun mobile」も活用しています。
バイタルデータの管理も多職種共有、Bluetooth対応で改革
ICT化によって、体温や血圧などのバイタル情報の管理法も大きく変わりました。17年11月には、こうしたバイタル情報を、「バイタルリンク(下の図参照)」という介護支援ソフトとは別の企業が提供する多職種連携情報共有システムに載せるように。例えば、訪問介護先で利用者のバイタル情報を測定して、スマホで連動させれば、かかりつけ医やケアマネジャーなど利用者のケアに関わる多職種間でバイタル情報をリアルタイムに共有でき、気になった情報に対する治療方針を関係者らが既読しているかどうかなども確認できるといいます。さらに、19年4月には、体温計や血圧測定器などのバイタル測定機器をすべてBluetooth対応のタイプに変更。測定データをアプリなどに連携できるようになったことから、記入ミスなどのヒューマンエラーもなくなりました。

パソコンやスマートフォン、タブレットを用いて、情報の閲覧や登録が可能なため、いつでもどこでも、利用者の情報を共有できる(資料:スマイリング・パーク提供)
配膳ロボット・AI車椅子も導入
スマイリング・パークでは、職員がより幸せになるための職場づくりの一環で、前々回の記事で紹介したセンサー機器「眠りSCAN」も16年11月からと早い段階から導入。見守りの作業負担を減らしたほか、現在は配膳などの業務をロボットで代替しようという取り組みも進めています。「デイサービスセンター ほほえみの園」では、料理を運んだり、食べ終わった皿などを片付けたりする配膳ロボット「ベラボット」を実験的に導入。価格についてはメーカー側と交渉し、どのぐらいであれば普及できそうかという観点から、交渉を重ねています。

【画像】配膳ロボット「ベラボット」を使いこなす職員
「これからの日本で、人が減るのは自明。働き手も高齢化で体力が衰え、記憶や判断力の低下、腰痛なども起きてきます。しかし、こうした不安はありつつも、準備をしていれば怖くありません。うちは定年を75歳に上げましたし、今と同じサービスの質を担保するためにロボット導入は必須」。山田さんはそう言い切ります。
20年11月には、AIを搭載した自動運転車椅子も日本で初めて導入しました。久留米工業大学の東大輔教授らが開発したもので、導入にあたり、ホーム内の居住スペースや食堂、売店、トイレなどの位置をAIに登録した上で、利用者は車椅子に設置したスマホに話しかけて、行先の指示を出します。車椅子が目的の場所に到着し、利用者が居室などに戻ると、車椅子は当初の置き場所に自動で戻ります。利用者の中には、職員に車椅子を押してもらうことを遠慮する方や、体力的に手動の車椅子を稼働させることが難しい方もいます。そんな利用者が職員の手を借りずに行きたいところに自由に行けるようになり、下の写真の通り、笑顔が自然と増えるのだといいます。

【画像】左がAI車椅子を開発した東教授、右が山田理事長
脳波を読み取り、利用者の思いを“見える化”するプロジェクトも
職員の幸せを追求する中で始まった、画期的な取り組みがもう一つあります。ケア・コミュニケーターという脳波を読み取る機器を活用して、「好き」「嫌い」「興味・関心」など利用者の感情を把握しようというプロジェクトです。介護現場では、いつも対面している認知症の利用者さんの気持ちがわからないことが、職員にとってストレスになりがち。「介護する相手の気持ちがわかれば、職員たちも本当に喜ばれているかどうかの根拠があるので、やりがいを実感でき、より質の高いケアに繋がるのではないか。そんな発想から現在、慶應義塾大学理工学部の満倉靖恵教授と協業し、満倉研究室が開発したケア・コミュニケーターを使って、実証実験なども行っています」。

【画像】ケア・コミュニケーターを装着中の女性。食事の摂取量が減った方に装着して、どんなおかずの反応が良いかを確認する中で、本人が昔漬けていた梅干しに最も高い数値が出て、結果として主食摂取量の増加に成功した例も
この10年の数々の施策によって、スマイリング・パークの離職率は3~8%にまで改善しました。DXによって、山田さんがこれから実現したいこと。「それは、気持ちのいい場所をいかに作るかということに尽きます。働き手であれ、利用者であれ、人は居心地がいいところに集まる。働く人が幸せでなければ、利用者さんを快適にケアすることはできません。実際、残業が減ってきちんとリフレッシュできるようになると職員のケアの質も高くなり、利用者の満足度も上がっていきました。ICTも入れっぱなしではなく、DXを進めて人がどう変わるのか、次はそれを“見える化”するための仕掛けを考えていきたい」。
山田さんがそのための“武器”と話すのが、健康管理やメッセージ確認などができる腕時計型の電子機器、スマートウオッチです。22年3月に、スマートウオッチを特養の職員、利用者さんらを対象に合計120台導入。働き手と利用者の身体機能やメンタルがどのように変化していくのかをレポートしていく方針です。山田さんの描く介護経営の未来で、人はどこまで幸せになれるのか──。その試みに目が離せそうもありません。
山田一久(やまだ・かずひさ)
1970年宮崎県都城市生まれ。IT企業のサラリーマン時代に、身体障がい者1級の友人を連れて九州南部の韓国岳に登山したことを機に、福祉業界の仕事に就く。2002年、特別養護老人ホームほほえみの園の開設準備に携わり、2011年6月、施設長に就任。「働く職員の幸福度を高める」ことをテーマに、ICT化などの業務改革に着手し、事業を拡大する。2016年5月から現職。