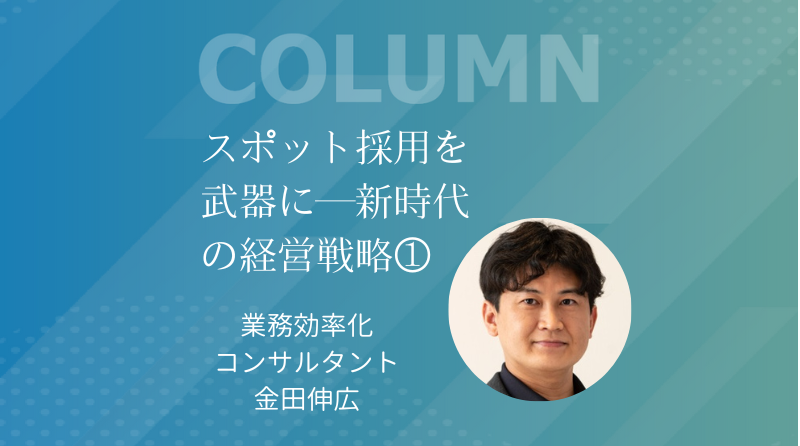介護業界は今、歴史的な転換期を迎えています。人材不足、高齢化、厳しい報酬改定という三重苦に直面する中、私たちには従来の常識を打ち破る革新的なアプローチが求められています。
現場の課題に応じたテクノロジーを活用しつつ、柔軟な働き方や新たな人材育成モデルを取り入れることが、介護事業の未来を切り開く手段となります。本稿では、従来の採用活動とは異なる強みを持つスポット採用や最新のテクノロジーに着目し、厳しい経営環境に打ち勝つ組織作りについて考察・提案します。
人材採用だけじゃない?スポットワーカー活用のメリット
介護事業者にとって人材確保は、まさに生き残りをかけた最重要課題ともいえます。これを解決する手段として注目を集めているのが、単発アルバイトを仲介するサービスを提供するプラットフォームです。スポット採用は単なる人材確保の手段ではなく、組織の構造改革をも促す革新的なアプローチです。
具体的なメリットには、人材マッチングの精度向上があります。医療や介護分野に特化したサービスも生まれていて、あるサービスの登録ワーカーは95%以上が有資格者、うち35%が介護福祉士というデータもあります。一方、別の会社が提供している介護分野に特化した有償ボランティアのマッチングサービスでは、登録者の多くが異業種出身または学生で、年齢では20〜30代中心という特徴的な構成になっており、介護業界と新しい人材を結びつける可能性を秘めています。
さらに重要なのは、こうしたスポット採用が長期雇用の入り口となり得る点です。求職者にとってハードルの低いスポットワークを通じて、従来の採用で起きていたミスマッチを防ぐほか、これまで介護業界に縁のなかった人材が新たなキャリアパスを見出す効果もあります。事業運営面のメリットとしては、スポットワーカーの多様な特技がレクリエーションの質を劇的に向上させたという事例もあります。
限られた報酬の中でいかに付加価値を生み出すか。これは、これからの介護経営の本質といえます。
コア業務の再定義:職員一人ひとりの役割を明確化する
介護現場の慢性的な人材不足は、職員の過重労働や業務の曖昧さを生み出しています。経済産業省の「将来の介護需要に即した介護サービス提供に関する研究会報告書」によれば、介護職が行う業務のうち本来業務の割合は少なく、60%以上の時間を間接業務に追われているといいます。また別の調査によれば、介護業務を48種類に分解した結果、約7割の業務が未経験者でも対応可能であることがわかっています。(スタッフサービス・メディカル調べ)。この状況から脱却するには、介護職にしかできないサービスと、介護助手やその役割を担うスポットワーカーに振り分けるタスクを明確に区分する「業務分解」が不可欠です。
具体的には、身体介護や専門的ケア、利用者の状態観察などを介護職にしかできないコア業務とし、環境整備、食事準備、洗濯、記録作業などを切り離すアプローチが求められます。
この取り組みは、介護職員の専門性を高めつつ、職務満足度の向上にもつながります。スポット採用した人材に加え、介護ロボット・AIツールの活用も進めることで、さらなる業務効率化も期待できます。
カギは、職員一人ひとりの役割を明確にして本来の介護サービスの質を高めることにあります。
介護ロボットやAI…テクノロジーは現場をここまで変える
介護現場における人的リソースの限界を打破するには、テクノロジーの活用も不可欠です。その代表的な存在である介護ロボットに目を向けると、移乗支援、見守り、コミュニケーションなど、多岐にわたる機能を持つ製品が導入されています。例えば、パラマウントベッドの「眠りSCAN」は、利用者の呼吸数や心拍数をリアルタイムでモニタリングし、夜間の巡回回数を大幅に削減可能にしており(山梨県「介護ロボット・ICT導入に関するモデル事業成果報告会」)、介護職員の身体的・精神的負担を劇的に軽減する可能性を秘めている技術といえるでしょう。
AIの進化も目覚ましく、高度な予測・判断の支援を可能にしつつあります。テスラ社の「オプティマス」のような人型ロボットの登場は、将来的に直接的介護をも可能にする未来を予感させます。
排尿予測や効果的な機能訓練計画の作成といった機能的な生産性向上を可能にしている機器はすでにありますが、人間の感情やその場の状況を理解してきめ細やかなサポートができるロボットが実現すれば、直接的な身体介護もできるようになるでしょう。このような未来が、もはや夢物語ではなくなりつつあるのです。
また、タブレットやスマートフォンのようなIoTデバイスの浸透によって、チャットツールやシフト管理ツールが現場に取り入れるようになりました。これらのソリューションの効用は現場のコミュニケーションを劇的に進化させた点にあります。
チャットツールを取り入れている事業所ではサービスご利用者のご家族やケアマネジャーとのコミュニケーションが円滑になり、介護職員はより質の高いケアに集中できるようになっています。
調整ツールによってシフト作成時間が大幅に短縮した事業所では、管理者が現場の声に耳を傾ける時間を創出できます。テクノロジーの効用は単なる作業時間の削減にとどまらず、人と人とをつなげる重要なツールにもなっているのです。
介護事業者が進めるべき新しい学びの仕組み構築:OJTとスポット採用の融合
あらゆる人材が活躍できる職場づくりを進めていくには、人材育成における課題にも目を向ける必要があります。多様性の時代に入り、従来のOJTを中心とした教育制度では介護事業者も生き残りが難しくなっています。厚労省は従来のまんじゅう型・富士山型を脱却し、「山脈型キャリアモデル」を提唱しています。

これは、一人ひとりがどこを目指すのか見えにくかった従来の「まんじゅう型」やキャリアの選択肢が少なかった「富士山型」の課題を克服し、多様なキャリアに応じた道標を示せるよう整理したモデルです。
キャリアの多様性を踏まえた経営がこれからの介護事業、ひいては業界の生命線です。
スポット採用が秘めている可能性を最大限引き出す「組織改革」
スポット採用に話を戻しましょう。
ここで採用した人材を真に活用し、時代に合わせた組織改革を進めるには、正規職員との社内での発言権の垣根を取り払う。これが肝です。スポットワーカーには異業種経験者が多いことに着目し、彼らの多様な経験を組織の学習資源として活用することで、組織の学習能力そのものを高めることができます。
例えば、異業種で培ったマーケティングスキルや、コミュニケーション能力を介護現場に活かす。ここに、スポット採用の真の価値があるといえます。
介護報酬改定で強化された研修制度を徹底活用し、スポット採用者にも必須研修の機会を提供しつつ、正規採用へのスムーズな移行を仕掛けることで組織の持続的成長を実現する戦略的投資としていく。法人と職員が協力してキャリアパスを作り上げていく、この柔軟性こそがこれからの介護経営のキーワードです。資格至上主義はもはや業界全体で見直す時期に入っています。
2024年度介護報酬改定を追い風に新たなキャリアパスの構築を
2024年度介護報酬改定で厚労省が示した基本方針には「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止」に並び、「働きやすい職場づくり」があります。
スポット採用の導入と併せてこのテーマに取り組むには、スポットワーカーも含めた全職員に対し、個別のキャリア面談を実施することが第1歩です。そして、職員の属性に関わらず、一人ひとりの強みと志向に合わせたキャリアプランを策定します。
例えば、一日10時間の週休3日制、0.5人月稼働、リモートワーク、週末勤務など、多様な働き方を受容することで、これまで介護業界に入れなかった人材の可能性を切り開いていくことができるでしょう。
また、報酬改定で強化された加算を戦略的に活用し、特定スキルに特化した研修プログラムを整備しましょう。法人体制も見直し、部署や役職の垣根を越えて、異なる専門性や経験を持つメンバーを集めて構成されるチーム、いわゆるクロスファンクショナルチーム(C F T)が活躍できる場を積極的に作り、契約形態ではなく個人の貢献度で評価する仕組みを構築します。そうすることによって地域包括ケアシステムの推進という国策に合った、地域の介護力向上に貢献できる人材育成ができる組織を目指しましょう。これは新たなキャリアパスであり、事業所の地域における存在価値を高める戦略でもあります。職員の目指す道が変わったとしても、法人がフォローする環境こそが、真の人材確保・定着につながるのです。
介護保険制度は3年に一度の改正です。驚異的なスピードで変化する社会情勢に対応したくても限界があるのが現実です。だからと言って、変化を嘆いているだけでは我々介護事業者は国内の他業種のみならず世界から取り残されていきます。
これから生き残るのは、いかに変化対応することに柔軟な姿勢でいられるか。これに尽きます。法人が、拠点が、個人がその意識を持てるかにかかっています。