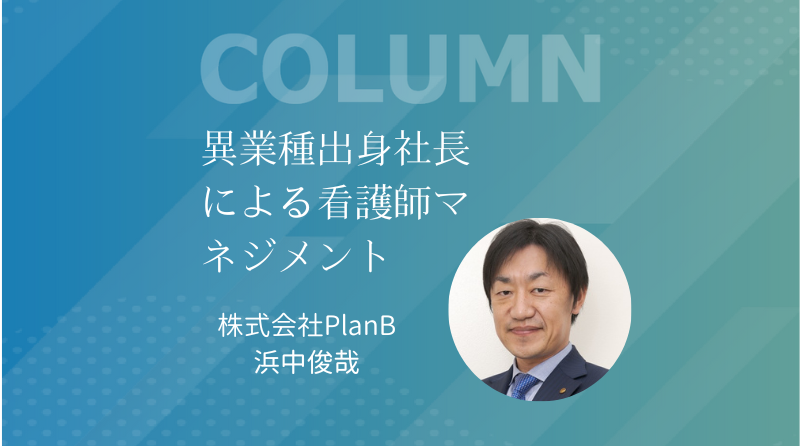この連載では、証券会社の営業マンという、全くの異業種から訪問看護事業を立ち上げ、いかに医療現場出身のスタッフをマネジメントし、地域に根付く在宅サービス事業者として自社を成長させていったのかを実例を交えながらお伝えさせていただいております。
前回は、私が訪問看護事業を起業した経緯や、立ち上げ時の苦労についてお話ししました。今回はその後、弊社がどのように成長し、どのような問題にぶち当たったか、そして、それをどのように解決していったのかをお話しさせていただきます。
医療現場で働いてきた看護師との意識のギャップに驚いた会社の”形成期”
新しく組織を立ち上げる―チームビルディングに役立つ考え方には、タックマンモデルという考え方があります。これは、組織の成長過程を表したフレームワークで、組織が形成されてからの変化を表わしたものです。
チームが形成されてから実際にその機能を発揮するまでの成長段階は①形成期→②混乱期→③統一期→④機能期→⑤解散期というプロセスを辿るという考え方です。

前回の記事では、企業における経営理念の大切さや病院で専門職として働いてきたスタッフのビジネスに関わる一員としての意識改革に取り組んだ時期のことをお話ししました。この頃、弊社はまさに②の混乱期にあったと言えます。スタッフ間で意見のぶつかり合いが起き、それがもとで退職者が出たり、ご利用者様にもご迷惑をおかけしたりしました。
この時期に私が取り組んだのは、わだかまりが残らないようにメンバーそれぞれからしっかりと話を聞き、一つ一つの衝突に丁寧に向き合い解決に当たることでした。不毛な時間になることも覚悟の上で、スタッフがどのように考え、どう思っているのかを知るいい機会であると考えたのです。
案の定、不平不満のような感情論が多かったのですが、驚いたのが、仕事に対する考え方です。
言い換えれば「株式会社に勤める看護師」として、こちらが求める認識とスタッフの自覚のギャップとでも言うべきでしょうか。決して、今までが病院勤務だったから意識に欠けるというわけではありませんが、時間に対する考えや備品1つに対する考え―何にどのようにお金がかかっていてどこからどのように収益があがるのか―をきちんと理解できていない方が多かったのです。
そこで、組織として次のステップを目指すために、この部分の意識の統一から取り掛かることにしました。
「社長はお金のことばかりで利用者様の気持ちがわからない」―混乱期を乗り越えるために取り組んだこと
開業間もない当時から、経営計画の発表会をしていたのですが、このギャップに気付いてからは、ここで話していた内容は全く理解も賛同もしてもらえていなかったのであろうと反省しました。入金までのお金の流れや、ガーゼ1枚、車を使って移動する事にも経費が掛かるという事、会社の利益がなければ昇給が出来ないという事、などを何度も分かりやすく説明し、株式会社である以上、利潤を追求していかなければいけないことを理解してもらいました。
それでも「社長はお金のことばかり言って、利用者様の気持ちが分かっていない」などと言われましたし、当時は1回1時間の訪問に2時間もかけるなどというスタッフもいました(もちろん利用者様は喜びますが1時間分の利用料しかいただけません)。
何度も何度も説明し、私自身も行動で示すことで、少しずつではありますがスタッフが変わっていったのを覚えています。タックマンモデルで言えば丁度、成長期から統一期に向けて変化していった時期でした。
しかしながらその後も主観的な仕事(自分がこんな看護をやりたい!という事を利用者様に押し付ける)をするスタッフが多く、何度もぶつかり合いました。スタッフの主張は「この会社じゃ私の思いが叶えられない」「本当に利用者さんが困っていることを決められた時間だけでは解決できません」といったものでした。
そこで私は弊社のスタッフと利用者様を対象にアンケートを取ってみることにしました。
スタッフには「利用者様は訪問看護に何を求めていると思いますか?」利用者様には「訪問看護に何を求めていますか?」を問いかけるものです。
結果は、回答が多かった順に下記の通りになりました。
【利用者様が訪問看護に求める事】
①時間を守って欲しい②上から物を言わないで欲しい③制度の説明をして欲しい
【スタッフが考える”利用者様が求める事”】
①看護技術・知識②看護経験③マナー
こちらが提供したいと思っていることと利用者様が求めていることに大きな乖離があったわけです。この結果は、すぐにスタッフに伝えました。そして、「本当に利用者様が求めることをしっかりと提供していくことこそが株式会社であり、私たちは究極のサービス業である」という事を全スタッフで再共有しました。
もちろんスタッフが「こうしたい!」という思いを全否定するつもりはありません。
しかし、まずは利用者様が求める事にきちんとお応えし、それから叶えていって欲しいと伝えています。この頃に「自分らしさを叶える場所になる」という弊社のキャッチフレーズを作りました。利用者様にも働くスタッフにも自分らしさを叶えて欲しいという思いを込めたものです。
利用者ニーズを起点にサービスの在り方を構築することで必要とされる企業に
利用者様からのアンケート結果をもとに、サービスの提供の仕方も一つずつ改善していきました。
一例として、「限界訪問数」という独自の指標を作り、全社の訪問能力を可視化し、人員配置や採用に使いました。これができたことにより、シフトに無理が生じず、時間遅れもなくなりました。また時間に間に合わない場合は社内のシステムを使い、「何分遅れる」と入力しておけば、社内の事務スタッフが利用者様宅に電話をして遅れる旨をご連絡する決まりにしました。例え1分でも遅れる場合は、現在も必ず連絡を入れています。
制度について説明する能力に関しては、社内で研修委員会を結成し、外部の講師、社内講師、専門家もお招きし年間に様々な勉強会をしてスキルアップをしています。マナー講習や法定講習ももちろん行っています。
実は、私が新たなサービスを始める際には、この時に限らず必ずご利用者様の困りごとからスタートしています。「利用者様のお困りごとを一緒に解決していく」というスタンスで、弊社がお役立ちできるのであれば新事業として始める、というマーケットインのスタンスで今まで事業を拡大してきました。やはり利用者様の声をしっかりと聞いてサービスに活かしていかなければ本当に必要とされる企業とはならないと考えています。
経営理念でしっかりと社内のベクトルを統一し、マーケットインの考え方で利用者様の声を聞き、看護方針にも取り入れ、自分たちのスキルアップもしました。
下がらない離職率。組織として高いパフォーマンスを発揮するための打ち手
こうした取り組みを経て、株式会社としての利潤の追求のためにすべきこともスタッフたちと共有できてきました。しかし、それでもまだ離職率が下がらないという現実がありました。
先のモデルでは統一期から機能期へ移行する時期くらいです。若くて有能なスタッフが、「育ってくれそうだなあ」と思った矢先に、突然辞めてしまう、の繰り返し。紹介会社に支払う紹介料は増える一方です。
なぜなのだろうと悩みましたが、なかなか答えは出ませんでした。
そこで私は、自分が社員だった場合、どんな会社だったら働きやすいか?働き続けたいか?をもとに仮説を立ててみることにしました。
同時に、スタッフから今起きている社内の問題をヒアリングしました。
【私の仮説】
福利厚生の充実/明確な評価制度の存在/社内IT化が進んでいる/従業員のライフワークバランスが取れている/会社が社会的に認められている
【スタッフからのヒアリング結果】
中間管理職に言っても動いてくれない/研修や勉強会をもっとして欲しい/会議で何が決められているのか情報があいまい/言った、言ってないという話が多くて困る
これらの情報を使って組織の課題を洗い出し、経営課題として改善していくことにしました。
しっかりと課題を解決さえすれば、それは必ず弊社の強みになると考えたのです。次回はこれらをどう解決し自社の強みに変えていったのかをお伝えできればと思います。