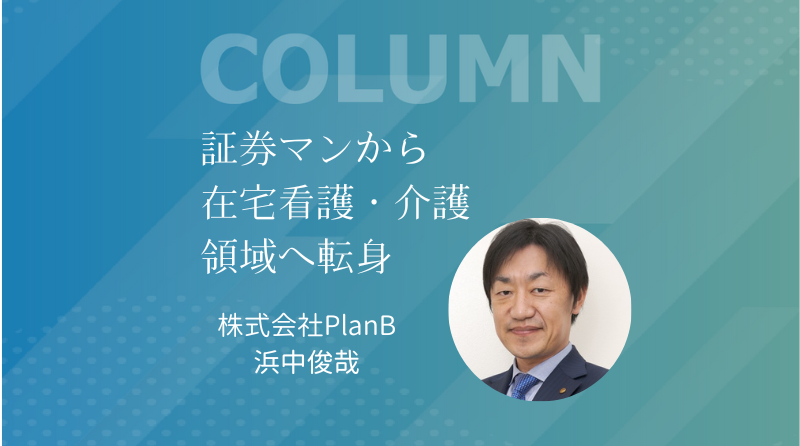株式会社PlanB代表取締役の浜中俊哉と申します。2014年に起業し、現在9年が経ちました。もともと私は介護畑の出身ではありません。証券会社という全く異業種から、参入して起業しました。
私の経験をもとに、そこから得た教訓などをお伝えしてまいります。
今回は起業までの経緯と開業初期の取り組みについて失敗についてご紹介します。
義母の介護を機に地域のインフラ不足に直面
12年ほど前、突然義母が要介護者になりました。
それまで介護保険サービスなど縁のない生活を送っていた私は、全く手探りの状態で申請手続きやサービスの内容について勉強しました。望むサービスが十分に受けられず、その時初めて自分の地域に必要なインフラが不足していることを知りました。
また、その時、さまざまな業者が自宅に出入りすることになり、何度も同じ話をする必要があったり、平日に開催される会議に出たりと、家族としてとても大きな負担を感じました。
起業を決意するに至った反面教師の姿
私の状況について、もう少し遡ります。
私は大学卒業後、東京で証券マンとして勤務していました。しかし、2006年、私は親戚から「経営する町工場に帰ってきて欲しい」と懇願され、跡を継ぐことになりました。ところが日々の中で会社の問題点や改善事項を指摘などしていると、親戚から次第に妬まれ、悪者にされるようになってしまいました。社内の軋轢は大きくなり、親族間の争いに巻き込まれるに至ってしまいます。親戚とはいえ、社員を大切にしないその経営者の姿勢に、「会社の未来はない」と感じて私は退職しました。
義母の介護が必要になったのはそんな状況の最中にあるときでした。
当時はマンションを買ったばかりでもあり、住宅ローンも残っています。再びサラリーマンになろうかとも考えました。けれど、自分が利用者の立場を経験し、そして反面教師としての経営者の姿を傍で見てきたことから、思い切って「利用者の困りごとを解決できる」と「スタッフが輝きながら働くことができる」が両立できる会社を立ち上げようと決めました。
「利用者の立場で経験した困りごとを解決したい」―。強く感じていたのは、在宅生活を支えるワンストップサービスの必要性です。
「あなた達のような訪問看護なんて使わない」営業先から受けた叱咤
当社は、訪問看護ステーションの立ち上げからスタートして、訪問介護1拠点、居宅介護支援事業所1拠点、ナーシングホーム(医療特化型サービス付き高齢者向け住宅)を2棟、神経リハビリセンター(保険外リハビリセンター)、障がい者グループホーム3棟、そして訪問看護ステーションをもう1カ所立ち上げました。2023年9月現在で89名のスタッフが所属しています。当初目指した通り、医療や介護を必要とする人が生活を送るために必要なサービスをワンストップで提供できる体制が実現しつつあります。
しかし、最初から全ての事業が順調だったわけではありません。全くの素人が立ち上げた会社ですから、当たり前と言えば当たり前です。なかなか新規利用者が獲得できず、売上に苦しんだ時期もありました。
地域の病院に何度も頭を下げ、営業活動を重ねていた頃の印象的な出来事として、県立病院の地域連携室の室長から大声で怒られたことがありました。
「あなたたちのような常識のない訪問看護なんて絶対使いません!」と。
後に、これは室長の愛の鞭であったことを知ったのですが、ろくに自己紹介もせずに利用者の紹介してくれというお願いばかりしていたのですから怒られて当然です。むしろ、怒っていただけたことに感謝しています。
訪問看護への思いを伝え県内初の訪問看護ステーション・医療機関間の連携協定が実現
私は帰ってすぐにその室長あてに直筆で手紙を書きました。それを速達で送り、翌日速達が着く時間の2時間後、再度管理者にその病院に営業に行くように指示しました。
手紙ではお詫びの言葉のほか、私が訪問看護事業にかける思いやそれを実現させるためのプロセスを伝えました。最後まで読んでいただけるよう、わかりやすく端的な表現を心がけました。
果たして作戦は見事成功し、室長は昨日の出来事を笑い話にしたうえで管理者との調整を図ってくれたそうです。
数カ月後にはその室長から直筆の手紙をいただきました。
「大変な方々ばかりをお願いしているにも関わらず、皆様の誠実さには感謝しています。近隣の先生方からも感謝の言葉が聞かれます。私どもとしては皆様がなんとも心強い存在です」
こうしたやり取りが発展して、数年後にその病院とは三重県で初の医療機関連携協定を結ばせていただけることにもなりました。室長は引退されましたが、いただいた手紙は今でも大切に額に入れてあります。
組織全体で同じ方向を目指すための経営理念
事業にかける想いを届けるべき相手は、地域の方だけではありません。
弊社は創業時から経営理念を全員で昼礼時に唱和しています。

経営理念は非常に大切で、経営者の思いや従業員への行動指針を示す会社の羅針盤となるものです。この事業に限らずお飾りであってはいけないと考えています。毎日唱和するからこそ、自分の行動をぶらさないための軸にもなりますし、スタッフにも浸透していきます。89人のスタッフを抱える今も、この経営理念を共有することで組織が機能していると思います。
私たちが提供するサービスは、ご本人様の生活が最優先でなければいけません。ここが病院で提供する医療サービスと異なるところであり、究極のサービス業を提供しているという意識を持たなければなりません。
ご本人に安心していただく環境を作り、私たちとの信頼関係が構築出来れば、仕事にもやりがいが生まれ、地域になくてはならない企業になれると考えています。
まさにそれが弊社の経営理念なのですが、病院で働いていた時の看護師の感覚のまま利用者さまの居室でふるまうなど、意識にバラつきがあってはマネジメントもうまくできません。在宅領域でサービスを展開する組織のマネジメントは、意識改革改革から始まるものと思いましたし、経営理念の唱和はそれを浸透させていくための取り組みでした。
というのも、事業を立ち上げ当初、この業界のサービス業としての意識の薄さに非常に驚きました。ここに在宅医療介護の概念を変えていくための大きなポイントがあると感じました。
次回は、医療・介護業界に参入して感じた違和感や事業展開と自社としての強みを確立させていくまでのプロセスについて書かせていただきたいと思います。