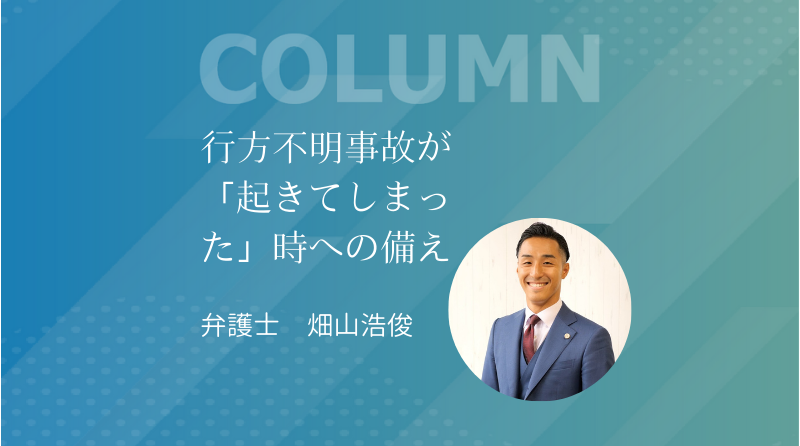1.精神論に陥りがちな「事後対策」とその理由
前回の記事では、裁判例を分析し、事前対策の重要性を考察しました(*前回の記事:行方不明事故にどう備える?介護事業者が実践すべき対策~事前対策編~
皆様の介護施設でも、利用者が職員の気付かない間に離設しないよう様々な対策を講じられていると思います。例えば、施設の出入り口にセンサーを設置する、離設時に音が鳴るような仕組みを導入する、エレベーターを暗証番号式にする、入口付近にある事務室から出入り口の様子をしっかり確認するよう事務室で勤務する職員に指示する等、介護施設の状況に応じて様々な取組みがなされています。
これらは、離設事故が生じないようにする「事前対策」です。
筆者が独自に調査したところ、「事前対策」に注力する介護施設は多いのですが、いざ離設事故が発生した後の「事後対策」に注力する介護施設は少ない印象を受けました。
具体的には、「事後対策」については、「職員で手分けして必死に探します」というような精神論に依拠した対策に偏る傾向があり、システマチックな捜索体制を構築できていない介護施設が多数見られました。
その理由の1つとして、「介護施設で利用者を預かっている以上、離設事故はあってはならない。」との強い意識が根柢にあるのではないかと筆者は考えています。
皆様もご存知のとおり、各自治体が運営している『認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク』(※編集注…参考:2014年9月19日老健局長名通知<「今後の認知症高齢者等の行方不明・身元不明に対する自治体 の取組の在り方について」)という事業があります。
この事業は、主に、認知症等により、外出中に道に迷う可能性のある高齢者等を早期発見する制度です。事前登録した対象者が行方不明になった場合、警察や当該事業に協力する事業者(コンビニ、ガソリンスタンド、介護事業者など)が皆で行方不明者を捜索しようという取組みです。
この事業は、在宅における認知症高齢者等を対象にして策定されています。
実際に、筆者の調べた限り、認知症の利用者が介護施設に入所する際に、介護施設から「万が一、施設から出て行ってしまった場合の備えとして、見守り・SOSネットワークに事前登録しておきませんか。」といった具合に活用している例はほとんどありませんでした。
つまり、介護施設側も、自治体側も、そして利用者のご家族も、「介護施設に入所しているのだから、離設事故が起きないように備えておくのが当然だろう。」と考えているのです。
このような意識から、介護施設側は、「事前対策」にはしっかりと費用を投じ、システムを導入するなどして万全の策を講じますが、「事後対策」については、「あってはならない。離設事故は恥だ。」という気持ちから、対策が疎かになるのではないかと思います。
結果、離設事故発生時には、「職員の皆で手分けして頑張って探そう!」という精神論に依拠した人海戦術に頼る他なくなるのです。
2.離設発覚後の「捜索」の重要性:裁判例の考察
離設事故により利用者が亡くなった場合、ご遺族が介護施設に対し、安全配慮義務違反があるとして損害賠償を求める事態に発展することがあります。
裁判では、事前対策のみならず、離設事故発生後の捜索が十分であったのか、という事後対策の点が争われることもあります。
前回の記事で紹介した裁判例(さいたま地方裁判所平成25年11月8日判決)においても、離設後の捜索についての過失の有無が争われました。
事例のおさらいです。
アルツハイマー型認知症が重症化したため、小規模多機能型居宅介護施設に入居した入居者が、介護職員が目を離した隙に同施設外に出て行方不明となり、その3日後に死亡しているのが発見された事故につき、亡くなった入居者の妻子が施設に対し、損害賠償を求めた事案
この裁判例では、離設後の捜索は十分であったとして、この点の過失は認められませんでした。
具体的には、この裁判例では、離設事故発生当時、職員1人が利用者3人をみていた状況でしたが、この職員は、利用者が離設したことに気付いた後、施設内を探し、施設外を探し、上司に連絡した後、もう一度施設内を探しました。そして、職員から連絡を受けた施設は、すぐに警察に通報し、警察犬も出動しました。
裁判所は、これらの対応をもって「過失があったとまでいうことはできない」と判断しています。
しかしながら、筆者は、この裁判例を読むと、逆の結論になる可能性は十分にあると考えています。
というのも、この施設では、行方不明になってしまった場合の緊急対応マニュアルは作成されていませんでした。マニュアルが無いということは、それに基づいた訓練も実施されていなかったということを意味します。
原告側は、まさにこの点を強く主張しています。
緊急対応マニュアルを作成しておらず、研修や指導も行っていない状況で、緊急時に備えた指導や体制が確立されていなかった、複数の職員が個々に判断したために、対応が不適切になり発見が遅れたのだ、捜索の仕方は無秩序・無計画で不適切だなどと主張したのです。
裁判所は、具体的な捜索状況を見て、過失があるとまでは言えない、と判断しましたが、逆の結論になっていても不思議ではありません。
上記の原告の主張にご遺族の怒り・悔しさ・悲しみが表れていると思います。
では、介護施設は具体的にどのような「事後対策」を講じれば良いのでしょうか。
3.介護施設に求められる「事後対策」とは
(1) 行方不明事故発生時の対応マニュアルの整備
まず、行方不明事故発生時の対応マニュアルを整備するようにしましょう。
ポイントは、捜索の手順をマニュアル化することです。
筆者が以前、介護施設で行方不明事故防止研修を実施した際、参加した職員に対し、「今、利用者が施設から出て行ったとしたら、皆様はどのように捜索しますか。施設内、施設外をどの順番で捜索するか。施設内の捜索は具体的に何分実施するのか。具体的に検討して下さい。」と質問したところ、各自、バラバラの回答でした。これこそ、無秩序・無計画な捜索方法です。予めマニュアルがあり、周知徹底されていれば、バラバラの回答になることはありません。
各施設の状況にもよりますが、対応マニュアルの一例を挙げます。
・行方不明事故発生時は、まず施設内の捜索を10分間行う。
・同時に社内SNSを通じて社内全体に行方不明事故発生を伝達し、施設長に電話する。
・施設内捜索を10分間実施しても見つからない場合は、施設の敷地内を10分間捜索する。
・それでも見つからない場合、ご家族に報告すると同時に、警察へ捜索願を出す。
・施設外の捜索を職員と手分けして実施する。
・施設外の捜索について、協力してくれる事業者へ一斉に連絡し、協力を仰ぐ。
・ご家族へは、捜索状況を1時間に1回は報告する。
上記はあくまで一例ですが、仮にこのような手順を決めていれば、効率的に探すことが可能になります。
注意点は、「思い込みを排除すること」です。
例えば、出入り口のセキュリティ対策を万全にしている施設では、「まさか施設の外に出て行くはずが無い。」と思い込み、ひたすら施設内を捜索してしまうケースがあります。
例えば、設備の不具合等により、セキュリティがオフになっている出入り口から利用者が出て行く場合もあり、このような場合、施設内を探し続けていれば、発見が遅れ、重大事故に繋がるリスクが高まります。
思い込みは排除し、捜索時間、捜索場所、捜索方法を念入りに決めるようにしましょう。
(2) 捜索ネットワークの構築
次に大切なことは、自分たちだけで探すのではなく、地域に協力を求めることです。
介護施設では「離設事故はもっての他だ。恥だ。」という思いから、行方不明事故が発生したとき、介護職員だけで必死に捜索するケースがあります。捜索から何時間も経って、いよいよ焦りが昂じてようやく警察へ通報する事例もあります。
ここは恥を捨てて下さい。
介護施設のプライドよりも利用者の命の方が大切です。
介護職員だけではなく、地域の事業者、自治会などの力を借りるようにしましょう。
前述した見守り・SOSネットワークのようなものを介護施設自らが先んじて構築しましょう。
具体的には、介護施設の近くにある公共機関やコンビニ、介護事業所、保育園、幼稚園、ガソリンスタンド、自治会などとの間で、いざというときの協力体制を築きましょう。
「そんなこと出来ない」と思うでしょうか。
たしかに簡単ではありません。
しかし、実際にこのような体制を構築している介護施設も存在しています。
「困ったときはお互いさま」の精神で、介護施設から先んじて地域との関係性構築に取り組みましょう。
4.実践と改善の重要性
マニュアルを作成しても実践しなければ「絵に描いた餅」に過ぎません。
いざマニュアルを実践した時に、様々な課題が見えてくるはずです。実践を通じ、発見した課題をどのように解決していくのか、介護職員や地域の協力者と話し合い、改善していきましょう。
何度も何度も素振りをするからこそ、いざという時に力を発揮できるのです。
5.まとめ
前回と今回の二回にわたり、行方不明事故対策について考察していきました。
実は、筆者も、過去に認知症の祖父が入院先から出て行き、入院先から10㎞も離れたところで保護されたことがあります。あのときは、心配で心配で生きた心地がしませんでした。もちろん、病院から居なくなったことに気付いたスタッフの方々も肝を冷やしたことでしょう。
認知症の利用者が介護施設から離設してしまうケースは、関わる全ての人にとって重大な問題です。
だからこそ、「事前対策」だけではなく、今一度、行方不明事故が発生した後にどう対応するのか、という「事後対策」についても見つめ直してみましょう。