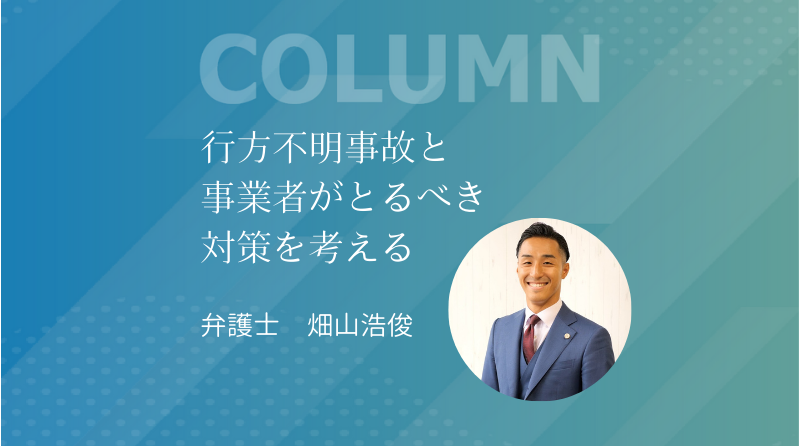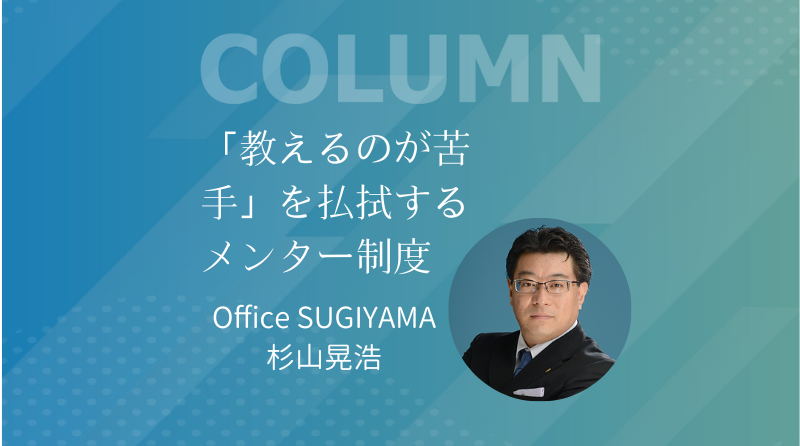ここは小規模多機能型居宅介護事業所。
「通い」「訪問」「宿泊」の各サービスを組み合わせて在宅での生活支援などを行う地域密着型のサービスだ。
この事業所を3カ月ほど前から利用している鈴木さん(仮名)。
要介護4の男性で、重度の認知症の利用者だ。歩行は自立している。
鈴木さんは、宿泊サービスを利用している際、度々、玄関や窓から出て行こうとする言動があり、職員も対応に頭を悩ませていた。
そんなある日。最悪の事態が起こった。
職員が他の利用者をトイレ介助している間に、鈴木さんが行方不明になったのだ。
目を離したのはほんの数分間に過ぎない。警察へも至急連絡し、懸命の捜索が行われたが、鈴木さんは一向に見つからない。
行方不明事故の発生から3日後、施設から約590m離れた畑の畝で、うつぶせの状態で倒れている鈴木さんが発見された。
鈴木さんは死亡していた。
(さいたま地方裁判所平成25年11月8日判決の事例を元に筆者が作成)0.はじめに:行方不明事故と結果の重大性
厚生労働省によると、わが国の認知症高齢者の数は、2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人に達することが見込まれています(厚生労働省『認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~』)。
認知症には様々な症状がありますが、歩き回って帰り道がわからなくなり、行方不明になってしまうケースがあります。
警察庁によると、令和2年度における認知症又はその疑いによる行方不明者の数は、実に1万7565人にも上ります(警察庁生活安全局安全企画課『令和2年における行方不明者の状況』)。なお、この行方不明者数は警察に行方不明者届が出された者の数ですので、実際の行方不明者はこれよりも多いと予想されます。
介護施設においても、認知症の利用者が職員の気づかぬうちに介護施設から出て行き、行方不明になる事例が生じています。また、幸い発見できたものの、介護施設から出て行き、職員総出で探し回り肝を冷やしたというケースも多々発生しています。
仮に、認知症の利用者が介護施設外に出て行ってしまった場合、交通事故などの何らかの事故に遭ったり、発見が遅れたりすることで、命を落とす危険があります。実際に、真夏では脱水症状が原因で、真冬では凍死が原因で命を落としてしまう事故が発生しています。
このように、ひとたび行方不明事故が生じると、その結果は人命に関わる重大事故に発展する可能性があり、介護事業者としては、事前の対策・事後の対策・日頃からの訓練の実施が非常に重要になります。
そこで、今回と次回の2回に分けて、介護施設で発生した行方不明事故について、介護事業者の安全配慮義務違反の有無が争われた裁判例を元に、介護事業者が実施すべき対策を検討します。
1.裁判例から考える行方不明事故防止の事前対策の重要性
冒頭のケースは、さいたま地方裁判所平成25年11月8日判決の事例の概要です。
この裁判では、介護事業者側の次の3つの点について、過失の有無が争われました。
(1) 介護職員の利用者に対する注視、監視義務違反の有無
⇒職員はきちんと利用者を見守っていたのか。
(2) 本件施設の設備の設置義務違反の有無
⇒なぜ出ていったことに気付けなかったのか。
(3) 行方不明後の捜索についての過失の有無
⇒捜索方法に問題はなかったのか。
本稿では、(1)と(2)を考察し、次稿で(3)を考察します。
前提として、判決文から判明した利用者鈴木さんの状態をまとめます。
<鈴木さんの状態>
要介護4、重度の認知症。起居、移乗動作、歩行、食事等は自立。
ショートステイを利用していた約3カ月の間で、玄関や窓を開けようとする言動、「帰りたい」と帰宅願望を口にするといった言動が複数回確認されている。
行方不明事故発生当日、起床後から徘徊する言動が見られた。
(1) 介護職員の利用者に対する注視、監視義務違反の有無
さて、鈴木さんは上記のような状態でした。介護職員は1人、利用者は鈴木さんを含む計3人でした。行方不明事故発生当日も鈴木さんには徘徊が見られたため、担当職員は相当大変だったと思います。
事故当日、担当職員は、他の利用者のトイレ介助のため、鈴木さんのいるリビングを離れました。
担当職員は、リビングで物音がした際に、鈴木さんの様子を2回見に戻っています。
その後、トイレ介助で鈴木さんから5、6分程度目を離したところ、鈴木さんがいなくなっていたのです。
裁判所は、「介護職員として要求される注意義務は果たしていたといえる。」として、介護職員の利用者に対する注視、監視義務違反があったとはいえないと判断しました。
人員基準を満たしている状態でしたし、物音がするたびに鈴木さんの様子を見に戻っていたのですから、担当職員としてはやるべきことはやっていました。この裁判所の判断は正しいと言えるでしょう。
(2) 本件施設の設備の設置義務違反の有無
しかしながら、この小規模多機能型居宅介護施設を運営する法人の義務違反を認めました。具体的には、「施設職員が気付かないうちに鈴木さんが施設外へ出ることを防止する措置をとる義務を怠っていた」と認定しました。
今回の事故が発生した小規模多機能型居宅介護施設は、2階建ての民家を改装した物件を使用して運営されており、居間、食堂、キッチンが一つの部屋になっており、キッチンに勝手口がありました。リビングと壁を一枚隔てた隣に洗面所とトイレがありました。
主な出入り口は、玄関と勝手口ですが、普段施錠されていました。
その他、居間にある開口部が床面まである窓にスロープが設けられていました。この窓の鍵には回して開ける取手の脇に施錠用のつまみが付いており、そのつまみを操作しないとロックがかかる仕様になっていました。
さて、普段、勝手口は、つまみをつまんで回せば開くサムターンタイプの鍵で施錠しており、勝手口の内側にはカーテンが付けられ、発泡スチロールが積み上げられていました。
この行方不明事故の当日、勝手口の鍵が開いていたことから、鈴木さんは勝手口から出ていったと推認されました。そして、この勝手口には、開いた際に音が鳴るような器具は設置されておらず、裁判所はこの点を指摘して防止措置義務違反があると認定したのです。
具体的には、「本件施設において利用者が外へ出ることが可能な場所に関して、スロープが設置してあるリビングの窓のように、鈴木さんが簡単に鍵を開けることができないようなロックがかかる鍵を設置していたところはともかく、勝手口の鍵のように、つまみを回せば簡単に鍵が開いてしまうようなところに関しては、少なくとも、ドアが開いた場合に音が鳴る器具を設置するなどして、鈴木さんが外に出た場合には、施設職員が直ちに気付くことができるような措置を講じておくべきであった」と判断し、義務違反を認定したのです。音さえ鳴れば、当時の担当職員が直ちに鈴木さんが出ていったことに気付くことができただろう、ということです。
2.介護事業者が注意すべきポイント
(1) 落とし穴が無いか再点検しよう
以上の裁判例の分析を読んで、ヒヤリとした介護事業者の方々も多いのではないでしょうか。
普段、仕事をしている場所・空間は、皆様にとっては安全・安心な場所であるとの思い込みがあり、「うちの事業所は大丈夫」と盲信してしまう傾向があります。
実際、筆者が関わっている顧問先でも、行方不明事故が生じるケースがあり、その際、多くの事業者は、「まさかそんなところから出るなんて」という驚きの声を上げています。
例えば、「廊下の窓から出てしまったが、まさかそんなことが可能なほど体力があったとは・・」といった声や、「2階の樋をつたって降りたなんて・・・」という驚きの声です。
物事に「絶対」はありません。
このような裁判例を検討することを通じて、自分たちの事業所に潜んでいる落とし穴を発見する取組みを定期的に実施することをお勧めします。
(2) システムを過信しないことが大切
上記裁判例は、勝手口のドアが開いた際に音が鳴る器具などを設置しておけば介護職員が利用者の出て行ったことに気付けたはずだ、と述べており、事前対策の一例に言及しています。
昨今は、ICTの発展に伴い様々な便利なシステムが介護現場でも導入されています。
例えば、GPSセンサーを活用して行方不明事故が生じた際も位置情報をいち早く確認して安全確保することで重大事故行方不明事故の防止に取り組んだり、施設全体にセキュリティ装置を設置し、出て行った際に職員に通知されるシステムを導入し、離設を未然に防止する対策を講じるなど、革新的な事故防止対策が広まっています。
しかしながら、皮肉にも、こういったシステムを過信するあまり、介護職員が思考停止に陥り、行方不明事故に繋がっているケースが生じています。
例えば、GPS付のセンサーを利用者がトイレに置きっぱなしにしてしまい、離設したことに速やかに気付くことができなかったという事例、施設のセキュリティ装置について職員が非常階段の装置を切っており、その非常階段から利用者が離設し、行方不明になってしまった事例などが実際に生じています。
これらの事故は、「システムを過信したことによりヒューマンエラー」に他なりません。
たしかに、様々な便利な機器が日進月歩で開発され、確実に、人の手を頼らなくても事故防止ができる世界観は実現されつつあるのかもしれません。
しかしながら、結局、それを使いこなすのは「人」です。
システムを過信することで、肝心の「人」が思考停止に陥ってしまっては本末転倒です。
「正しいインプットが無ければ、正しいアウトプットが出ない」というのがシステムの鉄則です。正しいインプットとはすなわち、正しい使い方を「人」が実践することに他なりません。
その意味では、行方不明事故にまつわる裁判例を分析し、基本に立ち返り、問題の本質から考える習慣が何よりも必要です。
「考える習慣」を介護職員全体で醸成していくリスクマネジメント研修の重要性は、今後も一層高まっていくのではないでしょうか。便利になっていく世の中だからこそ、原点に立ち返る習慣を身に付けていきましょう。