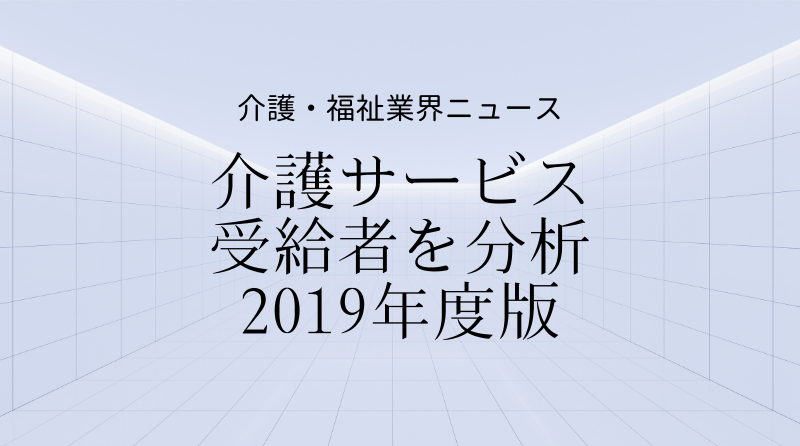厚生労働省は8月31日、2019年度の介護事業所保険事業報告(年報)を公表しました。全国における被保険者数やサービス受給者の状況をまとめ、報告しています。第1号被保険者数の対前年度伸び率(0.8%増)に対し、要介護または要支援の認定者数の対前年度伸び率(1.6%増)やサービス受給者数の対前年度伸び率(2.3%増)が上回る結果となっています。サービス種別の伸び率や地域差についても見ていきましょう。
*関連記事:介護職員の不足数2年後には約22万人に、厚生労働省が全国の集計数を公表
要介護等認定者数は11万人増で過去最高:全国の概要
まず、全国的な数値の概要は以下の通りです。
第1号被保険者数
*3,525万人(2019年3月末時点)→ 3,555万人(2020年3月末現在。対前年度比0.8%増、過去最高)
2020年3月時点の第1号被保険者のうち、前期高齢者 (65歳以上75歳未満)は1,726万人で48.5%、後期高齢者(75歳以上)は1,829万人で51.5%でした。前期高齢者は19年度に続いて対前年度比で微減(0.2%減)、後期高齢者は約33.7万人増(1.9%)で過去最高となっています。なお、高齢社会白書(2021年版)によると、前期高齢者人口のピークは2016年にすでにピークを迎えており、後期高齢者人口は2054年まで増加傾向が続く見込みです。

【グラフ】令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)の「ポイント」から抜粋
要介護(要支援)認定者数
*658万人(2019年3月末時点) → 669万人 (2020年3月末時点。対前年度比1.6 %増、過去最高)
2020年3月時点の要介護及び要支援認定者(以下・認定者)数は、669万でした。このうち、第1号被保険者は656万人(男性204万人・第1号被保険者に対する割合31.1%、女性452万人・68.9%)、第2号被保険者は13万人(男性7万人・第2号被保険者に対する割合53.8%、女性6万人・46.2%)です。
認定者数の伸び率が、第1号被保険者数の伸び率を上回っています。
また、認定者を要介護(要支援)状態区分別にみると、要支援1が93万人、要支援2が94万人、要介護1が135万人、要介護2が116万人、要介護3が88万人、要介護4が82万人、要介護5が60万人で要介護3が最も多くなっています。厚労省は、この結果について、「軽度(要支援1~要介護2)の認定者が約65.6%を占めている」とまとめています。

【グラフ】令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)の「ポイント」から抜粋
サービス受給者数(1カ月平均)
*554万人(2018年度)→ 567万人(2019年度。対前年度比13万人/2.3%増、過去最高)
2019年度のサービス受給者数の1カ月当たり平均人数は、567万人でした。第1号被保険者数と要介護(要支援)認定者数よりも対前年度伸び率が上回っています。サービス受給者数は、要支援者への訪問介護と通所介護が完全に介護予防・日常生活支援総合事業に移行した2017年度に1度減少していますが、その後は増加を続けて過去最高を更新しました。

【グラフ】令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)の「ポイント」から抜粋
また、利用者負担を除いた2019年度の累計給付費(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費)は、過去最高の9兆9,622億円となっています。
都道府県別では和歌山・大阪などで高い認定率
次に、都道府県別の状況を見てみます。
第1号被保険者数に占める認定者の割合は高い方から和歌山(21.8%)、大阪(21.7%)、愛媛(20.9%)、京都(20.8%)、島根(20.8%)となっています。割合が低いのは、埼玉(15.4%)、茨城(15.4%)、山梨(15.6%)、栃木(15.8%)、静岡(16.1%)、千葉(16.3%)などの順です(全国平均値は18.4%)。

【グラフ】令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)の「概要」から抜粋
ただし、認定者数の対前年度比伸び率では、埼玉や千葉は上位にあります。

【グラフ】令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)の「概要」から抜粋
訪問看護・居宅療養支援の受給者数増加が顕著、デイはマイナス県も
最後に、事業種別の状況を見てみましょう。
2019年度の居宅介護サービス(介護予防含む)受給者数は、1カ月平均で約384万人(対前年度比2.7%増)、地域密着型(介護予防含む)サービス受給者は1カ月平均で約88万2,000人(対前年度比2.3%増)、施設サービス受給者は1カ月平均で、介護老人福祉施設55万人(対前年度比1.5%増)、介護老人保健施設35万人(対前年度比0.4%減)、介護療養型医療施設3万人(24.6%減)、介護医療院1万6,000人(295.5%増)でした。
より細かく見ると、居宅サービスと地域密着型サービスでは、要介護1と要介護2がボリュームゾーンであり、合わせて受給者数の半数を占めています。



【表・グラフ】令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)の「概要」から抜粋※表の値は年度累計
これに対し、施設サービスの受給者数は要介護4が34.1%と最も多くなっています。

【グラフ】令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)の「概要」から抜粋※表の値は年度累計
また、主な居宅サービスについてサービス受給者数のデータを前年度と比較してみると、伸び率が高いのは居宅療養管理指導(全国平均7.7%)や訪問看護(同7.6%)で、これらは全国でプラスとなりました。このほかに、福祉用具貸与や居宅介護支援でも全都道府県で前年度比プラスとなっていました。逆に訪問入浴介護では、全国平均がマイナスとなっています=表=。

*【表】<都道府県別>居宅介護(介護予防)サービス受給者数 - (当年度累計)データの2019年度及び2018年度のデータを基に編集部で作成