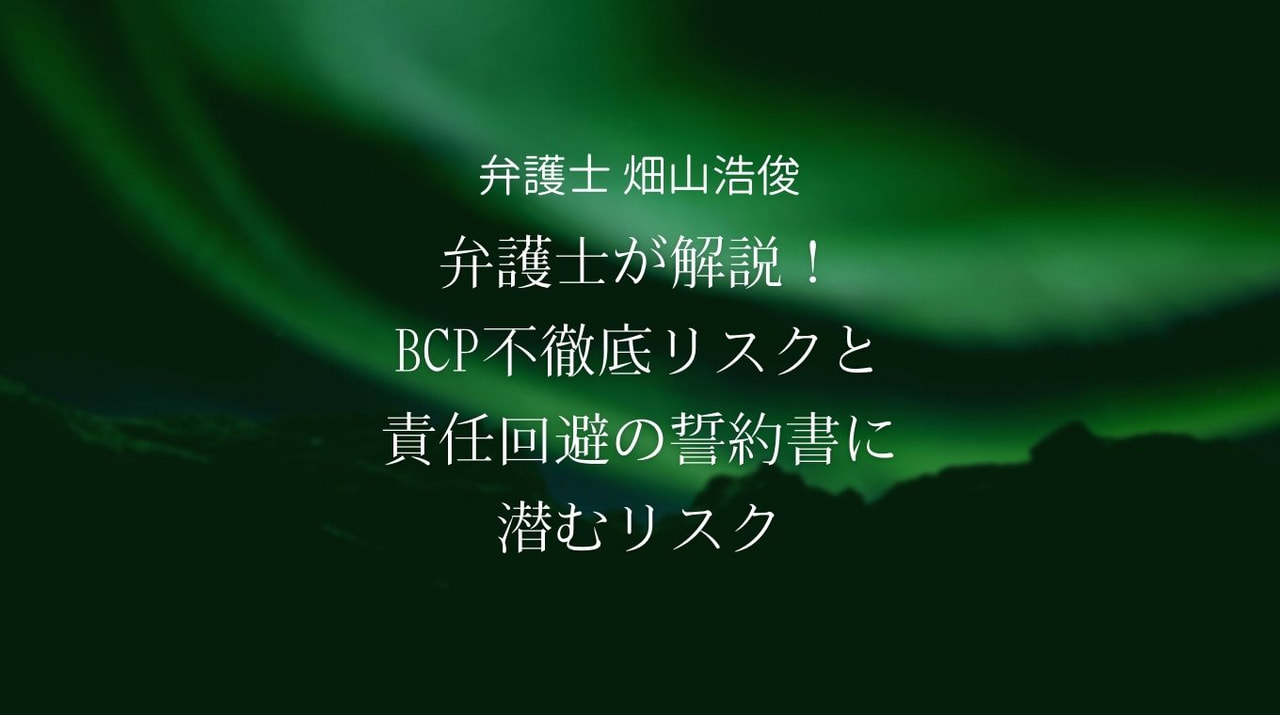1.BCPセミナーを通じて感じたこと
令和3年度の介護報酬改定で、全ての介護事業者を対象にBCP(業務継続計画)の策定が義務付けられました(3年間の経過措置有り)。
以前、『弁護士視点で見るBCP策定の重要性とリスクマネジメント』という記事で、BCPの不徹底が法人の法的責任に直結することをお伝えしました。その点を改めて強調してお伝えするために、現在の介護事業者におけるBCP策定状況の実態と、そこから想定される法的リスクについて解説します。
先日、新型コロナウイルス感染症に関するBCP策定にあたって、気を付けるべき法的なポイントを解説するセミナーを実施しました。その際、参加者約400法人を対象にBCP策定の進捗度合いを質問するアンケートを実施しました。アンケートの結果、「BCPを一通り完成させた」と回答した法人は全体の約6%でした。ほとんどの法人が、B C Pの策定に着手していないか、着手しているものの作成途中という状況です。
この結果からは、「3年間の経過措置があるので、まだ大丈夫だろう。」と考えている法人が多いことが推察されます。しかしながら、このようなスタンスで日々を過ごしていると、日常業務に追われるうちに、気が付けば3年間の経過措置が終了する間際になっている、ということは容易に想像できます。その段階で、事業所の実情に応じたBCPを策定することはほとんど不可能です。結局は他の介護事業者のBCPをコピーアンドペーストし、とりあえず形だけ整える、という対応にならざるを得なくなります。
これは私の単なる推測ではありません。実際に、今までにも、他の介護事業者の書式やインターネット上で公開されている書式をそのままコピーアンドペーストしたことで、事業所の実態と整合しないまま利用されている書面を多く目にしてきました。これらは、災害対策マニュアル、事故対応マニュアルのようなマニュアルだけでなく、利用契約書、重要事項説明書といった重要書類にまで及びます。この流れがBCP策定の一点で劇的に変化するとは考えられません(なお、コピーアンドペースト自体がダメだ、と言っているのではありません。各事業所の実態との整合性を確認せずそのまま使用することが良くないのだ、という点にご留意下さい。)。
また、マニュアル等が、事業所の実態と整合した内容で作成されていたとしても、これらが事業所内で周知徹底されておらず、管理者でさえ運用の仕方がわかっていないケースも多く見られます。
ここで一つ、平成23年3月11日に発生した東日本大震災にまつわる悲しい事件を紹介します。
日和幼稚園バス津波被災事件です。
この事件は、園で作成されていた災害対策マニュアルの内容を実践しなかった結果、園児5名が津波に巻き込まれ、尊い命が失われてしまった件について、同園を運営する法人等の法的責任が争われた事件です(仙台地裁平成25年9月17日判決、なお、同事件は高裁にて和解で終結)。
この園では、災害対策マニュアルが作成されており、その内容は、「地震の震度が高く、災害が発生するおそれがある場合は、全員を北側園庭に誘導し、動揺しないように声掛けして、落ち着いて園児を見守る。園児は保護者のお迎えを待って引き渡すようにする。」というものでした。日和幼稚園は高台に位置していたので、大規模地震の際には一旦園で待機しよう、という、園の実態に合った合理的な内容でした。
しかしながら、このマニュアルは職員間で共有されておらず、ほとんどの職員がその内容を知りませんでした。そして、あろうことか、同園の園長は、大震災発生直後、「園児にとっては保護者の元にいるのが一番安心できるだろう」と考え、園児を保護者の元へ送るべく、園から園児を乗せたバスを出してしまう、というマニュアルとは正反対の指示を出してしまったのです。
その結果、園児を乗せたバスは津波に巻き込まれ、バスは横転し、園児5名が車内で火災に巻き込まれ死亡するという悲惨な事故が発生したのです。なお、津波は、高台にあった日和幼稚園にまでは到達しませんでした。
マニュアルの不周知とその不徹底が、尊い園児の命を奪ったのです。
この事案は、そのまま介護事業者のBCPに置き換えることが可能です。
BCPでは、業務の継続と共に、その前提として、職員や利用者の大切な人命を守ることが求められています。他の介護事業者が作成したBCPは、あくまでその介護事業者に適合するBCPであり、これを単にコピーアンドペーストしただけでは、自社の運営する介護事業所の実態に伴わない形だけのBCPになることは自明ですし、このような形骸化したBCPが、職員間で周知され、運用されるわけがありません。
もしかしたら、実地指導はそのような形骸化したBCPであっても乗り切れるかもしれません。
しかしながら、BCPを作成し、これを運用するのは、実地指導を乗り切ることが目的ではないはずです。
日和幼稚園バス津波被災事件のような凄惨な事件が、皆さんの事業所で起こることがないよう、このことを肝に銘じて、どうか今から少しずつでも良いので、BCP策定に着手していきましょう。
2.「一切責任を負いません」という誓約書に潜む2つのリスク
【ケース】
弁護士の先生に質問があります。
介護事業を運営する中で、新型コロナウイルス感染症のリスクはどこまでも付きまといます。我々は感染対策を講じて事業運営しておりますが、そんな中、仮に利用者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、利用者やそのご家族から訴えられるようなことを予め避けたいと思います。広島県三次市で訪問介護事業を運営する法人が訴えられた話を聞いて怯えています。
そこで、利用者やそのご家族に対して、「利用者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、当法人は一切責任を負いません。」という内容を明記した誓約書にサインしてもらおうと考えています。このような誓約書があれば、万が一、新型コロナウイルス感染症で利用者がお亡くなりになった場合も責任回避することができると聞いたことがあります。この理解で間違っていないでしょうか。
新型コロナウイルス感染症に関する訴訟リスクを予め回避するために、上記のような「一切責任を負いません」という誓約書のサインを求めることは問題無いか、という質問を受けることが良くあります。実は、これは新型コロナウイルス感染症のケースに限ったことではなく、「転倒事故、誤嚥事故について一切責任を負いません」という誓約書について、同様の質問を受けることがあります。
結論から申し上げますと、このような誓約書の作成について筆者はお勧めしません。
以下に述べる2つのリスクがあるからです。
一つ目のリスクは、消費者契約法に違反し、無効になる可能性があるという点です。
消費者契約法第8条には、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除・・・する条項」については「無効とする」という定めがあります(同法同条1号参照)。つまり、事故が起きたり、新型コロナウイルス感染症に感染したとしても、事業所が一切責任を負わない、という趣旨の条項は、利用者の利益を不当に害するとして、法的に無効になってしまうのです。これは、せっかく作成した誓約書が、なんの効果もない無意味なものとなってしまうことを意味します。
介護事業者は、利用者に対して、安全配慮義務を負っています。介護利用契約に内在する本質的な安全配慮義務が、上記のような誓約書だけで無くなることはあり得ないのです。
二つ目のリスクは、利用者やご家族から不信感を抱かれてしまう点です。
このような誓約書は、介護事業者に一方的に有利な内容であることが明らかです。利用者やご家族は、このような誓約書を見て、どのように感じるでしょうか。
「この事業所は、いざという時に責任を取らないつもりだな。」と感じるのではないでしょうか。皆様がもし、利用者のご家族の立場であった時、このような事業所に、大事な家族を預けようと思うでしょうか。
利用者やご家族に、このような不信感を抱かれてしまえば、介護事業運営において最も重要な「信頼関係」が破壊されてしまうリスクがあります。
以上から、筆者は上記のような誓約書の作成の当否について法律相談を受けると、「何の得も無いので辞めた方が良い」と回答しています。
3.丁寧な説明こそが安全配慮義務履行に繋がる
上記のような、法的にも事実上も問題のある誓約書を作成する、という手段に逃げるのではなく、真正面から、日々、どのような点に意識して感染対策を講じているのか、そして、どれだけ感染対策を講じても感染リスクは存在しており、万が一、利用者や職員が感染症に罹患した場合は、具体的にはこのような対策を実践する予定である、といったように、事態が発生する前の対策内容のみならず、事態が生じた後の事業継続計画の内容を丁寧に利用者やご家族に説明することが重要です。
人は、見通しの立たないことに不安を覚えます。
先回りして、想定されるリスクが生じた場面に対する具体的な行動指針を職員だけではなく利用者やご家族と共有する事こそが、介護事業者と利用者・ご家族との間の信頼関係の構築に繋がり、何より、それこそが安全配慮義務の具体的な履行になります。
「大切なお知らせ」というような配布物として資料提供して、具体的に説明するよう心掛けましょう。作成した説明資料に法的な問題が無いか、不安なときは、顧問弁護士などの専門家に事前にチェックしてもらうと良いでしょう。
真正面から向き合うことは、精神的に辛い作業かもしれませんが、最も重要で本質的なことだと思います。
以上