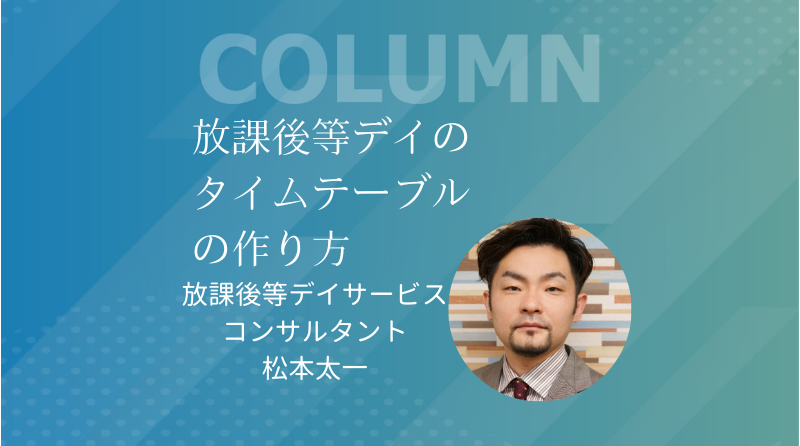放課後等デイサービスコンサルタントの松本太一です。この連載ではこの事業への参入に関心を持っていらっしゃる方に、ぜひ知っていていただきたいポイントをご紹介しております。療育の現場にあまり関わったことのない経営者の方にもぜひ参考にしていただければ幸いです。
前回は、タイムテーブルを作る上での前準備として「来所時間の明確化」について解説しました。今回はいよいよタイムテーブル作りの具体的な手順やポイントについて説明します。
タイムテーブルは計画的な支援プログラムを実施するために作成するもの
前回、タイムテーブルがない事業所では支援が行き当たりばったりになってしまい、子どもたちの問題行動が頻発してしまうことを指摘しました。そのこともあって、放課後等デイサービスのコンサルティングに入らせていただく前に、経営者や管理者に「タイムテーブルは作成できていますか?」とお聞きします。
このとき、「作っています」というお答えがあっても、事業所に伺うとタイムテーブルが形になっていないケースが大変多いのです。
例えば、以下のような予定表を使っている事業所があります。
- 宿題
- おやつ
- 運動(集団プログラム)
- 帰りの会
これではタイムテーブルとは呼べません。何をどの順番で実施するのかは書いてあっても、時間が書いていないからです。
こうした不完全な予定表をもとにプログラムを実施すると、「1.宿題」と「2.おやつ」をお子さんがそれぞれバラバラのペースで進めることになってしまいます。その結果、集団で行う「3.運動」を何時から始められるかがわからず、事前にどのような運動プログラムを実施するのか計画することができません。
そのため、おやつを食べたり宿題をしたり後は自由時間にせざるをえず、無計画な過ごし方が常態化してしまいます。すると、暇になった子どもたちが乱暴な遊びを始めてしまい、収拾がつかなくなってしまいます。
各プログラムの始まりと終わりの時間は必ず決めよう
タイムテーブルを機能させるためには、それぞれの活動の始まりと終わりの時間を必ず記載するようにします。先ほどの例を修正すると、以下のようになります。
- 宿題 15:30~16:00
- おやつ 16:00~16:15
- 運動(集団プログラム) 16:15~16:45
- 帰りの会 16:45~17:00
こうすることで、支援員は子どもたちに何時までに今の活動が終わり、次の活動に入るのかを伝えることができます。言い換えると見通しを持って子どもたちに関わることができるのです。そうすると子どもたちも落ち着いて、次の活動に移ることができるでしょう。結果として、事業所全体が落ち着いた雰囲気になり、個々の子どもたちの発達を支援できる体制が整うことになります。
タイムテーブルを作るうえでの3つのルール
こうしたタイムテーブルを作るには、以下の3つのルールを決めておく必要があります。
① 子どもたちの来所時間を明確にする
タイムテーブルとは別に、その日何時にどのお子さんがやってくるのかを書いた表を作成する必要があります。詳しくは前回の記事をご覧ください。
② プログラムの終了予定時間が過ぎても活動が終わらない子は個別対応する
おやつや宿題がタイムスケジュール通りに終わらない子は、一定数います。しかし、その子にあわせて時間を伸ばしてしまうと、次の活動が計画通りに進められなくなってしまいます。そうした子に対しては、事前に決めた見守りの担当者が対応し、次の活動には途中から参加するようにしましょう。
もし大半の子どもたちがスケジュール通りに活動を終えられないのなら、タイムスケジュール自体を見直す必要があります。
③ スケジュールを変更する権限をもったリーダーを決める
お子さんの来所時間のズレや予期せぬトラブルによって、プログラムがタイムスケジュール通りに進まない場合も多くあります。その場合、スケジュールを変更することになりますが、誰がその判断の責任と権限を持つのかをハッキリさせておく必要があります。そうでないと、支援員同士でいわゆる「お見合い」状態になってしまったり、特定の支援員が独断専行したりしてしまうためです。
そうならないために予期せぬ出来事が合った場合は、事前に決めたリーダーがスケジュールの変更を判断し、全体に伝えるのです。他の支援員は、スケジュールを変更する必要を感じても独断で動かず、リーダーに判断を仰ぐようにします。
併せてリーダーはタイムキーパーの役割も務めます。具体的には「あと5分で宿題はおわりです。運動をはじめます」といったように、全体に対して事前の声掛けを行います。こうすることで、子どもだけでなく支援員も次の行動について見通しを持つことができ、安心して動くことができるようになるでしょう。
タイムスケジュールの有無は支援のクオリティを測るバロメーター
放課後等デイを運営する難しさには、支援員が子どもたちに提供している支援が専門的かつ個別的であるため、質の高い支援が実施できているのか、経営者による評価が難しいという点があります。特に発達支援に関わったことのない経営者にとっては、自分たちの施設がどれくらいのレベルにあるのか、正確に把握することは困難です。
そこで、自事業所の運営状況を評価するうえでの客観的な指標として
- タイムスケジュールがきちんと作られているか
- 実際の支援がスケジュール通り進んでいるのか
もしタイムスケジュールが作られていなかったり、プログラムがその通りに動いていなかったりしたら、まずは管理者や児発管にその理由を聞いてみましょう。
「Aくんが活動に参加してくれないんです」「B先生がいくら言っても独断で動いてしまうんです」と、様々な理由が聞かれるはずです。それを一つ一つ解決していくことが、事業所全体として支援の質を引き上げることに繋がります。
さて、今回の記事の中ではスケジュールを変更する権限を持つリーダーを決める必要があるとお伝えしました。リーダーを決めることは、タイムスケジュールと並んで、事業所の支援の質の向上に重要な条件となります。次回はこの「リーダー」の役割について解説します。