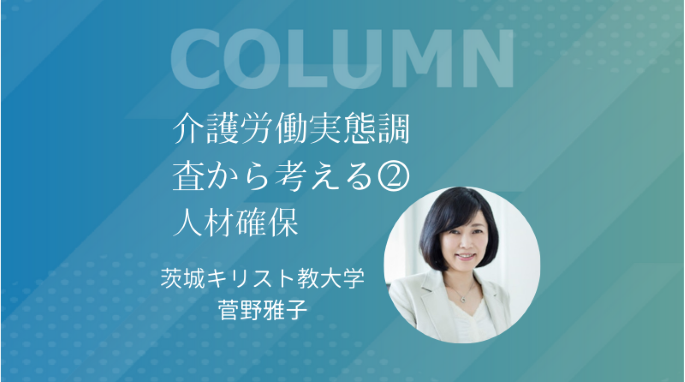事業所の人材不足感はやや減少
前回に引き続き、「令和2年度介護労働実態調査」(公益財団法人介護労働安定センター2021年8月23日公表)の結果を参照しながら、介護の人材問題について考えます。今回は、どうしたら採用がうまくいくのか、データをもとに検討していきます。
*参考:介護労働安定センターウェブサイト
まず、介護事業所の人材の充足状況を確認します。図1は人材不足を感じている事業所(大いに不足+不足+やや不足の計)の割合を経年で見たものです。この2年はやや減少している傾向がみてとれます。

とはいえ、訪問介護員80.1%、介護職員66.2%と多くの事業所が人材不足を感じている状況は変わりません。
不足している理由としては「採用が困難である」が86.6%(全体平均)となっており、深刻な採用難の問題を抱えていることがわかります。
それもそのはず、有効求人倍率が訪問介護員5.12倍、介護職5.16倍なのですから(全国社会福祉協議会・中央福祉人材センター・バンク,2021)、需給ギャップの大きさによるものであることは火を見るより明らかです。
人材の人数・質ともに確保できている事業所は2割近く
こうした採用難の状況においても、実はうまく人材確保ができている事業所もあります。表1は、過去1年間に採用した人材についての評価です。これをみると、人数・質どちらも充足していない事業所が20.2%と最も多くなっていますが、人数・質ともに確保できている事業所も17.1%と2割近くあります。

人材確保がうまくいっている事業所とそうではない事業所の違いはどこにあるのでしょうか?
施設系(入所型)と居住系、とくに大型施設は苦戦
まず主な属性別に1年間の人材確保状況を見てみましょう。表2をご覧ください。「人数は確保、質には不満」および「人数・質ともに不満」の群では、サービス系列別には施設系(入所型)と居住系で、事業所規模別にみると規模が大きいほどその割合が大きくなっています。
人数をたくさん確保しなければならないので、当然それだけ大変だということがわかります。仮に人数合わせはできても、質の確保はなかなか難しいということもわかります。

人材確保と定着状況は、強く関連している
もう一度、表2に戻り、今度は一番下の「人材の定着状況」別の数値を見てください。すると、「人数・質ともに満足」の群では「定着率は低く困っている」の割合が低いこと、「人数は確保、質には不満」の群では「定着率は低いが困っていない」の割合がかなり高いこと、「人数・質ともに不満」の群では「定着率が低く困っている」の割合がかなり高いことがわかります。
つまり、人材の定着状況が良い事業所は採用もうまくいっていると解釈することができます。実はこの傾向は、この10年以上ずっと変わりません。
採用がうまくいっている事業所は、採用の工夫を行っていない?
採用がうまくいっている事業所は、どのような採用方法をとっているのでしょうか。
この点については、平成30年公表の「介護労働実態調査(特別調査)」の分析をもとに述べます。
*参考:介護労働安定センター「平成29年度介護労働実態調査(特別調査)」
表3は訪問介護員、表4は介護職員の採用方法の工夫について、人材確保状況別にみたものです。
過去1年間に採用した人材の人数や質について、訪問介護員・介護職員いずれも「人数・質ともに確保できている」事業所は、採用の工夫に関する選択率が全体に低く、「とくに行っていない」だけが相対的に高いという結果でした。
逆に人材確保がうまくいっていない事業所は、採用の工夫に関する選択率が全体に高く、採用条件のこだわりを緩めて幅広く人材を求め、様々な採用の工夫を行い、頻繁にコストをかけて採用活動を行っている状況を確認することができます。
クロス集計なので因果関係は特定できませんが、人材確保がうまくいかない→ハードルを下げて採用する→ミスマッチによる離職が増える→新たな採用活動を行う・・・というように悪循環に陥っている可能性も考えられます。
前回も指摘しましたように、ミスマッチ人材は採用・教育コストの負担や、現場の士気の低下といった悪影響も生じやすいので、この点にも注意が必要です。


急がば回れ。魅力ある職場作りが、人材確保のカギ
以上を総合的にみますと、採用方法にコストをかけてあれこれ戦術を考えたり、入口のハードルを低くしたりすることよりも、むしろ働きやすい・働きがいのある職場環境を整備し定着率を高めることが、採用に好影響を与えることがうかがえます。
人材確保に特効薬はなく、急がば回れで、そのような職場環境整備の取組みを、継続的に地道に実施することによって、それが求職者を惹きつける最も重要な採用リソースとなると言えるのかもしれません。介護サービスは地域に根差したサービスなので、サービスの質も働きやすさも、口コミで伝播しやすいという性質が大きいためとも考えられます。
個々の法人・事業所の魅力が高まることにより、業界全体のイメージも大きく刷新されていくのではないでしょうか。
<参考文献>
・介護労働安定センター(2018)「平成29年度介護労働実態調査(特別調査)」・介護労働安定センター(2021)「令和2年度介護労働実態調査」(事業所調査)
・介護労働安定センター(2021)「令和2年度介護労働実態調査結果の概要について」(プレスリリース)
・全国社会福祉協議会中央福祉人材センター「令和2年度福祉分野の求人求職動向:福祉人材センター・バンク職業紹介実績報告」