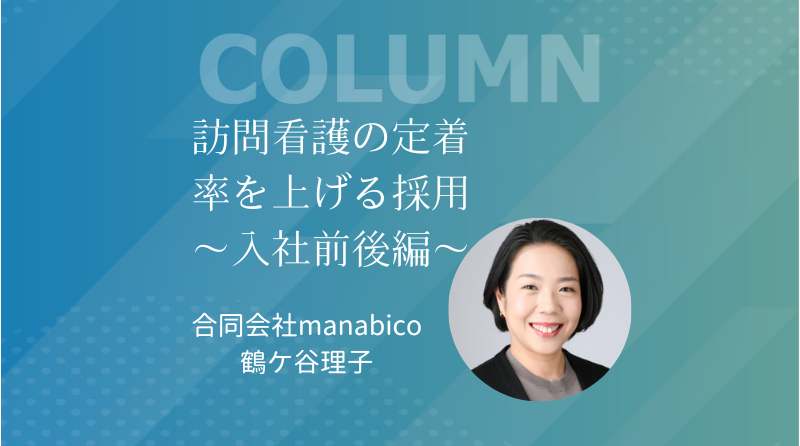これまで3回にわたり、「会社の目指す方向性や目的に合った人を採用し、その人がより活躍できるような環境を整える」ための採用について、ヒントをご紹介してきました。
今回は、採用プロセスの第三段階である「定着」について説明をしていきたいと思います。
訪問看護ステーションの定着に影響する要因
前々回触れたように、訪問看護ステーションにおいては普通、採用した人材は入職時のオリエンテーションや引き継ぎのための同行訪問等に従事します。そのため、新入社員が既存職員と同等の稼働率になるまでには、数カ月かかります。それまでの累積収支を黒字にするためには、少なくとも半年以上はかかると考えておきましょう。
また、採用にかかるコストは費用面だけではなく、研修や同行訪問、チーム内調整等に既存人員の時間的、精神的コストも多く割かれていると言えます。せっかく丁寧に教えたのにすぐに辞めてしまったということになれば、既存職員のモチベーションに与える影響も大きく、できれば避けたいところです。
このような理由から弊社では採用プロセスの中で定着について考慮すべき期間を「最低1年」と考えています。私の個人的な感覚になりますが、採用時のアンマッチによる離職は1〜3カ月の早期に起こり、それ以降の離職については支援体制に課題があることが多い気がします。
リアリティショックによる離職を防ぐために
訪問看護ステーションの看護師の有効求人倍率は2019年時点で3.1倍となっており、とても採用が難しい状況にあります。そのため、求職者に選んでもらえるように働きやすさや人間関係の良さ、教育研修の充実ややりがい等、魅力的な募集要項を出している訪問看護ステーションが目立ちます。
しかし、離職率に目を向けると、病院の看護師の平均は10%程度ですが、訪問看護師は平均15%前後ととても高くなっています。この原因は、入職後になって「思っていたのと違った」という期待と現実とのズレの大きさによって引き起こされる衝撃―リアリティショック―にあるのではないでしょうか。
これを防ぐためには、事前の期待をなるべく現実に近づけておく必要があります。そこでヒントになるのが、産業心理学者のジョン・ワナウスによって提唱されたRJP(Realistic Job Preview )という理論です。
RJP理論とは、就職後の現実的な働き方についての情報を求職者が事前に知ることで、【1】ワクチン効果、【2】マッチング効果、【3】コミットメント効果という3つの効果を期待することができます。

訪問看護ステーションの人材募集では「やりがいのある仕事で、お給料も高いのが魅力です。未経験者にも同行訪問があり、チームでケアをするので安心です」というような文面を見かけることがよくあります。この文章だけを読むととても魅力的な職場のような気がします。
しかし、この職場で現実的な仕事の情報を発信して人材募集をするとしたら、下記のような文面になるかもしれません。
「ターミナルや医療依存度の高い利用者が多く、やりがいとお給料は高いですが、オンコールや緊急対応への対応等の負担は大きいです。同行訪問やプリセプター制をとっていますが、基本的に1人で訪問して看護を行う業務ですので最低限のフィジカルアセスメント能力は必須となります。事業所内だけではなく多職種連携によるチームでのケアを大切にしているので、まめな報告・相談が必須のお仕事です」
先に示した文章とはずいぶん異なる印象を受けるのではないでしょうか。
実態がこのような職場だった場合には、良い面ばかりを強調した募集に期待を膨らませて入職した職員が、直面する現実にショックを受けてしまうことが容易に想像できます。しかし、現実的な仕事の情報を伝える募集をした場合は、そういったリアリティショックを防ぐばかりではなく、会社の提供する労働条件が合わない人や職場で求められる能力を持っていない人を採用せずに済みます。
また、良い条件ばかりが目立つ求人情報の中で、職場の良い面だけではなく現実的な情報を載せている会社は求職者にとって誠実に映り、ポジティブな評価に繋がるのではないでしょうか。特に、自身が誠実でありたいと考える人にとっては入社後の高いコミットメントへとつながります。
以上のことから、人材定着は募集の段階から始まっているということが分かります。繰り返しになりますが、いくら容易に人が採用できたとしても、その後に定着しなければ会社の成長にも課題解決にもつながりません。ですので、採用は定着とセットで考えることが重要になります。
支援体制としてのオンボーディング
最後に、オンボーディングについて説明をしていきます。オンボーディングとは船や飛行機等の乗り物に乗っているon-boardという言葉から発生した言葉です。新しく会社や組織に入った人材がスムーズに職場に慣れてもらうことで組織への定着を促し、少しでも早く戦力化していくことを目的として行う取り組みのことです。ですので、新入職社員研修だけではなく面談や懇親会等も含んだ考え方になります。
オンボーディングを考えるのにあたり、次の4つの要素が重要になります。

まず何よりも、新しい職場で自分が歓迎されていると思えるようにすることが重要です。そのためにはオンボーディング・プログラムの開始は早ければ早いほど良いでしょう。新入職社員が自信を持って仕事ができるような快適な環境を作ることが肝心です。そのためには一人ひとりの仕事と会社全体のミッション、ビジョン、ゴールとの関わりを意識することができるように期待される役割を明確にしてくことと、従業員が順守すべき規則、方針、手順を明確化して説明しておくことが必要になります。そうすることで、新入職社員は企業文化と自社での仕事のやり方を理解することができるようになります。また、既存の人間関係の中にポンと1人で入っていくのはとても勇気がいることですので、職場での人間関係の土台を築くためのサポートも必要不可欠です。職場での人間関係を築くことによって、チームで円滑に仕事を進められるようになります。
いくら仕事や会社とマッチングしていても、新しい職場で仕事を始める際は誰しも不安を感じるものです。ですので、その人がより活躍できるよう支援することは定着を促すためにとても重要なことと言えます。
今回までの3回を通して、従業員満足と利益の獲得を同時に達成するサービスプロフィットチェーンを実現するための採用について説明をしてきました。
御社の目指す方向性や目的に合う方を採用し、その人がより活躍できる採用プロセスを確立するヒントになれば幸いです。
参考文献
・ 服部泰宏(2016)『採用学』新潮社
・ 公益社団法人 日本看護協会 広報部. News Release. 2021年2月17日(2022/07/21)
・公益社団法人 日本看護協会 訪問看護の伸び悩みに関するデータ. 2011年7月13日.(2022/07/22)
・シナゾ・シビシ 2022-05-19.Harvard Business Reviewオンボーディングの改善を通じて、新規採用者の定着率を向上させる(2022/08/23)
・ジェームズ・M・シトリン 2021-07-13.Harvard Business Review“新入社員がリモート勤務の初日から活躍できるように、企業はどう支援すべきか(2022/08/23)