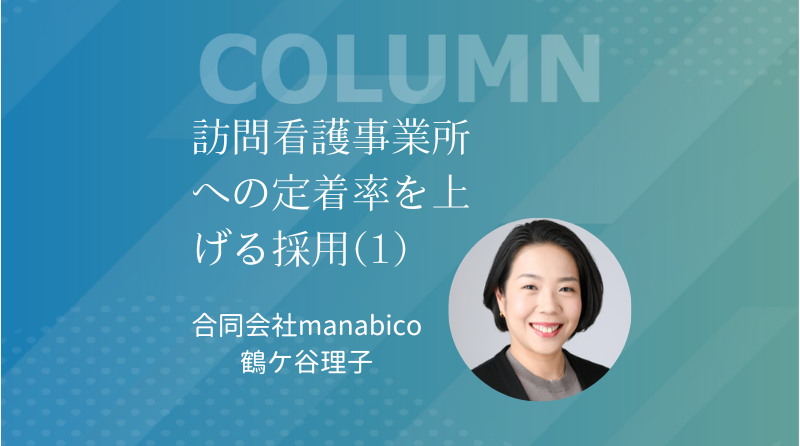前回は、従業員満足と利益の獲得を同時に達成するためにヒントとしてサービスプロフィットチェーン(以下、SPC)という考え方をご紹介しました。
今回から3回にわたって、SPCの実現において最も大切な「会社の目指す方向性や目的に合った人を採用し、その人がより活躍できるような環境を整える」ことをどうやって実現したら良いのか、特に採用についてのヒントをご紹介していきます。
訪問看護師の定着を見据えた採用活動の流れ
採用と聞くと、「ハローワークや人材紹介会社に募集を出して、応募してきた人を面接し良い人を採用する」といった一連の流れを思い浮かべる方が多いと思います。弊社ではこれに加えて、定着までを採用プロセスの中に組み入れて設計することをお勧めしています。

採用で考えるべきコスト
なぜ、定着までを採用プロセスに組み入れることをお勧めしているのかというと、せっかく採用しても定着をしなければいつまで経っても採用の目的である組織としての成長や現場の人材不足等の課題解決につながらないからです。
また、採用には多大なコストが掛かり、そのコストを取り戻すためには一定期間が必要だということも大きな理由です。採用した職員が職場や業務に慣れ、同行訪問ではなく単独で訪問できるようになり、かつ、それまでかかった費用を回収するまでには少なくとも数カ月はかかります。
一般的に、訪問看護ステーションでは40〜60%程度の稼働率(所定勤務時間内に算定できる業務を何時間行なっているかで算定)で単月での損益分岐点を超えると考えられます。例えば8時間勤務であれば3.2〜4.8時間の訪問(60分訪問2件、90分訪問1件等)というようなイメージです。採用すると入職時のオリエンテーションや引き継ぎのための同行訪問等によって、既存職員と同等の稼働率となるためには数カ月かかることが普通です。数カ月経過して損益分岐点の稼働率になっても、それまでの累積収支を黒字にするためには少なくとも半年以上はかかると考えられます。
また、採用にかかるコストは費用面だけではなく、採用後の研修や同行訪問、チーム内調整等にも既存人員の時間的、精神的コストが多く割かれていると言えます。せっかく丁寧に教えたのにすぐに辞めてしまった、というのは既存職員のモチベーションへの影響も大きくできれば避けたいところです。
以上のような理由から、採用を考える際には定着までセットで考慮して設計していくことがとても重要だと言えます。
採用を行う目的とは
まず、募集を開始する前にそもそも何で新しい職員を募集したいのか?ということについても考えておくべきでしょう。
産業・組織心理学系の研究において採用とは「企業内でなんらかの労働需要が発生、あるいは将来、発生する可能性に対して外から労働力を何らかのかたちで調達してくる活動」と定義されています。具体的には、新しい人を採用することで『組織の目標を達成する』ということと、『組織を活性化させる』ことが目的であることが多いようです。
『組織の目標を達成する』ためというのは簡単にイメージがつくと思います。「営業活動が順調で新規依頼が来るが、既存の人員だけでは近い将来対応が難しくなりそうだから新たな職員を採用しよう」などという場合がそれにあたります。
それでは『組織を活性化させる』というのはいかがでしょうか?経営学の古典的研究において、組織や集団は「同質」「似た人」「共通の目標を持った人」を好む傾向があります。そのため、時間と共に同質化への圧力が強くなり、外部に対して閉塞的になり、馴れ合いによって活発な意見交換が生まれにくくなるという結果が報告されています。そこで、新しい職員が入り、組織に対して良い意味での緊張感を生み出すことで閉塞感と硬直性を打ち破る役割を果たしてくれると考えられています。
定期的に新しい職員を受け入れることは、外に開かれ活性化した組織を保つために重要と言えます。
自社において採用するべき人材像の明確化
それでは、自組織の目標を達成し、組織を活性化させるためにどのような人を採用すれば良いのでしょうか。前回、サービスプロフィットチェーンを実現するという目標を達成するためには「会社の目指す方向性や目的に合った人を採用し、その人がより活躍できるような環境を整える」という事が重要だとご説明しました。採用するべき人材像においても「会社の目指す方向性や目的に共感し、自組織で活躍できるのはどういう人材か」という視点を持つことが鍵になります。具体的には、下記図のように様々な側面で問いを立てて採用したい人材像を明確化してみると良いのではないでしょうか。

募集段階においては、自組織に必要な求職者を惹きつけ、来てほしくない求職者が応募して来ないようにすることが重要です。そのためには、労働条件や必要となる技能や経験等を具体的に明示することが大切です。ただ、必要となる技能や経験に関しては、今は無くても今後自ステーションで伸ばすことができれば大丈夫というものもあるので、そういった記載をしておくことでターゲットを狭めすぎない工夫も可能となります。
訪問看護ステーションの職員をどこで募集をするか?
自社で採用したい人材像が明確になったら、どのようなメディアを活用して募集をかけるのかを考えます。前提として、採用したいターゲットに募集情報が届かないといけません。ですので、その人材がどこで求職活動をしているのか想像してみます。看護師の採用は主に下記図のようなメディアを活用することが可能だと考えられます。

弊社では人材紹介会社の活用に関する費用負担感についてご相談を受けることが多くあります。確かに、人材紹介会社を活用すると紹介料として多くの費用がかかります。しかし、看護師の転職において人材紹介会社の利用はポピュラーですので大勢の人が登録されており、かつ看護師の転職に詳しい担当者の方から良いアドバイスをもらえて力強い味方になることもあります。
また、社員や知人の紹介によるリファラル採用に力を入れている事業者さんも多くみられるようになってきました。リファラル採用は会社にとってはその人となりや経歴、持っている技能を信頼できる他者から情報収集でき、かつ採用される人にとっても労働条件や実際に必要な技能等を事前に知ることができるので採用後のアンマッチが起こりにくいと考えられます。ですが、元々友人関係だったのが採用後に役職の違いによって不満が起こる、親しい友人だったが同僚になってみたら合わなかった等の人間関係の不和が起こりやすいというようなリスクもあります。
このように、それぞれメリットデメリットがありますので自組織の状況に合わせて上手に活用をすると良いでしょう。
今回は、採用プロセスの全体像を説明し、第一段階である募集について詳しく説明をしました。次回は、採用プロセスの第二段階の選抜について詳しく説明をしていきたいと思います。
参考文献
• 服部泰宏(2016)『採用学』新潮社