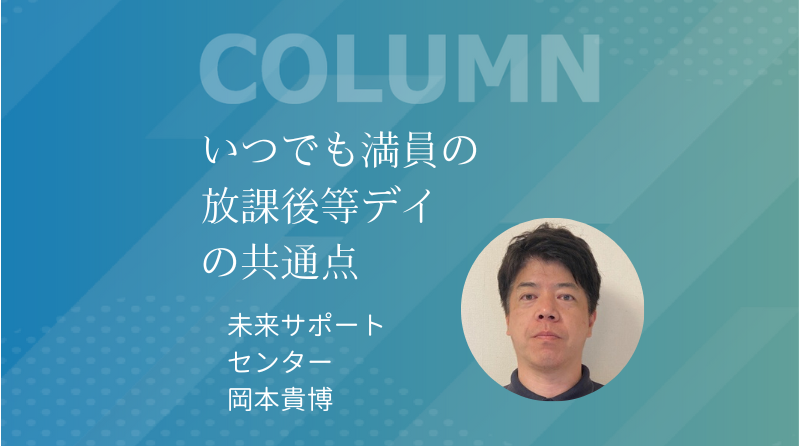前回、放課後等デイサービスを巡る2024年4月の報酬改定の方針と対応についてお話をさせていただきました。今回は、より具体的な内容についてお話しします。
法改正以降、事業所の方からよく「これから必要とされる放デイってどんなものですか?」と、質問をお受けします。しかし、この質問に明確なお答えを返すことはできません。なぜならば、答えは地域の子どもや保護者たちのニーズなどによって、大きく変わるからです。
そこで今回は、「これから必要とされる放課後等デイサービスとは何か」という問いに対する答えを皆様それぞれが出せるようお手伝いができればと思います。
前回に引き続き、法改正や報酬改定にも触れながらお話しします。
法改正以前も以後もキャンセル待ちの放課後等デイサービス事業所の共通点
法改正以前、そして改正後も変わらず、毎日定員がいっぱいの事業所には次のような共通点があります。
- 個別支援計画書に定めた内容が明確である。
- 明確な療育プログラムを作ることができている。
- 保護者と面談がきちんと出来ている。
- 従業員の定着率が高い。
- 学校等と良い関係が築けている。
すべては個別支援計画から始まる
人気のある事業所の共通点として、はじめに個別支援計画書への明確な記載を挙げました。個別支援計画が明示されていることによる直接的なメリットは、児童指導員や保育士がスムーズに児童と関わることができて、適正な療育支援がしやすくなることです。
また、個別支援計画の内容を明確にするには、児童発達支援管理責任者による保護者とのコミュニケーションが必要です。しっかりとしたコミュニケーションをとる過程で、保護者との間に信頼関係を築くことができます。さらに、方針を具体の計画に落とし込む際には児発管と児童指導員・保育士との間で、密な情報交換が必要です。そのとき、個別の児童について共通認識を持つことができ、従業員間の信頼関係を築くことができます。
しっかりと児童や保護者と関わることができていれば、学校等とも関わりスムーズに情報交換が行える余裕が生まれるでしょう。

個別支援計画が明確に定めてある、そのためのプロセスを適切に踏んでいるということは、事業所が児童指導員・保育士にとって働きやすい環境を整えることができるということでもあります。
先進的な放デイ事業所に制度が追いついた
4月の法改正でこども家庭庁は、「質の高い発達支援」や「家族支援の充実」を進めていくという方針を示しました。地域で求められる事業者の共通点と一致していることがわかります。
常に定員いっぱいの事業所様は、すでにこうした方針を見据えて取り組みを積み重ねているのです。
結果として、保護者や学校等からの評価が高まり、口コミが広がり、集客活動をせずとも、自然に児童が集まってきます。また、児童指導員や保育士がやりがいをもって働いているため、退職も少なく、それがためスキルも向上し、サービスの質が高まる好循環が生まれています。
法・制度改正が示すメッセージ:「『託児所』『タクシー代わり』の放デイは退場を」
一方で、普段私が関与している事業所の方からは、“共通点”に挙げた取り組みについて、いずれも実践できていないという声もお聞きします。実は、同じ状況にある事業所は多いのではないでしょうか。行政側もそうした事業所の存在を把握しています。
こうした取り組みができていないと、以下のような懸念があります。
- 明確な個別支援計画がないと…児童が抱えている課題について児童指導員・保育士が根本的な解決の糸口を掴めず、場当たり的な支援をしてしまう。結果として同じ問題を抱えながら業務に取り組むこととなり、ストレスが溜まり、最悪の場合、虐待等につながる。
- 療育プログラムがないと…「ただただ児童が帰る時間まで預かるだけ」のサービスとなり、児童指導員や保育士という立場で児童に関わる意味を見出せなくなってしまう。結果として業務へのモチベーションが上がらない、能力アップやキャリアアップ、仕事へのやりがいなどの意識が欠如する事態を招く。
- 保護者との面談を行っていない、または行おうとしないと…そもそも法令違反であり、直ちに認識を改める必要があります。保護者や子どものニーズを把握できてない事業所は多くの場合、保護者の御用聞きになっていたり、いわゆる「託児所」「タクシー代わり」のような事業所になっていたりします
こうした環境に慣れてしまうと、学校へのお迎えに行っても、職員が学校の先生と引き継ぎする意味を見出せず、ただ児童を引き取るだけになるなど、学校との信頼関係も築けないでしょう。
24年4月の法・制度改正の内容からは、「この様な事業所は退場してください」という意図が読み取れます。
保護者の意識についても、今後は変容が促されることになるでしょう。「預かり目的」「タクシー代わり」のために放課後等デイサービスを利用している家庭には、今後は、受給者証が交付されない流れが起きると考えられます。
必要とされる事業所を目指すため、まずは、次のことから一つずつ意識して、取り組んでいきましょう。
□ 個別支援計画がなぜ必要かを考える。
□ 全員同じ内容になっていたり、何年も同じ内容になっていたりする個別支援計画を見直す。
□ 児童発達支援管理責任者の業務を理解する。
□ 普段行っている支援内容を全て文字に起こし、療育が実践できているのか、個別支援計画に沿った取り組みになっているのかを考える。
□ 保護者との定期的な面談の機会を作る。
□ 保護者があなたの事業所を利用している理由を考える。
□ 全従業員にこども家庭庁から示されている「放課後等デイサービスガイドライン」を見てもらう。
必要とされる事業所になるには、特別なことをする必要はありません。放課後等デイサービスの制度を理解し、実行することが近道です。
次回は介護事業者様が事業で培ったノウハウと人材資源を活用できる重症心身障がい児対象とした放デイサービスの開業についてご紹介します。