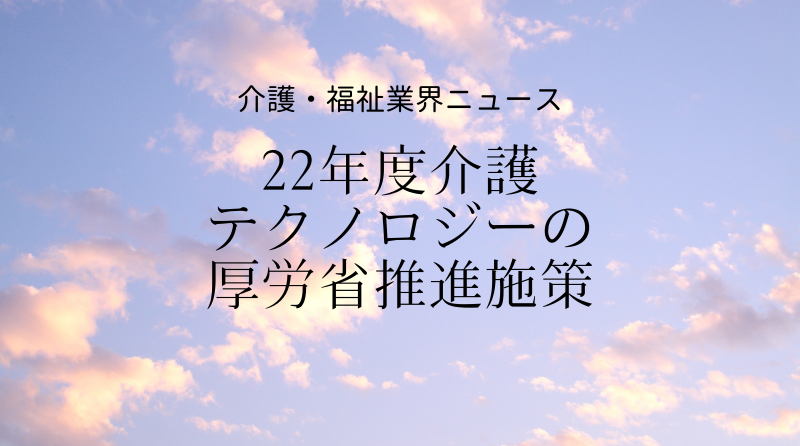2022年1月26日、テクノエイド協会による「介護ロボット全国フォーラム2022」が開催され、厚生労働省の介護テクノロジー関連政策に関する報告がなされました。介護現場の今後を取り巻く状況やこれまでの取り組みのほか、今年度以降の施策について示されましたので、整理してお伝えします。
介護人材確保に向けたこれまでの厚労省施策
高齢社会が進行する中、2040年の必要介護職員数は約280万人に上ります。19年度の実績値とは約69万人の開きがあり、この受給ギャップを埋めるため、厚労省は5つの柱に沿った施策を総合的に取り組んできました。

【画像】介護ロボット全国フォーラム2022・厚労省の講演資料より抜粋(以下・同様)
このうち、「離職防止・定着促進・生産性向上」に向けた施策のひとつとして「介護ロボット・ICT等テクノロジーの活用推進」が掲げられ、現場における見守り機器等の導入などが推進されてきました。
2021年度介護報酬改定でも、見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算の要件緩和や、テクノロジーの活用に伴う一部夜間人員基準の緩和等が実施されています。

現場における介護テクノロジーの導入状況、見守り機器でも導入実績は3.7%
フォーラムでは、厚労省の須藤明彦高齢者支援課長が、介護現場のテクノロジーの導入状況に関する調査データを提示しました。
介護ロボットに関して厚労省は、経済産業省と連携して重点的に開発支援する6分野(「移譲支援」「移動支援」「排泄支援」「見守り・コミュニケーション」「入浴支援」「介護業務支援」)を特定しています。
示されたデータは、2020年度時点のこの分野における介護ロボットの導入率を調べたもので、実に80.6%が「いずれの介護ロボットも導入していない」と回答しています。導入率がもっとも高かった「見守り・コミュニケーション(施設型)」でも3.7%(回答者を入所施設のみに絞った場合は16.6%)と、現場への実装は進んでいません。


介護テクノロジー関連の2022年度推進施策
このフォーラムでは、厚労省の今年度以降の施策についても大枠が示されました。紹介されたのは、主に以下の3つの施策です。
(1)介護ロボット開発等加速化事業(介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム)
この事業について須藤課長は、「(介護機器等の)開発・実証・普及については、しっかりと現場のニーズやシーズを把握しながら実際に現場で使用してもらえる開発を加速化させる必要がある」との認識を示しました。
その上で、介護ロボットの開発や普及を加速化するために、①相談窓口(地域拠点)、②リビングラボネットワーク(※)、③介護現場における実証フィールドの3つからなるプラットフォームの整備に向けた施策を継続していく方針を示しました。
※開発実証のアドバイザリーボード兼先行実証フィールドの役割を担う拠点、ネットワークのこと

(2)地域医療介護総合確保基金による導入支援
事業者に対する介護ロボット等の導入支援としては、各都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金が活用され、予算や支援内容が年々拡充されています。2022年度でも、職員の負担軽減や業務効率化に向けた支援を継続して拡大する方針が示されました。

また、介護施設等の大規模修繕が介護テクノロジー導入のきっかけになり得る可能性を踏まえ、大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造)の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入が補助対象に追加されています(23年度まで実施)。
(3)テクノロジーを活用した福祉用具の開発・導入支援体制の強化
福祉用具分野においても、テクノロジーを活用した器具の提案が急増しており、今後さらにICTを導入した福祉用具の開発支援や推進を図る方針が示されました。
直近の事例として、須藤課長は2021年11月に開催された「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」で、介護保険の対象となる福祉用具の販売種目として、新たに「排泄予測支援機器」が承認された点に言及しました。
この「排泄予測支援機器」とは、超音波センサーを腹部に貼ることで膀胱内の尿の溜まり具合を可視化し、排尿タイミングを知らせる機器です。

テクノロジーを活用し、要介護者のQOLの向上や介護者の負担軽減が期待される本製品が介護保険の適用となった点は極めて画期的であり、介護現場へのテクノロジー技術の実装を目指す方向性を指し示した形といえます。
約10年ぶりとなった新種目の追加やICT機器の推進する背景等を踏まえ、須藤氏は「テクノロジーを活用した福祉用具が介護現場の中でどう使われ、利用者の方々のためにどう影響し、介護従事者の方の負担軽減にどう繋がっていくのか、さまざまな側面から検討を進めていく」と述べ、講演を締めくくりました。