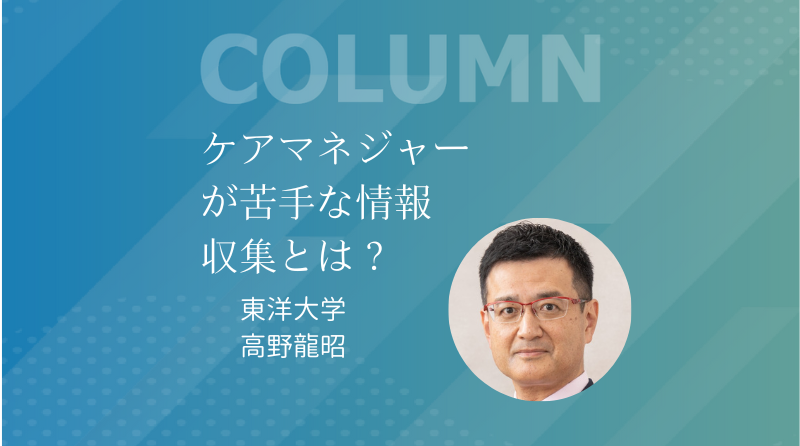このコラム(連載)は、高齢者社会ラボによる『介護の質の評価に関する調査』(以下「本調査」)の結果から、私が「気になるポイント」を示しながら、介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」)の実務に役立つ論考を行うものです。
私自身、ケアマネジャーとしての実務経験もあり、実践現場のケアマネジャーのみなさんは今も「仲間」だと思っていますから、その意味であえて「耳の痛い」話を含めてお示ししている連載です。
今回(第4回目)は、前回に引き続き、ケアマネジャーの中核的な業務と言ってもよい「アセスメント」について、その「情報収集」における課題について考えてみます。
ケアマネジャーは「口腔機能」「栄養状態」の把握が苦手?
私は、いくつかの保険者(市町村)で地域ケア個別会議のアドバイザーを務めたり、介護給付費適正化事業(「ケアプランの点検」など)の委託を受けたりすることがあります。そのため、ケアマネジャーのみなさんが作成したアセスメント表やケアプランなどに直接触れる機会が多く、事例検討としてそれらの内容について議論することがしばしばあります。
その際、気になっていることのひとつに「ケアマネジャーが利用者の口腔機能や栄養状態を見過ごしている」という点があります。口腔機能は、ケアマネジャーであれば誰しも知っている“標準23項目1)”に含まれています。また、栄養状態は、 “フレイル”に影響を及ぼす要因のひとつとして近年対策の重要性が強調されています。高齢者介護・医療の専門職が注意しておかなければならない常識的なポイントです。したがって、ケアマネジャーがアセスメントを実施する際、これら2点の情報収集をしておくことは不可欠な点と言ってよいはずです。
しかし、私が経験する事例検討では、誤嚥のある高齢者のアセスメントにおいて、口腔内の状態や口腔の機能を確認しないまま食事形態のことばかりを考えているケアマネジャーは珍しくありません。また、筋力低下をきたしている高齢者のアセスメントにおいて、栄養状態を確認しないまま筋力増強訓練のための通所サービスをケアプランに位置付けているケアマネジャーも少なくありません。
これを裏付けるかのようなデータが本調査で報告されています。たとえば、「アセスメント時の情報収集」において「口腔衛生」に関する情報を「十分に収集している」と回答したケアマネジャーは43.2%にとどまるとともに、同じ設問の選択肢(全27肢)のなかでその回答の比率は少ない方から5番目となっています(グラフ1)。また、「サービス担当者会議の参加者」については、「栄養指導員」が「毎回参加している」「たまに参加している」と回答したケアマネジャーは合わせて23.5%にとどまっています(グラフ2)。

(【グラフ1】高齢社会ラボ「介護の質の評価に関する調査(アセスメント編)」より)

(【グラフ2】高齢社会ラボ「介護の質の評価に関する調査(ケアプラン~モニタリング編)」より)
前者の調査結果・回答については、ケアマネジャーが利用者の口腔機能への関心の優先度が低いことを示唆し、後者の調査結果・回答は、ケアマネジャーが栄養指導員(管理栄養士や栄養士など)を担当者会議の重要なメンバーだと認識していない、あるいは栄養指導員がケアマネジャーの作成したケアプランにあまり関心がないことを示唆しています。いずれにしても、ケアマネジメントにおいて口腔機能や栄養状態に関するアセスメント・情報収集が手薄であることを示していると考えられます。
口腔機能や栄養状態は「生活の質」に影響する
口腔は、①咀嚼・嚥下、②コミュニケーション(発語のための器官・機能)、③外部の病原体(ウイルスや細菌など)や毒物から身体を守るといった機能があります3)。つまり、口腔の状態は生活のなかでの大きな楽しみである食事摂取に影響を与え、生活の手段であり社会参加にも重要なコミュニケーション機能を担い、対人関係に影響を与えます。さらには、ウイルスなどの感染から利用者を護る、すなわち命を護る役割も果たす器官です。
今回の調査は、コロナ禍の第6波と第7波の中間の時期(2022年5〜6月)に実施されています。この時期のケアマネジャーが、上記③の意味で、利用者の口腔衛生・口腔機能の情報収集を怠っていたとすれば、大変に残念なことです。
一方、栄養は単に医学的な問題という側面だけでなく、その状態が悪化すると精神的機能・社会的機能の低下もきたします。また、栄養状態の低下は、社会とのつながりが乏しくなったり、経済的状況が悪化していたりする状況を示す場合もあります4)。さらに、機能訓練(筋力増強訓練など)を行う際には、BMIが一定水準以上でなければそれを避けるべきであるということが近年の高齢者介護・医療分野での常識となっています5)。こうした観点から、栄養状態はケアプラン作成におけるアセスメントの重要な領域と言えるでしょう。
つまり、口腔衛生や栄養状態は、利用者(高齢者)の「生活の質」に大きな影響を及ぼす領域であり、ケアマネジャーはアセスメント・情報収集において一定の関心を払うべき点だと言えるのです。
まとめ:まずは利用者の口腔内の様子の確認を
口腔衛生の状況や栄養状態は、ケアマネジャーの行うアセスメント・情報収集で極めて重要なポイントなのですが、その情報収集などにさほどの関心が払われていないことが本調査から明らかになりました。
おそらく、多くのケアマネジャーはそれらの分野を「医学的な分野であるため苦手だ」と感じているのかも知れません。この連載のコラムの第2回で示したように、ケアマネジャーの大多数は社会福祉分野の専門職(介護福祉士や社会福祉士など)であり、それは致し方ないのかも知れません。しかし、生活の質を高めるための支援を行うケアマネジャーとしては、この点にもう少し注意を払い、アセスメントと情報収集のための工夫と努力をして欲しいと思います。
私からアドバイスするとすれば、口腔衛生については、アセスメントやモニタリングの際に「利用者に口を開けてもらって、口腔内の様子を見る」ことをまずお勧めしたいと思います。医療面に詳しくないケアマネジャーであっても、歯や歯肉、舌や上顎の表面などに異常がありそうか否かは目視で概ね理解できます。異常があれば、歯科医療関係者(あるいは耳鼻咽喉科医療関係者)に照会すれば良いのです。
また、栄養状態については、定期的に身長・体重を聞き(それを測定する方法も検討する)、BMIを算出することです(一般にBMIは18.5~25が正常範囲)。そして、1日の食事の回数を確認しましょう。それだけでも最低限の情報収集となるはずです。
このコラムをきっかけに、多くのケアマネジャーのみなさんに口腔衛生と栄養の情報収集・アセスメントに関心を深めていただきたいと思います。
【注】(参考文献)
1)厚生省老人保健福祉局企画課長通知「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(別紙4)」(平成11年11月12日・老企第29号) および 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』の一部改正にについて」(令和3年3月31日・老認0331第6号)
2) 飯島勝矢「より早期からの包括的フレイル予防」『健康長寿ネット(長寿科学振興財団WEBサイト)』https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/chokoureishakai/chokoureishakac-frailtyyobou.html (2023年3月31日閲覧)
3) J.N.モリス・池上直己他(著)/池上直己(訳)『MDS-HC2.0在宅ケアアセスメントマニュアル新訂版』p148,医学書院,2004
4) 同掲書,p143
5) J.N.モリス・池上直己他(著)/池上直己(監訳)/石橋智昭・山田ゆかり(訳)『インターライ方式ケアアセスメント』pp199-204,pp303-307,医学書院,2011