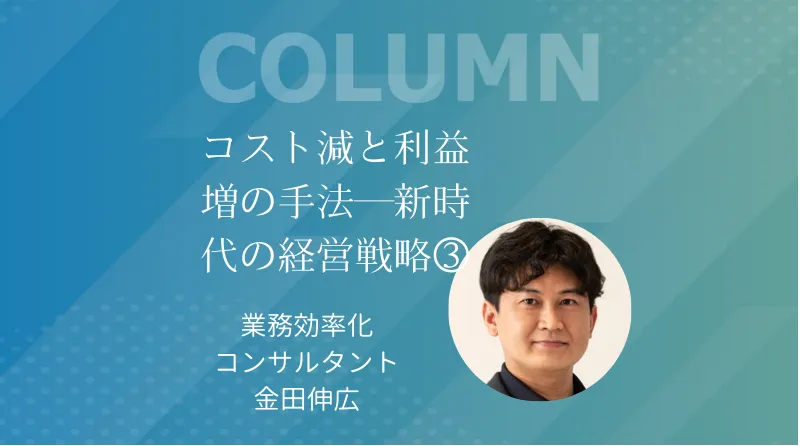これまで、介護事業を取り巻く厳しい環境にどのように立ち向かうべきか、国の動向を踏まえながら、新しいサービス・技術の活用して強い組織を作っていく“新時代の介護経営”について提案してきました。
*連載第1回:一過性の人材補填を越えた「投資」としてのスポット採用―新時代の介護経営戦略①
*連載第2回:人材不足の突破口?管理者の兼務や人材シェアという手法
最終回の今回は、コストを削減と利益を改善を図り、持続可能な経営を実現するのための4つの戦略について、事例を踏まえながらお伝えします。
これから求められるのは地域に合わせた柔軟な対応
日本は2040年に高齢者人口のピークを迎える一方で、生産年齢人口はその後も減少し続けます。しかし、減少のピークは地域ごとに異なり、すでに高齢者数が減少している地域もあれば、今後増加する地域も存在します。
介護事業者には、事業所単位で業務効率化を進め、質の高い介護サービス提供を追求するだけでなく、地域特性に合わせた戦略の立案や柔軟な対応が求められています。
戦略①新サービスの展開:保険外サービスの振興と先進事例
地域に必要とされる存在であり続けるための一つの戦略として、新たなサービス展開を模索するという選択肢があります。
そこで、まず注目すべきは保険外サービスとの連携強化です。
経済産業省が主導している保険外サービスの振興に見られるように、今、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせた新しい事業モデルの創出が期待されています。
例えば、訪問介護に加えて家事代行や買い物代行などの保険外サービスを提供することで、利用者の生活全般を支援する包括的なサービスが可能になります。
そのほかの切り口としては、リハビリサービスの拡充も挙げられます。介護保険では要介護度改善をアウトカムとして評価する動きが今後も顕著になるであろうことから、結果を残していく必要があります。
その点で、関心を集めているのが、旅行とリハビリを連動した動きです。デイサービスなどでリハビリを重ねながら、旅行を保険外サービスとして提供し、日頃のリハビリの成果を発揮する場にする取り組みです。(*参考リンク:株式会社エルダーテイメント•ジャパン )
また、「旅行介助士」(*参考リンク:一般社団法人日本介護旅行サポーターズ協会 )の育成として提供されている専門的な研修プログラムの導入も、新たな付加価値を生む取り組みとして注目されています。 このようなモデルは、収益源の多様化にもつながります。
戦略②:テクノロジーの活用で加算を漏れなく算定する
AI活用で介護事業所の業務効率化と収益向上を図る
介護報酬改定が3年に一度行われるこの業界では、改定された加算の取得と管理も重要な課題です。
年々複雑化している加算の算定要件や報酬体系に対応するため、今、AIの活用が注目されています。膨大なデータを瞬時に分析し、加算算定に必要な項目を自動で提案してくれるものです。
例えば、自動で口腔機能の評価を実施するAIツールを活用して口腔機能向上加算を算定したデイサービスで、結果的にひと月の収益が21万円増加したという事例があります(*参考リンク:株式会社エクサウィザーズ「CareWizトルト」)。
加算の算定からは逸れますが、AIは過去のデータを基に利用者の特性やニーズを予測し、適切なサービス提供計画を立案する支援もできます。株式会社シーディーアイが開発したAIケアプラン作成支援システム「SOIN(そわん)」の活用事例では、状態改善の予測を利用者に対して視覚的に伝えたことで、デイサービスの利用につながったというケースがあります。
複数拠点間で加算算定のノウハウを共有
複数拠点を運営する法人の場合、加算算定のための複雑な要件や手続きといったノウハウの共有が課題になりやすいです。効率的な情報共有の仕組みづくりが必要です。
例えば、クラウド型データベースを活用し、各施設で取得した加算項目や条件、成功事例を一元管理する方法があります。これにより、他拠点でも同様の手法を活用できる環境が整備されます。四国を中心に、関西や東京でも幅広い分野で福祉サービスを展開する健祥会グループでは、導入当時の68拠点188事業所で情報共有ツールを導入し、拠点間でこうしたノウハウを効率的に展開した結果、業務効率化とともに収益向上を実現しています。
また、すでに実施している事業所も多いでしょうが、オンライン研修や勉強会も有効な手段です。定期的に開催しているオンライン研修で、新しい加算制度や報酬改定のポイントについ情報共有した結果、加算の理解と取得までのプロセスが明確になり、取得率が向上するといった事例も存在します。
複数拠点間でのノウハウ共有は、加算取得に限らず、稼働率やサービス品質の向上などさまざまな場面で活きてきます。その意味でも、今後の持続可能な経営モデル構築に向けた鍵となるでしょう。
戦略③光熱費の削減―革新的ソリューションとしてのE M S
今度はコスト削減に目を向けてみましょう。
燃料費の高騰を受け、現在の経営上の重要課題の一つに電力コストの削減があります。 効率的なエネルギー管理をするために現場で注目されているのが、EMS(エネルギーマネジメントシステム)です。
例えば、エネクラウド株式会社が提供する「電気管理クラウド」では、独自開発のIoTセンサー「EMIΘ(エミシータ)」を活用し、電力使用量をリアルタイムで可視化することで、省エネと運営効率化を同時に実現しています。 このシステムの最大の特徴は、施設内のブレーカーや設備にIoTセンサーを設置し、セクションごとの電力使用状況を細かく把握できる点です。どの設備がどれだけ電力を消費しているかを一目で確認できるため、無駄なエネルギー消費を削減するための対策が立てやすくなります。
また、ピーク時の電力使用量を平準化するデマンド監視機能も搭載されており、基本料金削減にも効果を発揮します(*参考サイト:エネクラウド公式サイト)。
EMSの事例をもう一つ紹介しましょう。
岡山県の社会福祉法人夕凪会では、リコージャパンのEMSを導入し、空調システムの効率化に成功しました。温度設定の自動化やリアルタイムモニタリング機能により、省エネ効果と利用者満足度向上を両立させた事例です(*参考サイト:リコージャパン「夕凪会 EMS導入事例」)。
こうしたシステムの中には初期費用0円で導入可能なものもあり、中小規模事業所でも利用しやすい有効なコスト削減の選択肢といえます。
戦略④:業務プロセスの再設計―自治体による報告事例からヒントを得る
持続可能な経営を実現するには、業務プロセスの再設計も不可欠です。 その際にまず重要なのは、業務分解とタスクの最適化です。介護職員が専門業務に集中できるよう、記録作業や環境整備などの間接業務を切り分け、介護助手や事務スタッフに委任する仕組みを整えることが効果的です。
福島県は介護助手の導入を通じて介護職員が利用者への個別ケアに集中できる環境を整えた結果、サービス品質向上と人材確保につながったという事例を報告しています(*参考:福島県「介護助手導入の実践事例集」 )。
さらに、プロセスマッピングを活用した業務改善も有効です。
東京都東久留米市ではBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)の手法を用いて業務フローを見直し、作業時間を削減することに成功しました。この取り組みは要介護認定までの期間短縮という事例ですが、現場での業務改善の参考になるものです。(*参考サイト:DNP事例)。
業務プロセスの見直しを成功させるポイント
業務プロセスの見直しは、優先度は高いものの緊急度は高くありません。言い換えると、日々の忙しさを理由に、後回しにされてしまいがちです。何より、一時的に業務負担の増加などが伴います。そのため、必ずプロジェクトチームを立ち上げ、中長期的な視点で捉え小さな改善から段階的に進めることが大切です。
これからの介護経営に必要な取り組みとは
本連載では、人材不足や報酬改定にも対応できる経営の方策として、スポット採用やICT・IoT技術の活用、業務プロセス再設計の重要性を取り上げてきました。
これからの介護経営には、人間力とテクノロジーを融合させた新しい運営モデルが求められていると考えます。 激動の時代にありますが、焦らずに着実に小さな成功体験を積み重ねていくことが重要です。変化する外部環境に柔軟に対応しつつ、地域の中で事業価値を高めていきましょう。