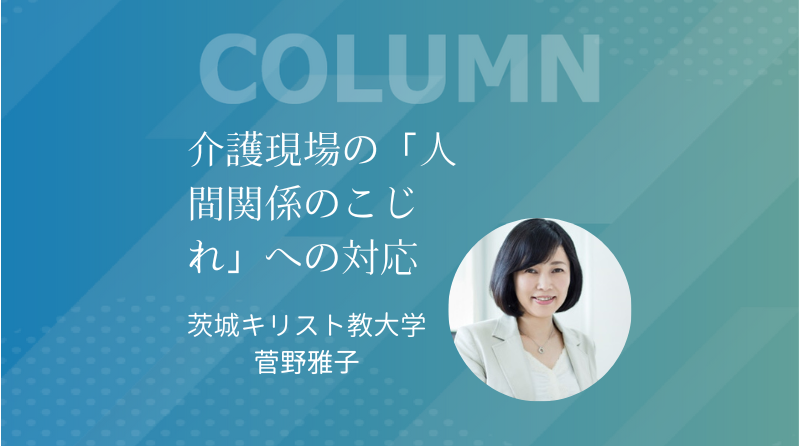引き続きこのシリーズでは、現場のリーダーや管理者からよく聞かれる悩みを題材に、介護現場で起こりやすい人材問題とその対処法について検討したいと思います。
第4回は、職員同士の「人間関係のこじれ」です。特養のフロアリーダーDさんの悩みについて一緒に考えてみましょう。
(事例は、筆者が見聞きした実話を題材にしたフィクションです)
若きフロアリーダーDさんの悩み:「人間関係の問題が、あとを絶ちません」
Dさん:「人間関係の問題は、大きなもの小さなもの色々ですが、施設の中では毎日見聞きしてあとを絶ちません。一つが片づいたかなと思うと、また二つぐらい出てきたり・・・」
やれやれという表情でため息をつくDさんは、福祉系の専門学校を卒業し、現在の社会福祉法人に入職して7年目。フロアリーダーとしては2年目の若手リーダーです。
Dさん:「トラブルとまではいきませんが、“あの人は嫌い、この人は嫌い”とか、“あの人はやる気がないから一緒に仕事をするのは嫌だ”とか、“あの人とはペースが合わないから組みたくない”とか、そんなことは日常茶飯事ですね」
Dさん:「あとは、“あの人は、リーダーがいない時はさぼっている”とか、“あの人はできない、足を引っ張る”とか、そういう告げ口のようなものもよく耳に入ってきます」
「忙しくなると、なおさらですね。誰かが休んだりすると、“また休んでいる”というような皮肉を言ったり、“あっちのフロアは暇にしている!”と文句を言ったり、誰かに何か言われると“そんなこと言ったって、こっちは忙しいんだから!”って感情的になる人がいたり・・・。」
「もう本当に、いつもそんな感じです。人間関係をどんなふうにバランスをとっていけばいいか、というのが難しいところですね」
Dさんが言うような人間関係の問題は、どこの介護現場にも多いのではないでしょうか。実際、介護労働実態調査(介護労働安定センター)の労働者調査を見ると、前職の介護の仕事を辞めた理由の第一位は、毎年「職場の人間関係」となっています。
逆に言えば、この人間関係の問題をうまく調整・コントロールできれば、人材の定着と職場の安定につながると考えることができます。
一体どう対応したらよいのでしょうか。
いつものことと放置しないで仲裁する
人間関係の問題が表面化した時は、いつものことと放置せず、まずは一次対応をした方が良いでしょう。例えば、「先輩の〇〇さんの言い方がきつくて、悩んでいる」とか、「同僚の〇〇さんとペースが合わないので、一緒に仕事をしたくない」など、メンバーの誰かから人間関係について相談があった場合などです。
他者から見れば大した問題ではないように見えても、本人にとっては精神的に追い詰められるような大きな問題であることも多いものです。また、ちょっとした人間関係の問題が、職場の雰囲気を悪くさせているということもあります。
相談したにも関わらず放置してしまうと、相談者はもう頼るすべがない、事態が改善する見込みがないと考えてしまい、離職にもつながりかねません。まずは、相談したらリーダーが話を聴いてくれた、動いてくれた、という事実が重要です。
さらに、軋轢が生じている職員の間に入って、両者の言い分を十分に聴き、仲裁して対立を収束させるなど、起きている問題を速やかに円満に解決できるのが望ましいと言えるでしょう。それぞれが、心を開いて話をしてみると、案外うまく問題を収めることができるケースも多いのではないでしょうか。
人間関係のこじれは、なぜ起きるのか
しかしながら、上述した対応は、あくまでも一次対応(応急処置)に過ぎません。火種を消したと思っても、またどこかから、別の火種が飛んできたりするのが常です。一体どうしてなのでしょうか。
それは、介護というヒューマン・サービスの特性が大きく関係しています。一つには、人と人の相互作用で成り立っているサービスであるという点です。つまりそれは、好き嫌いとか、喜怒哀楽など、生身の人間の感情から逃れられないということを意味しています。そのため、人間関係による疲労が蓄積し、ストレスとして感じることが多くなり、感情的なコンフリクトが生じやすくなります。
二つ目に、“人間”を取り扱う仕事のため、因果関係が明確ではなく、不確実性が高いという点です。つまり、マニュアルや教科書どおりにはいかないことの方が多く、仕事に対する考え方ややり方の対立や不一致も起きやすくなります。
三つ目に、労働集約的なため多忙であるという点です。多忙さから来るイライラやストレスが加われば、嫌悪感や不快感が表出しやすくなるのも無理からぬことです。
こうしたヒューマン・サービスの特性は、濃淡はあれど避けることはできないため、それを前提として考える必要があるのです。
人間関係を固定化しない
では、どうしたら良いのでしょうか。
まず「クローズドからオープンへ」というのが、一つの方向性です。介護の現場では、利用者と介護者の「馴染みの関係」を重視するため、スタッフの人事異動をあまり行わない職場も多いかも知れません。しかし、それは閉鎖性を強め人間関係の膠着状態を生み出すという側面もあります。古くからいる職員が、若手や新しい職員を受け入れないとか、これまでの方法を変えたがらないなど、変化への対応を損なうことにもなってしまいます。
単純なことのようですが、人間関係を固定化せず、例えば、人事異動やローテーションなどで定期的に人を動かしたり、チームの壁をなくし相互協力せざるを得ない体制にしたりしてみるといった方法などが考えられます。
さらには、他法人との人事交流や、外部研修等に職員を次々派遣するなど、法人・事業所外の人と何らかの交流を持つような機会を積極的に作るというのも有効でしょう。「自分たちの常識は、世間の非常識」ということに気づくこともあるでしょうし、組織外の人との人脈を広げたり、新たな知識・情報等に触れたりすることによって、組織の風通しは確実に良くなるでしょう。
ヒューマン・サービス専門職として、健全にぶつかり合う職場へ
もう一つ大事なことが、「健全なぶつかり合い」です。先にも触れたように、人間関係の問題は、感情的なコンフリクトばかりではなく、仕事に対する考え方ややり方などに関するコンフリクトから生じていることも多くあります。後者に関するコンフリクトは、徹底的に話し合い健全にぶつかり合うことによって、新たな知の創造や革新など、組織にとって、むしろプラスになることが知られています。
コンフリクトが起きやすい仕事だからこそ、ヒューマン・サービス専門職として、健全にぶつかり合うことができるような対話の場を大切にしたいものです。対話が、単に物事を丸く収めるという消極的な意味合いだけではなく、新たな知の創造や革新といった積極的かつ未来志向の組織開発につながるという点を、最後に改めて強調しておきたいと思います。